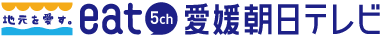NEW 2025年08月29日(金 ) 16:17
夏休み明け子どもが「学校に行きたくない」と言い出したら…大人はどうすれば?【愛媛】

夏休みがまもなく終わります。
この時期に、子どもが「学校に行きたくない」と言い出したら身近な大人はどう受け止めればいいのでしょうか。
不登校の支援などを行っている専門家に聞きました。
松山市の川内真紀さん。
学校の先生や塾講師を経て、現在は不登校の子どもたちの学習支援を行うNPO法人「ホームスクール愛媛」の理事長を務めています。
「ホームスクール愛媛」では、不登校など子どもに関する悩みについてLINEでの無料相談の窓口を設置していて、夏休み明けの9月には、保護者からの相談が増えるといいます。
この時期、子どもたちが学校への不安を感じる要因は長い休みで生活リズムが乱れたり、学習の遅れや進路への不安が大きくなること。
さらに、学校が始まると友人関係のトラブルが再び表面化することもあります。
2023年、全国で不登校の小中学生はおよそ34万6000人。
県内でもこの5年間でおよそ2.4倍に増加しています。
「学校に行きたくない」と子どもが言い出したら。
親や身近な大人はどうすればいいのでしょうか。
【ホームスクール愛媛・川内真紀さん】
「まずは慌てず落ち着いて話を聞いてあげることだと思います。『何で行かないの?』というような声のかけ方をすると子どもは責められていると思いますし、泣いてる子を無理やり手を引っ張って連れていくようなことをすると親に自分の本当の気持ちを伝えようという気持ちすら失いかねないので親子の人間関係を崩してしまうような対応はやめておいた方がいいかなと思います」
直接「学校に行きたくない」と言葉で伝えてこなくても、何らかのサインを出している子もいるといいます。
【川内さん】
「体調面に出てしまう子もいて、おなかが痛くなる、食欲がなくなる、夜眠れてないようだというような状態から顔の表情も暗くなったり視線が少し下がっていたりというところで気づいてあげるのもよいのかなと思います」
SOSを出す子どもに対しては、まず落ち着いて話を聞く。
次のステップを急かしてはいけません。
【川内さん】
「情報を親として知っておくのは大事なんですけども、例えばフリースクールもあるよ、ホームスクールもあるよ、こういうとこもあるよ、ああいうとこもあるよ、どうする?
まで言われてしまうと今子どもは新しい一歩を踏み出すような状態ではないときにプレッシャーを感じてしまうと思うので、子どもがまずご飯が少し食べられてるなとか、眠れてるなという状態になったら、こういう選択肢もあるよと、情報を子どもの目の前に置いておくような感覚で伝えるというのがいいのかなと思います」
さらに。
【川内さん】
「(学校以外に)人と関わる場所を何か一つ作ってあげる。習い事でも構わないし地域の団体活動でもいいしフリースクールでもいいし、自分の趣味の集まりでもいいと思うんですけど、孤立しないように誰かとつながる場所っていうのを作ってほしいなと思います」
この時期に、子どもが「学校に行きたくない」と言い出したら身近な大人はどう受け止めればいいのでしょうか。
不登校の支援などを行っている専門家に聞きました。
松山市の川内真紀さん。
学校の先生や塾講師を経て、現在は不登校の子どもたちの学習支援を行うNPO法人「ホームスクール愛媛」の理事長を務めています。
「ホームスクール愛媛」では、不登校など子どもに関する悩みについてLINEでの無料相談の窓口を設置していて、夏休み明けの9月には、保護者からの相談が増えるといいます。
この時期、子どもたちが学校への不安を感じる要因は長い休みで生活リズムが乱れたり、学習の遅れや進路への不安が大きくなること。
さらに、学校が始まると友人関係のトラブルが再び表面化することもあります。
2023年、全国で不登校の小中学生はおよそ34万6000人。
県内でもこの5年間でおよそ2.4倍に増加しています。
「学校に行きたくない」と子どもが言い出したら。
親や身近な大人はどうすればいいのでしょうか。
【ホームスクール愛媛・川内真紀さん】
「まずは慌てず落ち着いて話を聞いてあげることだと思います。『何で行かないの?』というような声のかけ方をすると子どもは責められていると思いますし、泣いてる子を無理やり手を引っ張って連れていくようなことをすると親に自分の本当の気持ちを伝えようという気持ちすら失いかねないので親子の人間関係を崩してしまうような対応はやめておいた方がいいかなと思います」
直接「学校に行きたくない」と言葉で伝えてこなくても、何らかのサインを出している子もいるといいます。
【川内さん】
「体調面に出てしまう子もいて、おなかが痛くなる、食欲がなくなる、夜眠れてないようだというような状態から顔の表情も暗くなったり視線が少し下がっていたりというところで気づいてあげるのもよいのかなと思います」
SOSを出す子どもに対しては、まず落ち着いて話を聞く。
次のステップを急かしてはいけません。
【川内さん】
「情報を親として知っておくのは大事なんですけども、例えばフリースクールもあるよ、ホームスクールもあるよ、こういうとこもあるよ、ああいうとこもあるよ、どうする?
まで言われてしまうと今子どもは新しい一歩を踏み出すような状態ではないときにプレッシャーを感じてしまうと思うので、子どもがまずご飯が少し食べられてるなとか、眠れてるなという状態になったら、こういう選択肢もあるよと、情報を子どもの目の前に置いておくような感覚で伝えるというのがいいのかなと思います」
さらに。
【川内さん】
「(学校以外に)人と関わる場所を何か一つ作ってあげる。習い事でも構わないし地域の団体活動でもいいしフリースクールでもいいし、自分の趣味の集まりでもいいと思うんですけど、孤立しないように誰かとつながる場所っていうのを作ってほしいなと思います」