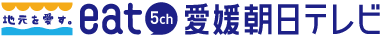第186回放送番組審議会議事録
開催日時:平成25年9月25日(金) 午後3時
課 題:「次世代テレビ時代、地上波テレビの生き残り策」
開催日時:平成25年9月25日(金) 午後3時
課 題:「次世代テレビ時代、地上波テレビの生き残り策」
・多くの資料を読んでいただきましたが、言葉では何となく聞いたことがあっても漠然としか判っていない4KとかHDTVとかフルHDなど、意味の良く判らない言葉がたくさんあります。一般消費者にとっても、またご参集の委員の皆様にとっても判らないことがたくさんあると思います。なので、最初に技術局長の西田さんからご説明いただきます。よろしくお願いします。
・次世代テレビには、スーパーハイビジョンとスマートテレビのふたつの柱があり、このふたつをセットにして総務省は進めようとしています。スーパーハイビジョンの動向としては、4K、8Kと言われている画質についてよく話されます。4Kは50インチ、8Kは100インチ相当のテレビの想定です。映画やゲームで一部4Kの動きが出ています。また、業務用プロジェクタ―や撮影用のカメラ、民生用ディスプレイなども4Kのものが発売されています。パソコンやノートパソコンのディスプレイは、現行のデジタル放送の2Kを超える商品が販売されています。国際的な流れですと、ITU-Tで4Kや8Kの放送の映像や音声の信号に関する符号の標準化を検討しています。これが終わると韓国やヨーロッパで4Kの放送機器や受像機の販売が開始され実験放送がスタートする可能性があります。すでに、韓国では昨年の秋から4Kの実験放送を実施したと聞いています。日本ではNHKやスカパーJサット、CATVも使用して様々な電送実験が行われています。2014年ワールドカップの時には、スカパーや他のCSを使用して希望する視聴者が視聴できるように環境整備を目指しています。2016年ブラジル・リオでのオリンピック時には、衛星放送、CSに加えて110度CSも活用します。2020年東京オリンピックでは、希望する人が4K、8Kの視聴を可能としたいと、比較的曖昧な表現がされていて具体的な所は不明です。また、コンテンツ提供は2016年までには4Kのコンテンツ、2020年までには8Kのコンテンツの提供が開始される予定です。加えて衛星CATVとなっているように、当面地上波のサービスについてはこの資料の検討会では検討されていません。続いてスマートテレビです。9月2日にNHKがハイブリットキャストを始めました。ホーム画面ボタンを押すことで色んな情報が得られるようです。今までのデータ放送と違うところは、このボタンを押してインターネット経由でデータを取ってくるところです。例えばEPGは8日分が出ますが、このハイブリットキャストは30日も遡って見ることができます。NHKは30日遡った中からNHKオンデマンドにアクセスするサービスを考えているようです。今年度になりスマートテレビが急に進んだ印象を持ちます。一方スーパーハイビジョンは、衛星を中心に進んで行っています。総務省の次世代テレビの検討としては、スーパーハイビジョンとスマートテレビは一体として進められることになっています。すなわち、スーパーハイビジョンが見れ、ハイブリットキャストなりスマートテレビの機能を生かせる受像機を作ろうとしているようです。なかなか難しいですね。「ハイブリットキャスト」は、始めて聞く言葉でした。局長もまだ見たことはないのですね。
・はい、現在の対応モデルは東芝レグザの10モデルと、パナソニックのビエラも対応機種が出るように聞いています。局長の話からスーパーハイビジョン、スマートテレビのように、テレビとパソコンが一体になったようなもの、むしろテレビからパソコン画面の出力ができるようになって技術的な進歩が目覚ましいですね。
・「生き残り策」と言うことですが、まず何年後を想定しているのでしょうか。20年から50年後位でしょうか。それによって発言内容は違ってきます。 さっきの局長の説明を簡単に言うと、テレビの画質がより綺麗になり、インターネットに繋がっているということですね。そうです。テレビを見ながらパソコンをする。すなわち番組に連動した形でスマートテレビに繋げ情報のやり取りを促し、視聴の動機づけを積極的に働き掛けようとしています。では、電波を使うこととインターネットを使うことは何が違うのですか。電波は1対多で出力しますが、インターネットは多くのインフラを使いながら繋げるので途中で切れる可能性があります。ならば、災害時対応が一番違うのですか。また、他のメリットは何ですか。スイッチを入れれば映像が見れるように、テレビ受像機はインターネットに比べ映像を見ることは判りやすいです。パソコンですと段階を踏みながら目的画面に入っていきます。しかし、それは設定で解決できますね。なら、視聴者からみればテレビなのかインターネットなのか将来的には判りづらいですね。はい、そうです。では、30年後と考えた場合、テレビは受信エリアしか見れませんがインターネットは、どんなに世界がグローバル化していてもリアルタイムで情報を得られますね。その時テレビは世界同時視聴ができなければ生き残りは難しいのではないでしょうか。しかし、局としての強みはコンテンツ制作力もあります。それで生き残ることも考えられます。インターネットは自分で何かを選ぶメディアです。テレビは受動的に与えられるメディアです。「与えられる」いう点で生き残っていくのでしょうね。そして何らかの文化の発生の源になる役割を持ち生き残ると思います。良いコンテンツや新しい価値観を常に提案提供、構成していき、そこに視聴者としては期待するし、それが生き残りの要素となると思います。
・番組という面からみれば、番組は人間が作るもので、地方局が会社として生き残れるかどうかの問題をも含んでいます。現実的にはテレビは携帯電話に食われています。若い世代は月1万円から2万円程度の出費を携帯電話にかけています。しかしテレビは無料ですが、なぜ支出の多い携帯に流れているかを考えました。単純に見ると、携帯電話の方が面白味があるのでしょうね。相互コミュニケーションでテレビでは与えられない情報が得られ魅力的なのでしょう。石光委員もおっしゃっていましたが、良い番組、良いコンテンツを作るしかないのでしょう。最近のTBSドラマの「半沢直樹」のように面白いものを作ればテレビもより視聴してもらえると思います。逆にマイナス面は、テレビ業界全体に驕りが感じられます。特にキャスターはかなり自由に発言しています。視聴者の立場からみると、例えば政府を批判する時には「我々庶民は!」的な言い回しをしますが、彼らの年収から言えば庶民ではない所得があり、違和感や嫌悪感を受けます。そんなことから一般の視聴者は、彼らの表現やトークには矛盾を感じていると思います。テレビの黎明期は、そうであったのでしょうか。我々庶民とかけ離れ奢っていることや欺瞞、偽善を出し過ぎていて視聴者に嫌悪を感じさせていることから、携帯とか他メディアに流れているのではないでしょうか。だから、原点に返り視聴者に魅力を感じさせるより、嫌悪を感じさせない謙虚な姿勢に立ち戻ることが必要だと思います。
・学生にテレビ視聴のアンケートをとると、携帯に流れているからテレビを見ていないと言うような一面的な事ではなく、もっと「なぜ」テレビ離れが起こっているか詳しく見ることが必要ですね。
・私は、少し前にアナログからデジタルに変わり、最近はスマートテレビとかハイビジョンとか、時代の流れに付いて行くだけで必死です。しかし、子供たちのテレビに対しての興味は強いものがあります。だから、地上波が押されているのではなく多チャンネル化で興味の散乱が感じられます。その上で、今まで通りの地上波に大きな興味を子供達はもっていると思います。今回の資料を拝見して、プライバシーを損なうことになるのではないかと言う恐ろしさを感じました。例えば、スマホでの位置情報をとってみても各家庭のテレビからそんな個人の情報を多くの人が知りえることには不安を感じます。今までの地上波テレビは言葉や映像の規制等があったと思いますが、インターネットと融合することでフィルターもなく、テレビとして放送されることは困ります。
・私もこの議題は経営方針に関わる議題であると思いました。経営陣はおそらく何らかのプランがおありだと思うし、社員の皆様が考えるテーマでもあると感じました。資料を読み共感したのは「ネットは大まかに言って信頼性の低い世界である。テレビ、ラジオ局が提供する物は信頼が置ける番組であり、今後も質の高い番組のサプライヤーとして地上局が存在し続ける事は間違いない」というくだりが一番共感しました。キー局と系列局は求められる役割が違います。系列局の場合は、地域に根ざして地域に信頼される番組、報道が重要です。いろんな組織、企業、人物が様々な情報を発信する時代なのでテレビ局が伝える情報の質の高さが求められます。このような動きの速い時代に対応できる人材育成が大切でありその環境整備が必要です。
・信頼性が一番大きなキーワードです。ネット情報は新鮮な情報が流れてきますが、充分に信頼のおける情報は少ないと思います。しかし、テレビ番組として作り上げた物は、少なくとも局が責任を持ち信頼性は高いです。この愛媛県には4社民放局はあります。数社の中でどこが生き残るのでしょうか。ある面で差別化を図り、放送局でなければ作れないものを作り出すことや、広告収入や視聴率ばかりに囚われず媚を売った番組を作らないことです。そして最近感じるは、タレントによるテレビ局の私物化です。ああいうことで番組作りが進んでいるのは如何なものかと感じます。日本に根付いた、日本の文化を基本に置いて番組作りを進めていけば、「テレビでなければ」と言うような信頼感に繋がると思います。私が子供の頃は、テレビの前に家族が揃い見ていました。そんな時代が懐かしいし、テレビを通して家族の絆や会話がありました。昔の平和な時代を再度考え直して番組作りに向き合っていただけたらと思います。
・最近の映画で「エリジウム」を見ました。その映画の中で、地上は汚れてしまい一部の富裕層は地球の周りを周回する大きな居住物に住んでいるシーンがありました。このスマートテレビとかスーパーハイビジョンは富裕層が見ていて、地上の人達は昔のアナログやラジオで生活しているのかな、などと想像しながら楽しみました。後で、監督のコメントを読んだところ、あの話は未来の話ではなく現代の話だと彼がコメントしていました。やはり今は、富裕層と差別化された層が出来上がりつつあり、上層社会で生活するのはほんの一部の人達の感じです。資料に目を通したところ、コンテンツを選択する上で一番優れているのは「スパイダー」であるとコメントがありました。しかし、スパイダーは普及していませんし、価格も高価です。家庭用はありえません。これの基本的な考え方は、全ての放送を全部録画して、どこでもどの番組も見ることができるようになる理想の機械ですが、一般の人には高嶺の花で購入は不可能です。インターネットが始まった頃は世界中で情報が得られ、平等に情報を持ち、差別の無い夢を見たのが20年ぐらい前でした。でも、現実はそうではないです。しかし、テレビは技術的な面で引っ張られてしまってコンテンツは視聴率でランク付けされる時代になっています。大学で言えば偏差値と就職率です。これが絶対的なものとなっています。恐らくこれと同様視聴率も絶対的な物で変えられないのでしょう。そんな中視聴率について書かれている松本清張の「渦」と言う作品を私の中でクローズアップしました。しかし、視聴率については詳しくは書かれていませんでした。「渦」と言うタイトルは、視聴率調査世帯を決める時に渦巻き状にランダムに選ぶことからタイトルがついています。この本から、松本清張でさえ良く判らなかった問題だから一般人が視聴率を推し量るのは難しいと感じました。しかし、作者は何か秘密を掴みかけたが書けなかったのだなと感じました。絶対基準になっている視聴率は生き残りを考える時不可欠な要素です。だから視聴率についてもう少し知りたく思いました。特に技術的には日進月歩目覚ましいなかで新技術は生まれますが、今出てくるものは、先程の映画「エリジウム」の中に出るスーパー富裕層対象のものでしかないように思います。
・墨岡委員長のお話からは、これからのテレビは4Kのようになっていくと思うが、視聴者にとってはそのような物は必要ないというお話しですね。はい。いらないし、余分な出費ですね。例えば、高視聴率であった「半沢直樹」をアナログテレビで見ても、スーパーハイビジョンで見ても、4K・8Kで見ても、ドラマとしての評価は変わるのでしょうか。本が良ければ良い作品が出来上がり、さらに映像でリアリティーが高まると言うことでより良いものとなります。匂いが判ったり、味も判ったら、もっといいですね。3次元は、3Dが出ましたが余り普及していません。あれは健康被害が発生しています。
・しかし、世界遺産の映像は4K・8Kで見ると素晴らしいですね。しかし、一般家庭用でそこまで必要かどうかは疑問ですまた、先程から今回の課題は経営者の問題だと言うご発言を受けまして発言させていただきます。テレビ画面にネットの情報がどんどん出てくるのには疑問を感じるという委員のご意見は貴重だと思いました。テレビとインターネットの違いは情報の信頼性です。インターネットには「炎上」がありますがテレビはありません。そこの違いはあります。視聴者は選択肢が増えるのは確かですが、地上波は選ばれれば良いのです。そこにつきます。第一次情報として情報を伝えるのはテレビは圧倒的に強いです。インターネットはひと手間が必要ですが、テレビ、ラジオが国民に情報を伝えるには一番です。そこに大きな責任感を持って信頼性のあるものを伝え続けることが必要ですし、選んでいただけるように努力すべきです。それが高画質であるかどうかより中身が大切です。
・信頼性のお話ですが、「イプシロン」の打ち上げの時の様子をネットでもテレビでも見ようと思い、いろいろチャンネルを探りました。ユーチューブはほとんど見ることができませんでした。多分アクセスの集中でしょう。しかし、テレビはNHKの中継で綺麗に見ることができました。結果ネットは意外に役に立たないと思いました。「2ちゃんねる」にもユーチューブは全然役に立っていなかったと、沢山の書込みがありました。以前の選挙報道の時にも言いましたが、ネットで集めた情報をテレビで流してよいものか、何となく違和感が残りました。あのような、ネット情報とテレビ番組の組み合わせ放送は、局側が混乱を招いてしまうような気がします。
・今、民放連はネットと融合した情報が得られる新しいテレビが出てくるのを反対しています。なぜかと言うと、同じ画面上に情報が露出した場合、これは放送局の情報だと勘違いされます。だから、そのようなテレビのCMは出さないと規制しています。さらに、都合のよいものだけを放送しようと思えばできるので、先程の選挙情報の抽出は意図的なもので余り芳しくないと思います。ネット情報全部を出すことは非常に危険です。放送禁止用語に始まり出せない表現もあります。そんなことひとつ取っても、放送の責任も問われますし、インターネットがテレビに乗っかるのは難しい問題です。
・我々は放送法に則り信頼性のある情報、番組等を出しています。ニュース報道であればきちんと裏どりして放送しています。しかし、ネットは信頼性に欠ける多種多様な意見があります。それらが混在するということが視聴者にとってどうなのでしょう。我々放送事業者としても大きな問題です。ネットを利用することが信頼性を欠くと言う話の流れですが、スマートテレビは飛んでいく先は放送局が管理します。なので、テレビを視聴してもらうツールにするという利用はできます。
・では、ローカル局は選ばれるために何をすべきなのでしょうか。ローカル局とキ―局は全く違います。もっとローカルに徹底したほうがよいと思います。そこに生き残っていくひとつの方向性があるのではないでしょうか。キー局とローカル局の役割は違います。ローカル放送は県域放送で電波の範囲が決められています。そんな中で何をすべきかと言うと、地域文化を継承し発展させていくことに役立つ番組作り、コンテンツ力の強化をすることです。原点回帰です。また、それらをどのようにビジネス展開していくかという問題も一方ではあります。しかし、原点は地域文化の発展に役立つ番組作りです。
・1960年代、映画【ALWAYS3丁目の夕日】の時代の頃から、1990年までテレビは【黄金時代】(小林/2010)と呼ばれていたらしい。思えば、私も私の周囲も、子どもの頃、よくテレビを見ていた。紅白歌合戦も、1980年前半までは最高視聴率が80%を超える「お化け番組」と称された。その後,横ばいから右肩下がり、PC、インターネット台頭で、テレビ、ラジオ、新聞.雑誌離れが始まった。近年、その危機が叫ばれているが、私は、テレビは、ちゃんと生き残ると思っている(ラジオも特別なニーズがあるので大丈夫だと思う)。テレビの普及率は,ほぼ100%、ニュースの速報力はもとより、エンターテイメント、広告媒体としても確固たるポジショニングあり。テレビが登場してから50年以上も、家族のように人の記憶と繫がってきたテレビが、そう簡単に、私たちの生活から消滅するものではない。近年、推進されている地上波テレビの複次利用についてはeatから送っていただいた資料のように進められているようだが、IT音痴の私には,その可能性や弊害を語る知見も勇気もないので、墨岡先生にお任せして、私は、地上波テレビの生き残り術をオリジナリティーの観点で考えてみようと思う。番組の編成を観ると、同じ時間帯に、同じタイプの番組で、横並びの印象が強い。夕方5時から7時まではどこも【キー局とローカル局のリレー方式のニュースと生活情報】。アナウンサーとコメンテーターの顔が違うくらいで、どこも作りは似ているドラマも同様に思う。連続ドラマは1時間枠、バラエティやスペシャルは2時間枠、特にサスペンスやワイド劇場系は、2時間枠でチャンネルは違っていても、原作者がかぶっていて、展開は同じ。【横溝正史】【夏樹静子】【西村京太郎】シリーズなどは、登場する探偵や刑事役の俳優を変えただけで、台本に新鮮さはない。(余談だがBS各局は、なぜあんなに韓流ドラマばかり流すのか。BS朝日は比較的日本のドラマが多いけれど)私は、時々夢中になる「掘り出し物」があるので、ドラマは結構観ている。テレビは、オリジナリティのある台本が書ける無名の小劇団の作家や新人にチャンスを与え、発掘する力がある。【家政婦のミタ】【あまちゃん】【半沢直樹】などのように面白いドラマには視聴者もちゃんとついてくる。気になる視聴率だが、ドラマをDVDで録画してみる人の数字は、どのように反映されているのだろうか。視聴率の算出は時代にマッチした方法で実施されているのだろうか。時代にそぐわない算出方法なら、視聴率の数字は、ほとんど意味を持たない。 私がほとんど見なくなったジャンルがバラエティ。申し訳ないが、品のない生活のアカのような話題、どこの局にも登場するひな壇スタイルのトーク(特にひな壇上の芸人やモデル枠の顔ぶれがどの局も似ている)、人をだまして苛める(私にはそう見える)仕掛け、ランキング方式で下位の人を嘲笑の的にするトーク、タレントや芸人、歌手が、演技も芸も唄もなしで、ゲームやクイズに興じる。これらに辟易して,私はバラエティを観なくなった。45分近く、時には2倍に水増しして放送するバラエティが、どこの局にもある。まとめとして、・ドラマは、特に2時間、3時間など、長時間のものはだらだらしていて、観る方も疲れるし、注意力も集中力も、湧かない。短い15分ドラマ、30分バラエティなど、短い番組の方が、今のニーズに合ってきたように思う。・都市と地方では視聴者の生活習慣と視聴時間帯が異なる。キー局は都市(特に東京)の視聴者の生活習慣と視聴時間帯をベースに考えているようなので、各局のローカル局が地元をしっかりリサーチして、その地元に合ったオリジナリティのある番組編成とオリジナルカラーを出す番組の質が必要だと思う。・視聴率がとれると安易に続編を作り(続編を期待する番組も中にはあるが)、作りすぎて質を劣化させる連続ドラマを増やさない。・評判になるドラマがあるとすぐにパロディにして、薄いお笑いに変えようとするバラエティは、テレビの価値を下げる。テレビを作る人間がお互いの番組の足を引っ張りあうのではなく、良い競争をしてほしい。番組を作る側が、消耗番組と消耗タレントを繰り返し作るルーティーンワークから脱却することが、「やっぱり、テレビだね。テレビがいいね」をもう一度増やすことに繋がるのではないかと思う。
・まず、「生き残り策」ですが、我々番審のメンバーが考える事ではなく経営者側の判断なので言うこともおこがましいですし、何とも言えないところです。
ただ今月号の文藝春秋に「フジテレビはなぜダメになったのか」という表題で日枝久会長のインタビューを載せていましたが、そこには本業のテレビ事業のみでは生き残っていけない。メディアコングロマリットへの変貌が必要で、本業以外の強みを持つことが必要であると書いていました。正にこのように将来に向けた経営サイドの多角化に向けた考え方の再構築が肝要なのでしょう。
また、次世代テレビ時代については視聴者としてより利便性の良いツールを求めていくのは自然なことでしょう。若者がテレビ離れをしているのではなく、そこにはVODなど数多くのコンテンツが存在するようになり、それの選択肢が増えたのであってデータ上のHUTの低下という数字での判断のみでは本当の視聴率というものが読めないのではないでしょうか?前回頂いた資料のなかで「それでも放送は社会に役立つ」ということをアピールする事が必要であると書かれていた通り、もはや視聴率の持つ意味もなくなってきた時代になったのではないでしょうか。
・地上波テレビの衰退とスマートフォンに代表されるニューメディアの進化は大きな潮流となっていて、この流れを食い止めるのは難しい。テレビはお笑い、クイズ、サプリメントの広告が溢れてテレビばなれに拍車をかけている。NHKが携帯端末のコンテンツに参入したのはこのためである。メディアからの情報を受け取るのはすでに個人単位となっていて、コンテンツの良否がその勝敗のキメ手となるだろう。私的なことを言うなら愛媛CATVから俳句の句会番組と川柳の句会番組を放送しているが、優れたコンテンツとしてインターネットで過去に放送したものもすべて視聴できるようになっている。愛媛は俳句王国であるとともに川柳王国でもある。それだけに愛媛発の番組として存在感を高めつつある。この番組にCMをつけているがCMもこうしたコンテンツにシェアを侵食されることになるやも知れぬ。ちなみに、 俳句 川柳の番組は下記滑稽俳句協会http://www.kokkeihaikukyoukai.net/俳句美術館 http://pc-fit.ddo.jp/HAIKUWORLD/index.html愛媛CATV http://www.e-catv.ne.jp/のホームページのトップページからご覧いただけます。テレビはインターネットで見る時代になりつつある。新しい時代に生き残るには 優良コンテンツをつくることができるかどうかにかかっている。また、ジャーナリズムとしての存在感は、ネットの情報の信頼性や多様性に敗北しつつある。視聴者は端末を自在に操作して信頼できる情報を選択しているのである。テレビ新聞ともに新しいメディアに対抗するには新しいメディアとの協調以外にないのではないか。