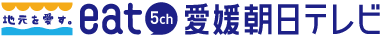第207回放送番組審議会議事録
開催日時:平成27年10月26日(月)15時00分
課題番組:テレメンタリー2015「私たち、長浜高校水族館部 ~小さな町のおさかな女子 大海原へ~」
2015年 7月15日(水)[午前] 3時55分~[午前] 4時25分(30分)放送
・まず、冒頭のナレーションで、地域の高齢化率について触れていましたが、のちに出て来る若者との対比という意味で非常に良い情報だと思いました。2点目には、長浜高校が人工繁殖の方法を開発していたことをまったく知らなかったので、このことには純粋に驚ろかされました。3点目、研究というのは着想力と積み重ねが必要なのであって、野口英世さんのような特殊な人がやり遂げるものだけでもないことがよく分かりました。科学の分野で研究をしてみたいと考える若者がこの番組をみたら、結構そういう印象を持つのではないかと思います。夢を持てるドキュメンタリーだと感じました。4点目、研究だけではなくて、英語でプレゼンをしなくてはいけないという時の苦悩や苦闘もしっかりと描かれていました。ひとつのことから、ほかのことも学べるようになるということがメッセージとして伝わって来て、公教育のこれからの方向性は、実はこういうところにあるのではないかと感じさせてもらうことが出来ました。そして5点目、女子生徒が、「お互い、言い合うぐらいが丁度いい。」と話していましたけれど、昨今のいわる、"KY文化と言われる若者"、それから"若年無就業者の問題"にも通じる内容だったのではないかと思います。6点目、番組の後半で長浜高校に企業が来ましたけれども、一視聴者として、いわゆる、"知の搾取"というのか、せっかく若者が磨いてきた知を搾取していくのではないだろうかと気になりました。そのあたりをもう少し丁寧に描いていたら、より良かったと思っています。一方で、あのように企業がワッとやってくるというところは、ドキュメンタリーには欠かせないリアリティも感じることも出来ました。最後に、ドキュメンタリーはやはり知らないことを教えてくれるとみていて思いました。制作費など、いろいろな制約があるのでしょうけれども、良質な情報、知識というのを私たちに、これからも与えていただきたいなというふうに率直に感じました。
・3点、申し上げたいと思います。1点目は、まずは素材となる高校生二人が生き生きとしていて、本当にこの二人のやりとり、仕草をみていると、世の中に期待が持てるようなものを感じました。2点目は、こういう公教育に関わってくるような良い番組はたくさんの人にみてほしいのですが、この番組の放送時間は、たくさんの人がみる時間ではないと思います。放送時間のことをもう少し考えていただきたいと思いました。最後に、番組では"チーム・ニモ"に関する説明がなかったので、その点が気になりました。
・自主制作番組としては全国で放映されても十分堪えられる、見応えのある番組だったのではないかと、まず評価をしておきたいと思いますが、愛媛の場合、午前3時55分という時間帯での放送はもったいなかったと思います。長浜高校に水族館があるのは知っていたのですが、その裏で、高校生が真剣に、研究に没頭しているということは、全く知りませんでした。地元の地域の魅力を掘り起こす、大きな番組であったと思います。また、二人の若い柔軟な頭には、すごい発想力があります。クマノミ、イソギンチャクから発想を転換して、クラゲに刺されない予防クリームとは、我々の堅い頭では、なかなか考えつきません。これが本当に商品化されたら、素晴らしいと思うとともに、これからも、是非、この二人を追いかけて取材をして、3年、5年後、どのような研究者になっているか、もう一度、番組をつくってもおもしろいのではないかと思いました。「発見するのが、すごいのではなく、発見してさらにそれを私たちの日常生活に活かせるように…。」という彼女の言葉を私は聞いた時には、まさに科学者誕生の瞬間ではないかと思い、本当に感激し、素晴らしい番組をみせていただいたと感じました。ナレーターの小倉さんもとても良く、番組をゆっくりとみることができました。非常にしっくりとしている声質だと思いました。愛媛県ではどういう学生が育っているか、どのような魅力があるかなどを掘り起こして、このような番組をつくっていただいたら、ありがたいと思います。
・私も本当に興味深くみせていただきました。みなさんが言われたように、放送時間帯が非常に残念だったと思います。長浜高校の水族館部を知らなかったのですけれども、すごいなと感じたのと同時に、ノーベル賞の大村さんのことが連想されました。まず、ひとつは、この高校生が、必ずしも有名校や進学校の子ではないということ。それから、発見というものは、人の役に立つとものでなくては、ダメだということに気付いたところなどは微生物から人を助ける薬をつくった大村さんと非常に共通性があって、番組をみている間ずっと、本当に、ミニ大村さんみたいな感じがしていました。非常に感動的な番組だったと思います。この番組は7月15日にオンエアされていますから、まさに、そのノーベル賞の前のオンエアなので、本当に先見の明がある番組のような感じがしました。最後に、ナレーターの小倉久寛さんの独特の語り口は、分かりやすくて本当に良かった。それも、番組を盛り上げていたと思います。
・長浜高校水族館部の女子高生二人の研究が日本学生科学賞で内閣総理大臣賞を受賞し、さらに世界大会でも入賞したエピソードは、小さな町の高校生の話だけれど、全国の人に伝えたい話ですから、今回の番組が全国ネットで展開されるということは、当然であり、喜ばしいことだと思います。番組では、岡山の養殖場で働く先輩やほかのOBのかたがたを訪ねたインタビューや水族館部の高校生たちがあいさつをして部活動を始めるところ、魚に愛情をそそぐ姿など、水族館部の実態をきめ細かに盛り込まれていましたし、今回の世界大会後の動きもフォローして、クラゲに刺されないクリームについて、大手企業の研究員が訪問するなど、時系列でキッチリとつくられていると思いました。また、田舎のまちの水族館部の紹介というだけでなく、女子高生二人の友情物語、それと成長物語になっていることを感じました。国際大会の英語での発表に備えた練習では、お互いに檄を飛ばし合いながら意識を高め合い、渡米してからも発表の訓練をするなど、懸命に向き合う高校生の清々しい姿を感じました。大会後、いろいろなことが変わったとか、発見を日常生活に活かせるようになりたいという成長の跡がうかがえるのも、ひとつの部活動のストーリーと、高校生の成長ストーリー、友情ストーリー、そういうのも軸にあり、あっという間の30分だったと思います。これだけの番組が[午前]3時55分の放送というのは残念だと思います。
・私も、一番気になったのは、放送時間帯です。是非、教材の意味も含めて、先生方もみるような時間帯に再放送をしていただけたら、とても良いのではないかと思いました。長浜高校水族館部は、2011年に、先輩が3位で環境大臣賞を受賞していたということですから、研究が代々引き継がれているという部分をもう少し紹介すると、もっと学校のアピールが出来たという面は感じられました。30分番組の中で、二人の女子高生が大きく成長する姿をみせていて、一旦は完結されていますが、未来を想像できるような内容で、とても素敵だなと思いました。肱川(ひじかわ)あらしのきれいな映像を長浜の紹介で全国に放送したことも、とても良かったと思います。
・順序立てて、進行していく番組のつくりが素晴らしくて、自然にのめり込まれて、みせられたというそんな雰囲気がいたしました。長浜高校はこれまで脚光を浴びるような学校ではなかったのですが、そこに今回、スポットが当たったことは限りない自信に繋がったと思います。既に、自分の方向性を見つけ出し、その分野で頑張っている高校、若い子供たちにスポットが当てていただくことで、本人が自信を付け、頑張ってもらえることは、大きく言えば、日本の発展に繋がると思います。30分の中で、彼女たちの成長もよく分かりましたし、これからは、何か温かい、大人として出来る、テレビ局として出来るそういう手を差し伸べてあげてほしいと思いました。
・残念ながら、放送時間帯の問題は、いろいろな制約があったと思います。内容に関しては、私も素晴らしいと思います。瀬戸内海にもけっこうクラゲがいて、刺される人もたくさんいるので、非常にテーマとしては良かったと思います。水族館部の高校生たち、先輩がたなどをみていますと、やはり魚に対する愛情が重要だと思いました。ともすれば、実験というと、切り刻んだり、薬物を投与してとかになりがちなのですけれど、そうではなく行動を見守るというのは、古くはノーベル賞を受賞したコンラッド・ローレンツがいます。この先生は、『ニルスの冒険』、昔、ありましたアニメの『ニルスのふしぎな旅』ですが、これを読んで、動物行動学の世界に入ったと言われています。そのような感じで、逆に、水族館のなかのいろいろな物語をアニメでつくれる可能性など、いろいろな素材を提起しているような気がしました。
※「放送番組の種別ごとの放送時間」の報告
2015年4月~2015年9月の各月第3週に放送した番組の「種別ごとの放送時間」について報告があった。