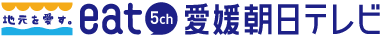第156回 放送番組審議会議事録
開催日時:平成22年9月27日(月)午後3時
課題番組:「放送番組全般について(特に、選挙、政局報道について)」
1.開催日時:平成22年9月27日(月)午後3時
2.課題番組:「放送番組全般について(特に、選挙、政局報道について)」
3.議事の概要:
・BPOの報告を読むと、番組全般についての意見として「テレビは、鳩山総理を叩き、民主党の支持率下落を嘲笑するような報道をしていたのに、菅総理に替わった途端、今度は新総理や新閣僚らを持ち上げるようなことばかり言っている。内閣交代によるお祭り騒ぎは、テレビ独特の節操の無さの産物だ。軽薄で無責任そのものの報道を改めようという声は内部から起こらないのだろうか」とか「選挙間近に政治報道を扱う場合、キャスター、コメンテーターに意見や感想を主張させることは問題がある」、あるいは「政治に関しての街角インタビューについてだが、これほど危ない報道手法はないのではないか。意図的な操作が容易にできる。少数意見でも多数意見のように見せることができる。マスコミが伝える世論の実態に乖離を覚える」といった文章が出ています。政局が動いた時に、誰を叩けば国民は面白がるのか、国民をのせる、面白おかしくというと語弊があるかもしれませんが、そういった感じの報道が多々あったのではないかと思います。政治を劇場化して表現する、これもマスコミのあり方という点で問題ではないかと思います。また、最近は選挙ではなく、検察庁や尖閣諸島の問題が取り上げられています。たとえば、村木元局長が無罪となった汚職事件。権力があのような犯罪を犯すということ、検察庁の犯罪、これこそ恐ろしい。それをマスコミが監視すること、これぞマスコミのあり方として期待したい。尖閣諸島の問題についても、船長の不起訴と釈放は政治判断なのか、検察の判断なのか、マスコミで色々と言われていますが、そういった事を、情報として伝えるのはやはり報道番組であり、我々一国民、一市民は、マスコミの報道にどうしても左右されやすいという怖さもはらんでいます。
・これはなかなか難しい問題です。民主党代表選が9月14日にあり、その様子を私はテレビで見ていました。主にNHKを見ていました。よく最近言われていることとして、大学もそうですが、「可視化」ということを言われます。「見えるように」と。可視化といっても、はっきり分かるようにしてしまうと、かえって公平公正とは違った一つの見方が強調されてしまい、なかなか難しいと思います。この選挙報道で特にそうだと思ったものは、テレビ朝日の場合、投票中にはっきりとどこの陣営が優勢なのか字幕として出ていました。もちろんNHKは出ていませんでした。この中では、投票の内訳を見ると、サポーター票は、随分、菅さんの方が多かったです。皆さん、テレビ中継を見ながら2チャンネルでしゃべったり、ツイッターなどネットで色々としゃべっています。テレビ中継は残らなくても、ネットには文字が残っていますので、それを見てみますと、なかなか皆、厳しい意見を持っているなと思いました。サポーター票については、本当のところ、事前には数字が分かっていなかったのか、微妙な問題だと思います。民主党の選挙管理委員会が、サポーター票について実は知っていて、それをどうしたのか、あるいは知らなかったのか?ネットではかなり極端な意見が出ています。そういう中で、マスコミでの取り扱い方は難しいと思いますが、根本に返ってみると、これは権力闘争です。キレイごとをいくら言っても権力闘争なので、権力闘争となると、中国や北朝鮮を見るとはっきりしているように、相手をとことん叩きのめします。ですが他の国では、いわゆる民主主義、それからマスコミ、という枠があり、その「とことん」ということができなくなっています。もし、この枠の中で権力側が何か思惑を持ち、世論を操作することができるかもしれない。民主主義の枠の中で、マスコミも操作することができるかもしれない。そういう事になってしまうと、非常に危険だというのが、最初に委員長が言われたコメントの中にも感じられます。そういうことを感じながら、テレビをずっと見ていました。劇場型に似ているというのは、難しい。小泉政権の時、A層、B層という言葉を作り出しました。A層、B層とは何かというと、知的水準でした。知的水準によって、政治に関心がある、ない、を横軸に持っていき、縦に知的水準を持っていき、知的水準が低く、政治にはそれほど関心がない層をどのようにして引っ張り込むのか、それをあるコンサルタント会社に頼んだということが、国会で暴露されたと思います。その事件をふと思い出しました。あの時はコンサルタント会社が、よくアメリカが取っている手法で、いわゆる日本でいうとチラシ、アメリカでいうとフライヤーを入れて、B層の方を動かす。そのようにマスコミの立場というのは使い方によって難しいという気がしていました。厚生労働省の話しなど、色々な話がありあすが、どれも最近ネットで出ています。マスコミだけではない、そういう勢力も、ツイッターを使ってどんどん書いている人達もいますし、特にはマスコミの中の記者クラブに入っていないような人たちがツイッターの情報を元に色々なことを書いているので、それを読んでいる一般国民とは言えませんが、結構ネットを使っている人達は、そういった情報を集めているので、そのあたりも今までとは違った動きが出てくるのかなと思いました。
・サポーター、党員票は世論に影響されるという数字が表れていたと思います。議員の投票数はほとんど逼迫をしていたので。今回は小沢氏、菅氏でしたが、小沢氏のダーティーなイメージが本当にマスコミによってしっかりと作られていったという感じがします。それよりも面白かったのは、菅氏が決まった投票後、決定した後、すぐにマスコミはそれぞれの議員に、「挙党一致ノーサイド」といった言葉が流行ったと思いますが、本当にそうだろうか、ということでどうにか議員を煽り、本音を聞き出そうというところが非常に見えており、先ほどまで選挙があったのに、すぐにそのような民主党の代表選挙だけ、民主党を二分させるようなコメントを引き出していくというところを、選挙の中では報道を見ながら感じました。かなりマスコミの影響力があるのだろうなと思います。
・視聴者がどうすれば面白がるのか、そういう手法にはしりすぎているということを感じています。例えば参議院選、相当前のような感じがしますが、タレント、スポーツマンの候補者の扱い方、取り上げる様子を見ていると、ここの人たちがどのように政策を考えているのか、ではなく、その人たちの過去のことを出してきて・・・といったことをしており、確かに関心がない、野次馬的な部分は誰しも持っています。それはそれで良いのですが、ただそれだけがすごく作る側の行動に表れ過ぎている。もうそろそろ限界ではないのかと感じました。特に朝のスーパーモーニングは見る機会が結構あり、また古館氏の報道ステーションもですが。お昼は全然分かりませんが朝の番組で言いますと、そこに政治ジャーナリストや政治評論家など出てきますが、そのチョイスが少し偏っている。また裏情報好き過ぎで王道を忘れている。実際にこの時間帯にテレビを見る私や主婦の人たちは、「政策の違いは何か」を分かり易く、パネルや分かり易い言葉で言ってくれているところはすごくありがたいのですが、政治の中に入り込んでいるジャーナリストが出てきて、裏の幹部の意見としてはこのようなことが流れていまして・・・といった身内話になってくるのを見ると、段々うんざりしてきます。メインになる情報をしっかりと流し、「この違いをしっかり見ていくことが大切です」というような事までなら、ある意味分かりますが、裏情報みたいなものをどんどんどんどん優先させ、例えば小沢氏なら小沢氏の映像を出す時に、ものすごく嫌な顔をしているところの小沢氏のアップを何回も何回も流すなど。菅氏の居眠りしているところを何回も何回も映すなど、そういった作為が見られる時は、やはりこれは政治がショー化している、番組のドラマのように、作りたがっているなということが感じられ、それはそろそろ成熟した報道を考えていってほしいと思います。特にスーパーモーニングは報道ステーションとは違った層が見ている番組なので、もう少しマーケティングをリサーチしていただき、やっていただけたら良いと思いました。以前は選挙違反のことが大きいニュースでしたが、今や選挙違反よりも内部抗争がメインになっています。以前にも内部の色々なことはあったと思いますが、それをうまく解決し表に出さないというのも政治ではないのかなという気がします。政治をなさる人に対して尊敬できなくなってきます。ただ期待しているのは、今度、知事選、市長選があります。これはすごく関心があり、地域が力をきちんと分権でやっていけるのかどうかが試されている時だと思うので、良い選挙に関わる情報番組が流れることを期待しています。
・マスコミが自信をなくしている、そういう状況だと思います。非常に難しいと言いますか・・・国民もおかしいなと思いながら、それを声に出せない状況が続いている気がします。例えば愛媛新聞が「アクリート」という無償で配布する雑誌を出しています。それに毎回川柳を出しています。「エコカーに収めた税が使われる」と出しました。私はエコカーに替えるわけではないですが、税金を納めています。そういった庶民感覚が素通りしてしまって、経済不況にはエコカー減税が必要だといったことがまかり通っているということに甚だ疑問を持っています。そういうことを言うマスコミはありません。「マスコミは具合わるけりゃ知らんぷり」民主党の代表選挙の直前にはNHKは小沢氏が勝つと決めたような持ち上げ方をし、自信たっぷりな顔を出し、どのような政党にするのかというインタビューを堂々としていました。瞬間に思ったのですが、もし小沢氏が負けたらどうなるのか?負けましたが、それは一切知らんぷりです。それがマスコミであり、昔50年も前に「マスコミは新聞読む方、新聞は嫌いだ、新聞は世論に思われるものだ」と言いました。そのような伝統は続いており、マスコミは世論に阿るということ。マスコミはどのようにするべきか。ジャーナリズムはどうあるべきか。基本的なスタンディングポイントが見失われているという気がします。それがないと、例えば尖閣諸島の問題でも専門家を雇いしゃべらせ、知らないので・・・。専門家は強硬に行くべきだ、弱腰をアメリカだって笑っているじゃないかと、それがどんどん論調としてやっていった時にはどのような結果を生むのか、非常に怖いなと思って見ています。強硬姿勢だけが良いわけではありません。それが強硬姿勢を皆が争って、競って主張するようになった時には、その事の方向が違ってくるのではないか。どのような意見を取り上げるのか、基本的な立場、なぜジャーナリズムが必要なのか、あるのか、という事を考えないといけません。それが失われているという気がします。安保の頃、昭和60年代、沖縄返還がありましたが、その前後に私は沖縄タイムスに取材に行った事があります。編集長にインタビューしてきました。「一歩先の警鐘を鳴らすのはマスコミの役割だ、鳴らした警鐘が少数意見であっても、その警鐘が違っていても、今の世論に阿るのではなくて一歩、二歩、三歩先をよんで警鐘を鳴らすのはマスコミの役割なので、それがもし誤っていたら引っ込めれば良いですが、マスコミが世論に追随していったのでは立場を失ってしまうだろう」ということを言っていました。ジャーナリズムの在り方について基本的なところ、何をスタンディングポイントとするのかという事があやふやになっているという気がしてなりません。そこが一番、報道について言えば、物足りない、危機感を持っているところです。尖閣諸島を報道するのに何を基本としてどう考えているのかというと、誰も応えられないと思います。そこが実は問題です。品のない国がお金を持った時には、あのような威張り方をするのだ、と言う人もいるわけですが、正にその国際舞台の歴史的には浅い国が、今度、大手を振って威張りだした時に、日本のような国が被害を被ってしまうということです。非常に難しい問題で結論がでませんが、そんなことを感じています。
・本来の選挙、政局報道について、色々意見があると思いますが、特に今回の民主党の代表選挙の場合は正にマスコミの力が出ていました。国会議員の投票は半々、地方議員になると少し菅氏が有利、党員サポーターはかなりの差で菅氏が有利、何だかんだ言ってもマスコミの影響だと思います。良い悪いは別ですが、マスコミの影響が出ているなと思いました。世論に阿る、阿ない、という話しが出ていましたが、世論はどのように作られるのか?やはり一般の人はよく分からないのでテレビや新聞から得る情報が作るので、結局、一番、力、影響力を持っているのはマスコミ自身である、というのが偽らざる現実ではないかと思います。従ってマスコミの責任は重いと言わざるを得ないのですが、現実を見ると、民主主義の劣化ということを言いたいです。まず選挙に出る人がスポーツ選手、芸能人、要するに有名であるということがマスコミの力によって意図的かどうかは別として圧倒的に有利です。中身は別として結局マスコミにのって名前を売っている人が、例えば選挙に関して圧倒的に有利である。話題性もあり、本来の政策、中身がどうなのか、見識はどうなのか、と言うより先に有名である、人が知っているか知っていないか、ということで圧倒的に有利である。これもある意味ではマスコミの責任、マスコミの存在がそうしていると思います。選挙に関しても非常にマスコミの影響力が強く、責任が重い。どのように扱うのかによって本当に政治を構成する人がガラッと変わる。完全に影響力を持っている事を自覚してほしい。今更ながらですが、マスコミの方々は、経営者というより報道ですが、持っている力は自分達が意識している以上に影響力を与えているという気がします。ANN系列の報道、情報番組の中で、「報道ステーション」だけは違うなといつも感じでいます。報道なのでニュースとは違うのかなと。定義はよく分かりませんが・・・古館氏は非常に自分の考え方を全面に出し、ニュースを報道する時に表現していますが、これがいかがなものかと感じている人もかなりいると思います。例えばNHKのニュースは淡々と事実を視聴者に知らし、あとの判断は視聴者に任せるというような感じですが、古館氏は、特に報道ステーションの場合は、久米氏の時代からそうですが、「例えばこんなことがあっていいのか?」という枕詞をやっておいてから、そのニュースを流す。そうするとある意味では扇動的なやり方だと感じます。これが嫌な人は見なければよいと言われればそれまでですが・・・ある程度自分の立場で、主義主張を持っている人は判断しますが、大多数は無党派層の人なので、かなり影響力を受けると思います。これは良いか悪いかについては言いません。究極的なことは言えませんが、やり方としては非常に自分の考え方、自分の好みを押し付けるやり方だと感じます。
・私たち主婦がテレビを見て何を見てどう思うのか?という事は自分達の興味のあることを一番よく主張してくれる候補者について、「この人いい人だ、この人悪い人だ」と、そういった情報でしか判断できないと思います。昔と違い、今はテレビから得るものだけではなく、ネットからの情報が沢山転がっていています。出口調査一つにしても、小沢氏にしても、ネット上の小沢氏の票と菅氏の票は、小沢氏の方が優勢だったなど、ネット上とメディア上、テレビ上のことが全く違っていたということも耳にします。どの情報が本当の情報なのか、私たちにはきちんと伝わってこないということを一番感じました。選挙の時に電話がかかってきたことがありますが、テープの自動音声で、永江氏が選挙に出られた時に、「どちらの政党を支持されますか?番号でお答えください。」と言われ、「面倒臭いから適当でいいや」と適当に答える一般市民もいるので、本当に正しい調査結果が得られているのかどうか、不真面目な回答をした者が言うのはおかしいのですが、あまり信用できないのではと思うこともあります。そこからきて出口調査などを踏まえで、いざ開票になり「当確」を打った段階で、前の時も早く当確を出したところの局はアナウンサーが「申し訳ありません」と謝っているのを見ると、早ければよいというのではなく、正しく伝えてということを一番見ている視聴者としては感じます。テレビとネットで、取材する、調べる対象は、年代層も全く違ってくると思います。データの取り方が、データの質自体が違ってくると思いますので、取材する時にはまんべんなく公正に取材したものを載せていただけると信憑性が高くなり、私たちも信じ易いと思いました。最近見たもので、あるテレビ局が小沢氏と菅氏の街頭演説の側でアンケートを取っていました。「どちらに入れますか?」とフリップにシールを貼ってもらうものですが、スタッフの人が裏で貼り替えていたという場面を見ていた人もいるという話しを耳にしました。小沢氏に貼られたものを菅氏に貼り替えていたというのをネットで見ました。そのような情報は本当かどうか分かりませんが、私達は目にすると「何が正しいの?」ということになるので、スタッフも気をつけて誠実な行動を取っていただきたいと思います。流れてくるものを真に受けずに受け取る、こちらでよく咀嚼して考えるというこちらの姿勢も大事だと思いますが、知るすべがない、裏事情も分からない私たちからすると、公正な取材をお願いしたいと思います。ただ最近思うことは、記者会見で質問する記者の方を見ても、仕方のないことを聞いている。もう少し確信をついた事を追い詰めて聞けないのか、と思うことがあります。記者の養成も、年長者が伝承していくというわけではありませんが、足で稼ぐ、といったことをきちんとされたらよいと思いました。
・朝のスーパーモーニングとお昼のワイドスクランブルをたまに見ますが、やはりレギュラーのコメンテーターの方の言われることがその局のカラー、その局の考え方であると受け取れることが多い気がします。「これは以前の話しですが、隠された話しなんです」と裏話、裏事情などを2人でお話され、「あ~ありました、そうですよね」と内輪だけがよく分かっているような、見ている人たちは「有名な人たちは、皆が知らない情報も知っているのか」という感じで、「すごいな」というふうに感じている人。色々な憶測、解釈の仕方をしている主婦が多いと思います。男性の方は見られないと思いますが・・・NHKと民放との違いですが、NHKはアナウンサーが自分の個人的な意見を絶対に述べないということです。民放はその意見を述べることによって、その局のカラーが醸し出されるという部分はありますが、少しここまでで良いのでは、という部分をよく感じます。それはどの局に関してでもです。小沢氏、菅氏の顔の表情が違うのはよく分かりますが、どちらが好き嫌いではありませんが、小沢氏の難しい顔ばかりが出て、この人は笑わない人なのかと思うくらいです。違った顔も出してあげればよいのにと感じました。それによって票が減った、増えたということはないでしょうが、投票する権利、力のない人たちも次期代表が誰になるのか、ある意味において期待している、この経済状況がよくなるようにやってほしいという期待感があったり、色々感じて見ていると思います。映像を繰り返し流される時には、同じような映像を流してあげる、など今回は痛切に感じました。司会者が発言されている意見は、コメンテーターの方が発言されている意見にもっと被せて、すごく説得力があり、この番組全体を任されている人が言っているので、「そうなんだろう」と視聴者は取る場合があると思います。司会者の方もよく本番中に頭の中を整理しながら発言されると良いのではと思うところも時々感じさせられます。前回の参議院選でタレント、スポーツ選手が多かったという意見がありましたが、確かにそう思います。テレビに顔が出るようになったら次のステップは政治家かと思います。
・検察がストーリーを作るのと同じように、マスコミも面白いストーリーを作り、それにあうような映像を度々使い誘導していってしまう、非常に恐ろしい一面ではないかと思います。
・先ほど民主主義の劣化とお話をしましたが、一昔前と比べ、日本の中で劣化しているのは取材力だと思います。立花隆氏が昔、田中角栄の金脈を文藝春秋に出しましたが、大変な取材力だったと思います。そのような意味の、一線のマスコミの記者の取材力の回復をぜひ期待したいです。検察のでっち上げについては、大ニュースになっていますが、このきっかけは内部告発なのか、あるいは取材で突き詰めたのか?今は内部告発が多いです。色々な問題が表面化するのは。そこのところも一段落すれば、ぜひ報道してほしい。取材なのか、内部告発なのかをやり、そのような問題の解明をしてほしい。尖閣列島の問題も、基本的には日本の領土なので、やったことに異論を挟む余地はありませんが、外交なので、相手があることなので、たとえ相手がどんな理不尽なことをしてきても、落しどころがないと困ります。本当にドンパチやることはないでしょうが、その辺のこともこれこそマスコミの勤めだと思います。後ではっきりと、我々に報道、知らせてほしい。どういうことであったのか、今後のことになるためにも報道してほしい。要するに取材力をアップしてほしいです。
・同僚の検事が時限爆弾をしかけたというコメント自体はどこから出ているのか?不思議だという気がします。なかなかそこら辺が我々では分からない、ベールに包まれたところをどのようにしてマスコミ、ジャーナリズムの力で引っ張り出していくのかというところに醍醐味があるのかという気もします。
・前から記者クラブ制度の弊害について言われていますが、一向に改善されません。記者クラブというのがあり、そこへ色々情報が提供され、それを記事にするだけということが何十年も続いています。今、取材力が落ちるというのは当たり前な話しです。そこが一つ大きな問題です。