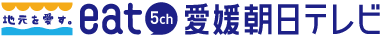第170回 放送番組審議会議事録
開催日時:平成24年2月27日(月)午後3時
課題番組:「にほん風景遺産」
1.開催日時:平成24年2月27日(月)午後3時
2.課題番組:「にほん風景遺産」
2011年12月28日(水)14時00分~14時55分(55分)
3.議事の概要:
・この番組は地上波での放送に先だってBSで放送されたということですが、チャンネルがあまりにも多すぎて私はBSを見るということがなく、BSで放送されたということを知りませんでした。この1時間番組は、祭り、大島石、水軍レース、造船、大山祇神社と非常にネタが沢山ありましたが、その割には、1時間という時間が、長くも短くも感じられませんでした。3島紹介には丁度良いくらいの時間の設定であり、あっという間に気持ちよく見ることができました。ナビゲーターである加藤氏の語り口もそうですが、ナレーションの下平アナウンサーの口調も非常にゆったりとして、番組全体として時がゆっくり流れている感があり、ゆったりとした気分で鑑賞できました。BGMも非常によく考えられていて、邪魔にならない音楽を選んでいたと思います。このような番組は批評し辛いのですが、見ていると時代が分かり、片岡鶴太郎さんの名前が少し出ましたが、「なるほどな」と納得できました。そういったものを取り込んで、非常に素晴らしい愛媛の紹介ができたのではないかと思います。
・テレビと言うと、バラエティやクイズ、お笑いが多い中で、年のせいかもしれませんが、ゆったりと、NHK的番組と言いますか、新日本紀行と言いますか、個人的には非常に良い番組を久しぶりに見させていただきました。落ち着いて見ることができました。最近はテレビを付けると騒々しい番組が多いのが当たり前になっていますが、この番組は良い感じでした。材料が多く、大島、伯方島、大三島の歴史を非常に感じさせるものがありました。せっかく良い材料を取り上げていますが、もう少し深くやってほしかった部分があります。一つは伯方島の造船の船大工のところです。日本のモノづくりの原点と言いますか、ヒントを与えてくれるような切り口で良かったです。愛媛県には造船、海運がありますが、そのルーツでもあります。また豊田自動車のルーツは船大工です。プラスティック船はやめた、木造船の方が面白かったというコメントのなかに、モノづくりの精神を非常に感じました。実はモノづくりの中で、図面なしで作っていくということは、見直されてきています。何でも図面があり、コンピューターで、その通りにやれば良いものができるかと言うと、そうではありません。日本の製造業、モノづくりは、そういった微妙なところに原点があります。製塩のところでは、今は流下式枝条架塩田ではなく、電気で作るようになったが、昔の天日式には非常に見直すべきものがあると言われていましたが、その通りです。その辺のことをもう少し掘り下げてもらったら良かったかなと思います。もう一つは大山祇神社の所で、加藤氏がお参りする時に、礼をされていたのですが、神式参拝の正式の作法にしたがって、二礼二拍手一礼をやっていませんでした。加藤氏ほどの人が知らないはずはないと思います。放送番組における宗教の取扱いについては、色々考え方があるのでしょうが、教会に行けば十字をきるべきだろうし、神社に参拝するときは、宗教色、イデオロギーということではなく、初歩のマナーとして、二礼二拍手一礼をしてほしかった。若い人がそれを見て、神社の時はこのようにするのだなということが身に付きます。それをもって宗教色がどうかということまでは言う必要はないと思います。単なるマナーとして、やってほしかった気がしました。また、ひとり相撲がありましたが、相撲は古い歴史があり、やはり神事でありスポーツではないということを感じました。二勝一敗で神様が勝つのですが、五穀豊穣を願うという背景があり、相撲は単なるスポーツではないということを再認識しました。それをもう少しアピールしても良かったと思います。全体としては大変良い番組で、このような番組が増えてほしいと思いました。
・私も、モノづくりの所は確かに同じように思いました。今はコンピューターがあれば、車でも何でも作れてしまう。コンピューターもコンピューターで作ってしまう。今のコンピューターを最初に作り、圧倒的な人気を得たバロウズというメーカーがあります。これはIBMとは違う作り方でコンピューターを作ったのですが、バロウズのOSを作った人は、絶対部屋にコンピューターを置いてはいけないというポリシーを持っていました。計算機も置いてはいけない。部屋にあるものはゼロックスのコピー機だけでした。あとは全部頭で考えて手でやる。またマイクロコンピューターを作ったアップル社のウォズ二アックも、驚くべきことに全部手で書いています。恐るべきことです。ロジックは面倒なので、普通は人間が全部書くということを致しません。それなのにロジックを全部書いたということは、自分の頭の一部を移植したのがコンピューター。そのような感覚で作っています。これがモノづくりの原点であり、番組内でも木材を自分の手で削っていましたが、自分の手、目などが一つの装置で、その熟練工から見出される一つのアート。そこの部分を、私も見ていて、もう少し視聴者に伝えてほしかったという気持ちがあります。
・風景には、人の営みが表れているということが伝わってきました。やはり風景に関わる人のインタビューをふんだんに盛り込んでいることが反映されたのかなと感じました。私はまだあまり愛媛の知識がないので、三つの島の事がよく理解できました。非常に参考になる番組だったと思います。加藤氏の人柄が番組の中に滲み出ていて、音楽の選択については、瀬戸内海の細波を思い出させるような静かなタッチで伝えようとしているのかなという印象を持ちました。ただ、静かな感じで通していたので年末に放送される番組としてはパンチに欠けるかなという感じがしました。しかし、番組のトーンとしてこういうのもありなのだろうなと思いました。また仕方のない事だと思いますが、関係者の方が、皆さん高齢、先輩であり、人生観を語れる人ということで、そういう層になることは仕方ないとは思いますが、後継者の繋ぎといった形での若い人があまり登場していないと思いました。年末の放映でしたが、映像全般に、夏から秋にかけての印象があり、風景は季節感の影響が出やすいので、もう少し早めの放映であっても良いと思いました。
・「にほん風景遺産」はシリーズものですか?見た感じBSっぽい番組だと思いました。時間がゆっくりしているのと、旅番組の色が少し入っている感じがしました。旅番組をビデオに溜めて週末見ることが好きなので、色々見ています。出演者が加藤氏ということで、若手の芸人ではなく、上品な感じで、時間がゆっくり流れ、教養番組風で良いと思いました。このような番組はBSや他の局でも沢山あると思います。似たような番組が沢山あるので、それぞれテーマがあり、特徴を出していると思います。例えば、路線バスの旅、路線だけをバスで繋いでいく、ローカル列車で一駅ずつ降りていく、路地裏をカメラを持って歩くなど、それぞれの番組が特徴を出して作っています。この番組を見て、ひとり相撲、船大工の話などが入っていて、文化や人にスポットを当てたことを特徴とする番組なのだろうと思ったのですが、似たような旅番組を3つ4つ見た後に、この番組を思い出そうと思っても、記憶がごちゃごちゃになる。番組内容それ自体は良いのですが、この番組をシリーズものの一つとして作ったのであれば、どこかに何かこのシリーズならではの特徴、色、パターンなど何か一つでも毎回踏襲するものがあった方が、記憶に定着させるという意味では得策だと思います。「あの番組がやっている」、番宣の時に「今回はあの地域で、きっとこういう展開なのだろう」「こういうところに力をあてるのだろう」というのが分かり易いので、シリーズものであれば、何か特徴があった方が良いと思いました。
・見ていて自分自身が落ち着いた感じになりました。なぜかなと考えますと、歴史が分かり、皆さんより私はとても歳を取っているので昔のことが思い出されました。魚を釣っている風景を見ると、父親があのようにして魚を釣りに行ったことや、一緒に行こうと船に乗せられ釣りに行ったことを思い出しました。また「塩田の塩は苦いですから」と舐めているのを見た時に、子供の頃に塩1俵を買い、ザルに入れ、納屋に入れておき、落として滴を取っていたのを思い出しました。その滴がニガリです。そのニガリを使いおばあさんが豆腐を作ってくれました。そのようなことを思い出し、懐かしくなり、私自身はこの番組を見て嬉しく思いました。風景の美しさの中に、潮の流れの美しさ、近代的な橋の美しさ、そして人の心と歴史をうまくマッチさせていて良かったと思います。渦潮は徳島にしかないものだと皆思っていますが、瀬戸内にあのような潮の流れがあるということ、観光船などをPRしてほしかったと思います。自転車で橋を渡っているのも、それぞれの島が見えて良かったです。車で走ってしまうのではなくて、愛媛の島のPRができていて良かったと思います。大工さんの手仕事の部分については、プラスティックの船よりも、木の船の方が温か味があり、熱さも木が吸収して良いということでしたが、やはりコンピューター全盛の世の中で、そういった職人技、手の皮一枚で勝負するというようなところが、もっと何かの形で出ても良かったと思います。コンピューターにもできること、できないことがあると思います。私はコンピューターのことは分かりませんが、子供たちの話を聞いていると、コンピューターではできないことがあると聞きますので、やはり仕事をこれから伝えていくことの大切さに、視聴者が心を寄せてくれるような撮り方をしていただいたら良かったと思います。弟子がなく、おじさん独りで可愛そうだと思いました。宮大工や船大工が亡くなっていっていますが、やはりこの世の中には必要であり、弟子が入っていくということをしてほしいと思いました。大三島の相撲も良かったと思います。昔の写真を見ると痩せ細ったおじいさんが相撲をとっているので、哀れな感じがしました。あの方も歳を取るまでやると言っていましたが、あと10年くらいでバトンタッチした方が良いと思いました。相撲取りは太っていないといけません。細々となってから取るのはよくありません。何かの形で教えてあげてください、視聴者からこんな話があったと。落ち着いて見ることができ良かったです。またこのような番組を作り愛媛県をPRしてください。
・加藤氏のゆったりとした話ぶりと歩きが、番組ののびやかさをかもし出していたように思います。居ながらにして三つの島と海をゆったり気分で観光できました。鮮明で迫力ある映像の時代になりましたが、「きれい」な映像であればあるほど、画像に見えない部分への洞察が必要になると思います。つまり綺麗な画面だけでは、観光パンフレットになってしまうように思います。欲ばりな視聴者のためには、画像的にも内容的にも「暗い」部分を味付けとしていれる必要があります。つまり、それぞれの島の特徴ある産業風物にスポットをあてていましたが、島人の生活感がでれば良かったということです。それぞれの家族との語らいを入れるなどして、島の今をよりリアルに描くことが出来たのではないでしょうか。例えば「船大工を孫に継がせたい。孫はその気はない」など。ご多分にもれず高齢化の島で、ひとり暮らしの老人が自炊をするところ、主婦、青年、子どもなどを登場させて、加藤氏と対話の中で、今を生きている島を描く。つまり、観光的な映像にほんの少し裏側を見せることで、表の映像が生きると思いました。番組の作りとしては、加藤氏のリポーターとしての役割を前面に出した方が良いのではないか。例えば古文書を熱心に読む、「こんなものはないか」と村上水軍がらみの痕跡を発見しようと執拗に尋ね歩く記者らしい部分が、一つ二つあれば良かったと思いました。加藤氏の「語り」を読みではなくトークにして、もう少し増やし、時代の変化に翻弄されることなく生き続ける人たちの存在について、社会時評をしてもらった方が番組の色が出たように思います。リポートものは、ともすれば、お膳立てのできたシナリオに、借りてきたリポーターという感じになってしまいがちです。予定したものでない「何か」に驚くハプニングの演出が欲しいということです。大山祇神社の宝物殿は武具甲冑が沢山あって見せ場ですから、内部の映像を撮影できたなら、今に連なる水軍の島を確実に伝えることができ、同時に視聴者を驚かせたと思います。
・良い番組でした。他の委員の方も言われましたが、タイトルが持つ意味「神々が住む」ということを打ち出すのであれば、最低限、参拝の仕方はきっちとした形でお願いしたいと思いました。参拝の仕方については、加藤氏が悪いのではなく、制作側がきっちり伝えてあげるべきだと思います。例えば、出雲大社で参拝している画像がよくありますが、それは私が知る限り、きっちりした参拝の仕方の映像が撮られています。そこがあるかないかによって、この番組がもっと生きる、荘厳さを持った良い番組になると思います。モノづくりなどについては、皆さんと重複するので省きます。委員の意見に反対する訳ではありませんが、そこの島々の方たちの生活がなかったからこそ、美しい番組に仕上がったと個人的には思います。関係はないかもしれませんが、全部終わったあと、神社のCMが出ましたが、良いと思いました。そこまで全体をコーディネートしたのであれば、すごさを感じます。塩田風景は、昔は坂出のあたりでよく見られ、岡山の大学に行くとき、宇高連絡船に乗るために、高松に行く途中で坂出の塩田を見ると、親元からここまで離れてしまったなと思った時代を思い出しました。時代も変わり、昔の良さを見直す時代になっていると思いました。失われた風景など、色々発掘しこのような番組作りをされると良いと思います。これは若い人たちにぜひ見てもらいたいと思いました。
・1回目、2回目の番組についても、BSでの作り方とeatでの作り方を見比べることができれば良かったと思います。番組課題として、「eatではこのような番組に仕上がっている、BSではこのような番組に仕上がりました」といった見比べができれば今後は良いと思います。今回は何日くらいの取材、収録だったのですか?釣りをしたり橋を渡ったりするなど、かなり長期間かかったのかなという感じがしました。
・BSで放送したものとは思っておりませんでした。この資料を見ると、BSの放送は10月4日で、eatでの放送は12月28日とタイムラグがあります。地上波で見ている人にとっては、服装、風景がミスマッチというか、年末にしては季節感が合いませんが、それが原因かと思います。宗教に絡んだ行事、参拝する時の作法につきましては、私自身も神社に行く時には、きちんとやらないといけないと思っています。昔、アメリカの会社にいて、イギリス人と一緒に神社に行ったことがあります。その時、どのようにしたら良いのか、色々質問をされました。若い時だったので、あまり分からずに、日本人として間違ったことを言ってしまったと思った苦い記憶があったので、それを反省して、きちんとやろうと心に決めました。ですから私も見ていて加藤氏が気になりました。広告には「朝日新聞」と大きく載っていますが、朝日新聞とBSというイメージで番組が作られているのかなと思いました。愛媛という要素については、eatプラス愛媛、eatプラスBS朝日の「eat」の部分があまり見えませんでした。地元をもう少し宣伝し、集客したいという目から見ると、このような文化があり、愛媛は良いという風に持っていきたい気がします。愛媛に関係した人だと、そういう思いを持った人がいると思います。番組全体としてはスムーズに見ることができました。年末慌ただしい時にこういう番組を見ると、心も安らぐと思います。