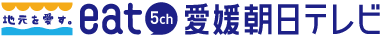第196回放送番組審議会議事録
開催日時:平成26年9月25日(木)午後3時00分
課題番組:「球は霊なり~台湾へ 海を渡った愛媛野球 近藤兵太郎物語~」
平成26年5月29日(木)27時05分~27時35分(30分)放送
(1)課題番組の審議
・近藤兵太郎という人物のことは、ほとんど知りませんでしたが、林司朗氏はよく存じ上げているので、親近感を抱きました。ただ、放送時間が27時台ということで、普通の人が見ようと思う時間帯ではなかったことがとても残念でした。もっといい時間帯に流して、広く愛媛県の人に見て欲しかったと思いますし、今後の再放送にも期待したいと思います。劉正雄さんが流暢な日本語で「球は霊なり」と言っておられたのが印象的で、こういう人が社会に出て通じる人間を育てるのだと思いました。野球というスポーツを通じた人間形成のすばらしさ。こういう人に薫陶を受けた人は立派な人間になるのだろうと実感しました。最近の松山商業野球部はやや低迷している感がありますが、それは、この精神が途切れたからなのか、それともどんな組織にも寿命はあり、その寿命が来たのか、などいろいろ考えさせられました。
・高校野球については、知識が乏しいうえ、いろいろ鳴り物入りの番組だったので、かなり期待をして拝見しました。映像はとても美しかったと思います。また、情報量が多く、いろいろなことがわかったので知的好奇心を満たされ、面白いと思いました。ただ、近藤氏の人となりを知ることができるエピソード、あるいはインタビューだけではなく、他の観点からの情報があればよかったと思います。
・野球王国と呼ばれる愛媛の放送局ならではの番組だと思います。なぜ野球王国となったのか、野球王国と呼ばれるようになったのか、その原点が理解できました。近藤兵太郎氏のことは、野球のことをかなり詳しく知っている人でも知らないと思います。台湾で映画化され、松山市にとっては、松山-松山便の就航とも重なるタイムリーな話題です。そもそも、甲子園に台湾から出場した学校があるということも知らなかった。そこそこ知っているつもりの私ですが、知らなかったことが如何に多いかも思い知らされました。また、野球を通じた人的交流により培われた友好関係は非常に強いのだと実感いたしました。
・近藤兵太郎という人のことは全く知りませんでした。番組を見て、気になったこととしては、まず近藤兵太郎という人のことをどうやって知ったのか、また、この番組はどういう視聴者を想定して作ったのか。さらに、松山商業野球部にスポットを当てているのですが、今の生徒からコメントがないのは何故なのか。低迷しているのはなぜなのか。このような熱い指導者が少なくなったのか、今の生徒は近藤兵太郎さんのような指導法では指導できないのか。そのあたりが気になりました。社会に出て通用する人間をどう育てるのかという視点は、悪い意味ではなくNHKの教育テレビのような切り口だと思いました。いろいろな意味で勉強になる番組でした。
・聴衆として、台湾の人ばかりを集めたリサイタルをしたことがありましたが、知日家、親日家は多く、日本の歌もよく知っています。日本人以上にマナーもいい。そういう台湾の方たちの良さが伝わってきました。ただ、放送時間が悪すぎる。まだ、深夜でなく早朝の方が良かった。非常にもったいないと思います。今の松山商業野球部が低迷しているのは、原点を維持することのむずかしさなのでしょうか。しかし、野球に興味のない人にも面白く、役立つ番組でした。
・映画になったことで近藤兵太郎さんが浮かび上がって来たのかもしれませんが、愛媛朝日テレビの強みである”野球”を軸にした細やかな情報収集力を活かした番組でした。放送時間が異常に遅いですね。びっくりしました。見終わって2つの”なぜ”が残りました。1つめは1919年31歳のとき台湾へ移住されたことはわかりました。しかし『なぜ台湾なのか?どのような経緯でいくことになったのか?』私が見落としたのかもしれませんが、わかりません。2つめは近藤さんのご家族はどのように近藤さんの野球人生を受け止めていたのかという点です。全体的に監督と選手の繫がりは描けていたと思いますが、今ひとつ近藤さんの人間像がファジーです。また『魂の入っていない野球はやるな』の精神論は十分強調されていたのですが、具体的な戦術や方略についての内容が薄く,これもまたファジーでした。村上さんのナレーションは声が明るく、若く(若いから当たり前ですが)初々しさに溢れていました。何カ所か「しゃ、しゅ、しょ」と「サ行」を発音する際に、息が、マイクにあたり、その音が収録されてしまっていたのが気になりました。録音技術の課題かもしれませんが。もう一点気になったのが、中国語で話されるサイ監督の日本語訳の字幕が、監督の白いユニホームと重なってしまい、字幕がほとんど読み取れませんでした。これはとても残念でした。最後に、窪田さんの登場など、地元を活かし、懐かしい名場面、おそらく秘蔵と思われる写真がふんだんに盛り込まれていて、楽しめました。実直な作り方で、近藤さんの教え子の皆さん、共に野球に関わってこられた皆さんに喜んでいただける番組づくりになっていたと思います。
・オープニングは、2人の方のコメントから情熱的なものを感じ、また高校野球(松山商業)の名勝負のシーンから高校野球ファンにとっては引き込まれる感じで、好感が持てた。タイトルの「球は霊なり」の字は、どなたが書いたものなのか?または単にこういう種類のフォントがあっただけなのか?字が素敵だった。近藤氏の略歴で、正岡子規が野球を伝えた年と没の時間軸でリンクさせているのはとても分かりやすい。松山商業高校・嘉義農林の野球の歴史における近藤氏の功績を知って「そんなにすごい人がほとんど知られていない」ことに素直に驚いた(私も松山商業出身ですが、近藤氏の話は聞いたことがありません)。何気ない挿絵なのかもしれませんが、グラウンドの水たまりに雨粒が落ち、ライトが揺れる映像は、とても美しいと感じた。台湾現地に飛んで取材することで、単なる偉人伝ではなく、劉さんが「近藤先生」と呼び、近藤氏の指導内容まで鮮明に覚えていらっしゃるところに、指導者としての人柄が伝わってきた。「球は霊なり」の意味が、番組中ほどで、劉さんの言葉で明かされる。「精神が入っていなければ球にはならない」「魂の入ってない野球はやるな」・・・これは野球だけの話ではなく、仕事においても同じことが言える。もの凄く共感させられた。また、劉さんの「僕たちを育んでくれた」・・・この言葉に、高校野球の監督ではなく、育成者としての近藤氏を感じることができた。異なる3つの民族に分け隔てることなく教え、その特性に応じて配置して長所を活かすのは、近年のダイバーシティ(多様性)に通じる。また、窪田氏がいう「精神野球」と近藤氏の「球は霊なり」、窪田氏の「定石」と近藤氏の「3割は基礎」という窪田元監督と近藤氏との共通点は、座ってパソコンで検索すれば答えが出てくる時代にあって、その教えは、ますます必要になると思う。そして、新田高校の教え子でいらっしゃる林氏の「本当の根にあるものは、社会に通用する子どもたちを作る」「負けることは構わない。けど諦めてはいけない」のコメントでもあるように、こういう”厳しさの中の愛情”というものが、家庭教育・公教育・企業教育において薄れゆく中、何度もリピート放送して、多くの方々にこの番組を観て頂いて、感じ取って頂きたいと強く思った。
・野球王国愛媛の礎を築き、台湾でも野球指導の業績を残した近藤兵太郎の足跡を紹介する番組を興味深く拝見しました。単なる人物紹介にとどまらず、愛媛と台湾の教え子の証言を絡み合わせて「球は霊なり」の精神野球の尊さを伝える番組を興味深く拝見しました。台湾での映画のヒットと故郷松山での顕彰の動きをとらえての報道は時宜にもかなっていたと思います。ただ、構成はインタビューと映画の映像に頼りがちのうえ、映像が無かった時代の出来事なので、同一写真の多用が目立ったため、立体感に欠けた嫌いは否めません。取材時間の制約もあったのでしょうか。教え子インタビューも、もう少し幅広い人からエピソードを聞きたかった、との印象を持ちました。あと1点、松山商業のユニホームの変遷。高校野球ファンにはとても興味深い話ですが、番組の趣旨に照らすと必要なものだったか、疑問を持ちました。場つなぎにこしらえた感が否めません。番組時間が30分と短時間だったため、人物像の掘り下げにもっと時間を割いても良かったのではないでしょうか。
(2)諮問への答申決議について「愛媛朝日テレビ放送番組基準の変更について」
・本件諮問に係る「愛媛朝日テレビ放送番組基準の変更について」は、結論において妥当である。