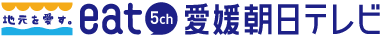第195回放送番組審議会議事録
開催日時:平成26年7月25日(金)午後3時00分
課題番組:第83回テレビ朝日系列番審委員代表者会議の議題
「今の時代、本当に見たいテレビ」
(1)課題番組の審議
・今、どのような番組を見たいのか知人に聞いてみたのですが、なかなか意見がでませんでした。正直なところ、テレビなかったら困るか、といわれると、困らない。災害情報も携帯電話やスマートフォンでわかる時代になりました。テレビをよく見るという人に聞いても、何かをしながら見ていることがほとんどです。家事、ゲーム、ネットサーフィンなどをしながらテレビをつけている。テレビを消すとさびしいが、ないと困ることはない。中には、情操教育を考えて子供にテレビ見せない人もいますが、女性、男性、母、父、立場違うと意見も違うと思います。テレビ不要論もある。本当に見たい番組が何かといわれても一通りの答えにはまとまらないのではないでしょうか。
・私はテレビが好きで、一日中テレビの電源を入れています。番組もいろいろなものを見ます。スポーツはよく見るし、朝ドラなどNHKを見ることも多い。民放ですと、通販が始まるとチャンネルを変えてしまいます。夕方はニュース、スポーツなどをよく見ます。家事などいろいろなことをしながら、番組がついている。子供はとても忙しくチャンネルを変えます。同時に、いろいろな情報を早く集めたいようです。一方、家族全員が同じ番組をみて楽しむことはなくなりました。勉強をしながら、テレビのそばで、スマホをいじる時代になっています。民放連では、番組の分類をしているようなのですが、何がどれにあたるのか、よくわかりません。子供が言っていますが、バラエティ番組の副音声を英語にして、トークを英語で楽しみながら、勉強ができるような発想が欲しいと思う。
・もう少しいろいろな情報が出た方がよいという意見のように思います。テレビの周りに家族が集まるという意味では、テレビが茶の間の中心になっているといえると思います。
・テレビに子守りをさせのはけしからんという話もあるが、これはテレビそのものの問題ではなく、使い方の良し悪しの問題だと思います。
・主婦、障害者のように、社会との接点が限られている人にとって、テレビ番組は、いろいろな人がこの世にいるのだということを感じる一つのチャンスになっています。テレビ番組を見ることで、孤立感がなくなったりするし、社会の情報を獲得したりする必要なツールだと思います。この設問については、テレビが、社会においてどういう意味で必要とされているかという角度から考えると回答に近づくのではないかと思います。他者に対する好奇心を持つことはコミュニケーションの原点ですが、そのためにテレビが果たす役割は大きいと思います。
・テレビは、tele(遠い)vision(見る)というところから名づけられているのですが、その名前の由来を考えるべきかも知れません。テレビについて、最近は番組内容に偏りがあることに懸念を覚える。最近、中東情勢などはアラビア語メディアをよく見ているのですが、残念ながら日本のメディアは一方的なものが多い。本当の意味で多角的な情報を出してほしいと思います。しかし、あまりにも多様な情報を詳細に扱うようになると、プライバシーの侵害にもつながる。また、最近気がついたのですが、意外と昔の番組が面白い。老人がBSを見るのは、昔の番組を見たいからだという指摘があります。
・こういうテーマが出てくることに危機感を感じます。また、こういうテーマが出てくること自体、テレビを作っている人たちも危機感を感じているのだろうと思います。インターネットのグーグルはCMの世界にも目覚ましい進出をしています。そういう動きを見ていると、テレビがなくなることはないと思うが、ビジネスモデルが継続できるのか懸念があります。しかし、主体的に情報を求めなければならないインターネットに比べると、テレビの方が楽であり、ネットへの利用者のシフトはそんなに劇的には進まないと思います。質のよい番組さえ作れば、その番組に関心をもつ視聴者の支持は得られると思います。しかし、ビジネスモデルは変わるのではないか。面白い番組を作るのは大変な仕事であるとは思いますが。
・笑っていいともが終わったとき、テレビの一つの時代が終わった気がしました。時代を先取りした番組としてスタートしたのですが、いつまでも先取りしつづけることはできない。いつかはマンネリ化する。マンネリ化をいかに脱するか、それともマンネリ化して終わるのかが分かれ目ではないかと思います。個人的には、最近はマツコデラックスにはまっている。切り口の違う多くの番組に出ています。「見たい」という意味をどのような時代のスパンでとらえるかによるが、マツコデラックスのような魅力ある人物が出れば、人気が回復すると思います。
・私は「さんまのからくりテレビ」が好きでした。私はDVDで数番組を録画して、後で面白そうなものを選んでみているのですが、あの番組はほぼ毎回見ていたので、あれが終わるのはある意味ショックでした。私は、暗いニュース、深刻なドキュメンタリーではなく、ほのぼのしたバラエティが見たいと思います。先ほど、コミュニケーションの話が出ていましたが、受け取る側がどのようにとらえるかによりコミュニケーションの内容は変わります。テレビはコミュニケーション能力に優れた人、知識の豊富な人が一度にたくさん見られるものであり。そういうものはテレビしかないと思います。
・「珍百景」は日本の古い時代のいいものがでています。テレビはローカルに近づいてほしいと思います。テレビ視聴者の年齢層は幅広いのですから。「本当に見たいテレビ」と「テレビの役割」とは同じテーマです。温かいものを発掘してほしいと思います。
・一新聞記者として、読まれる新聞とは何か、デジタル発信を含め新聞社の報道はどうあるべきか、日々、模索しております。「今の時代、本当に見たいテレビ」という問いは、新聞とテレビとの媒体の違いこそあれ、マスメディアの悩みとして相通じるものを感じます。難題です。
子供のころ、ホームドラマやプロ野球ナイター、時代劇など、茶の間でテレビを囲みながら一家団欒のひとときがありました。チェックしておかなければ時代から取り残されるというトレンディドラマ隆盛時もありました。ただ、ここ数年で欠かさずに視たのはドラマ「半沢直樹」くらいしか記憶にありません。バラエティー番組はどの局も似たようなつくりで魅力に欠けます。
今の時代、パソコン、スマホ、ゲーム機などと向き合う時間が増え、視聴者とテレビとの関係は様変わりしています。テレビ機を通じて視聴できるのは地上波だけでなくBS、CS、CATVなど多様化しています。私自身、大阪本社勤務時は、仕事柄、最新のニュースを24時間流し続けるスカパーの番組を月400円で契約していました。定時放送の地上波ニュースは見逃す可能性があるからです。
地上波のあり方について、キー局と地方局は分けて考えたらいかがでしょうか。とりわけ地方局については、地域密着型のCATVに対して、優位性を持った番組を提供できるかが大切だと思います。県全域のニュース番組は重要でしょう。視聴者の関心は高いはずです。愛媛朝日テレビさんのJチャン愛媛が高視聴率なのも、番組作りへの力の入れ方が結びついた結果だと思います。また、仕事とは関係なく、各局の地元情報番組も楽しんで見ています。こうした番組とキー局が作る良質な番組を組み合わせることで、地上波に視聴者を引きつける効果を生むのではないでしょうか。
ちなみに、家族に見たい番組を聞いてみました。中1の長男と小6の長女は、好感の持てるお笑い芸人が出る「面白い番組」。芸人さん達でも、下品過ぎたり、ただただうるさいだけだったり、というのはイヤだそうです。嵐が出演するバラエティー番組も好きです。好感の持てる5人が、いろいろな競技を出演者と楽しく競うところが、見ていて気持ちがいいのでしょう。子供ながら、好感度を重視しているようです。妻は、ある場所を定点観測して、訪れた人にインタビューする番組。ファミレスやスーパー銭湯、スポーツジム、ゲーセンなど、毎回場所は変わるけど、いろんな人間がこの世の中にはいるのだと改めて感じるそうです。家族そろってリフォームやお宅訪問などの番組も好みと言います。様々な家庭の暮らしぶりに触れてついつい見てしまうとのこと。サッカー日本代表の試合、代表選手に出ている番組にも関心を持っています。一昔前に比べてサッカー人気が高まっていることを反映しているようです。
(2)諮問「愛媛朝日テレビ放送番組基準の変更について」
・民放連の放送基準が平成26年6月13日付で一部改正され、来る平成26年11月1日から施行される予定となったため、当社でもこの変更を盛り込みたいと考えております。これは、間接的に当社の放送番組基準の変更となるのですが、放送事業者が放送番組基準を変更する場合は、放送法第6条第3項により、その放送事業者の番組審議機関に諮問しなければならないこととされています。このため、諮問文をお読みいただき、妥当であれば、次回の審議会で妥当であるという答申をいただきたいと思いますので、ご検討をお願いいたします。