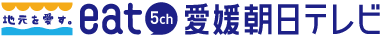第111回 放送番組審議会議事録
開催日時:平成18年3月27日(水) 午後3時
課題番組:「ふるさとCM大賞EHIME」
1. 開催日時:平成18年3月27日(水) 午後3時
2. 課題番組:「ふるさとCM大賞EHIME」
平成18年2月25日(土)13時05分~14時35分(90分)放送
3. 記事の概要:
・とにかく面白かった。絶対に大洲市が大賞を獲るに違いないと思っていたら、その通りになった。次に好きだなと思ったのは、久万高原町のもので、野菜をかじっている様子がよく伝わってきて、素晴らしいなと思いながら見た。伊方町の「よめこい踊り」をしている人が、実はお嫁さんがいるというのも面白いと思った。また、舞台に出ている子供と審査員のやり取りがほのぼのしていて良かった。こういう番組は、一人や二人が参加するのではなく、地域の人たちが大勢参加して画面に出てこないとだめだ。気になったのは、司会者のコメントで、あの程度のコメントなら原稿に眼を落とさず、覚えてしまわないといけない。プロ意識に欠けている。名前を間違えてはいけないということだとは思うが、ちゃんと覚えて相手の顔を見て話をしなければならない。また、司会者の服装が如何にも浮いていた。それも、高級なものではなく、如何にも化繊の安物で、愛媛県内だと野村町のシルクのドレスとか、そうでなくても伊予絣とかいろいろありそうなものだ。番組に相応しい服装はどうあるべきか配慮に欠けているといわざるを得ない。また、桂小枝さんと二人の司会者の遣り取りも気になった。やはり、格が上の人に対して、ただの「にぎやかし」とか言うのは如何なものか。また、審査員の石井達矢さんが、今治市の高校生が「悪いところも教えて欲しい」と言ったことに対して、「役者かな」と冷たく言い放ったのも、素人に対しては洒落にはならない。がっかりいたした。松岡誠司ディレクターのナレーションは、今の時代にぴったりで、なごやかで、あたたかい感じがして良かった。松岡さんの顔を知らない人は、「松岡さんはどんな人だろう」と思って、いろいろ想像したのではないか。全体としては、本当に楽しい、90分という時間を感じさせない番組だった。
・このイベントを見て、ぱっと思いついたのは、「欽ちゃんの仮装大賞」だが、あの番組も、企画の段階では、「果たして、こんなものが番組になるのかどうか」という不安があったと思う。このイベントも、企画の段階では、そういう意見があったかもしれない。しかし、現実に作ってみると、明らかに面白い。飽きない。もっと見たくなる。この番組も、あの「仮装大賞」同様、「化ける」要素がある。一つには、これまでは「視聴者参加」といっても、それは「視聴者」として参加するのであって、視聴者が制作者側にまわることは殆どなかった。この番組は、視聴者が制作者側にまわり、視聴者が画面に出演する。一種の「変身願望」を満たす。誰しも「変身願望」があると思うが、そういう部分をうまく活かしている。また、一種の「民活」というか、実は、市中にプロデューサーや役者はゴロゴロしているのだということ、これを明らかにした。こういうものができれば、未来は明るいと思う。メディアがどう変わろうが、結局はソフトだ。勝負はそこで決まる。この番組は、それを教えてくれていると思う。だから、何か、番組のコンペのようなものがあれば、この番組は是非出品してほしい。そのぐらいの評価を受けるべき番組だ。また、実は、私はこの番組の中で3秒ほど映っているが、たった数秒出ただけでも、あちこちから電話がかかってきた。やはり、テレビに出るというのはうれしいものだ。そして、そこには、視聴者参加ということの本質が顕れている。視聴者をテレビに出す、テレビに出たいという視聴者の欲求を満たすということは、実はテレビ局が視聴者に対して提供しなければならない重要なサービスの一つだ。しかし、視聴者をテレビに出すといっても、ふつうは、映すだけ。視聴者が長い間かけて積み上げてきたもの、場合によっては何十年とかけて築き上げてきたものを、ほんの数分だけ上面をなぜるという程度に終わることが多い。しかし、この番組はそうではない。その人たちに本当に喜んでもらう方法がここにある。本当に拍手喝采をしたいぐらいの番組である。番組の中で出てくる作品については、個人的には、松前町のCMが面白いと思ったが、ちょっと玄人向きかもしれない。残念ながら入賞しなかった。全体として、非常にいい番組を見せていただいた。夢ができた。この番組を見て、自分も作ってみようと思う人が出てくれば、自分の街を見つめなおすには非常に良い機会になる。誇りに思うチャンスが増える。そして、自分の街の将来について考えるうえで、いろいろな糸口が見えてくる。制作者が考えている以上に良い番組ではないか。
・上手な作り方をしている。内子町の「わしのこと好きか」というのは、最初は、このおじいさんはいつまでも元気だな、達者だなと思っていたら、実は、「わし」を「和紙」にかけていた。オチのところで、ぐっときた。松前町は、水をふんだんに写していて、これは松山市民としては、なんとなく嫌味な感じがしないでもない。また、三瓶町の子供が地図の間違いを指摘したところなどは、郷土愛はいいな、また、子供は素直でいいなと思った。松野町のところで、合併できずに孤立したというような弱音のようなことを言っていたが、小枝さんが「明るくあらねば」とはげましていた。私も同感で、今の愛媛の現実を垣間見せた、面白い遣り取りだった。地域密着ということがお話に出たが、これからは一歩進めて、地域発信をしていただきたい。CM 素材の交換の話があったが、ぜひ実行していただいて、良いものが多いにも関わらず知名度の低い愛媛の産物を全国に知らせていただきたい。地域内だけで密着するのではなく、その情報を外に発信していただきたい。
・番組放送後、大賞になった大洲のCMが流れているのをよく耳にする。やはり、年間200回というのは、かなりの量だと思うので、PR効果は大きいと思う。今回は、自治体によって力の入り方が違っていたが、あれだけ聞かされると、自分の街も是非と思うようになり、来年からは、今回必ずしも積極的でなかった自治体も、かなり力を入れてくるのではないかと期待される。来年以降どんどん面白くなるのではないかと思う。
・この番組を録画で見る前に、大賞受賞作の大洲のCMを見て、なぜかちょっと涙ぐんだ。番組の最後に、審査委員長の天野祐吉さんが「ふるさとへの愛情の強さ」を指摘しておられたが、まさにそれを感じた。皆さんの一生懸命な意気込みが、シンプルな作品の中に凝縮されていて、それが率直に伝わってくる感じがする。CM制作の過程で、自分たちの街のいいところを探すことになるが、改めて見直して、いいところを探すことによって、自分たちの街のいいところを再認識し、共有したうえで、制作できるというところは素晴らしい。小枝さんについては、やはり「ただのにぎやかし」ではもったいなくて、「探偵ナイトスクープでおなじみの」とか「幸福モードでおなじみの」というふうに紹介すれば、そちらの番組の紹介にもなっていいのではなかったか。石井達矢さんのコメントは、的確で説得力があり、音の工夫の話など、私たちが普段何気なく見聞きしているCMを見直すきっかけになった。方言については、「びやびや」という方言は、初めて聞いた。また、新居浜の方が話している言葉の中に、夭折した友人が遣っていたものがあり、胸に迫るものがあった。そのほかにも親しみのもてる言葉が沢山でてきた。CM素材の交換の話は、まさにそうすればいいなと思っていたところだ。JRグループなどは既に他地域の会社のポスターを駅に貼ったりしている。衣裳やヘアメイクは、アカデミー賞などを意識して、あのような感じにしたのだと思うが、もう一工夫欲しいと思った。タイトルには「第一回」とはついていないようだが、頑張って次回の開催も検討していただきたい。
・まず、意外と松山市のCMはつまらなかったということがある。また、すごいなと思ったのは、大洲市、久万高原町から南にかけてのエリア、ここからの作品が面白い。人情とか、子供の表情が、忘れそうになっていたものを思い出させてくれるような時間を持つことができた。愛南町も良かったし、内子町も良かった。自治体により力の入り方が全然違っていたというのは確かに感じられたが、今度はどの自治体も力の入れ方が変わってくるのではないか。ただ、そうなると背広姿の役人の歴々がステージ上にずらっと並ぶということも予想されるが、これだけは警戒していただきたい。やはり、城のかぶり物をさせられている子供たちや、海苔をかじっているおじさんとか、そういうキャラクターが舞台に上がって自然体に振舞える、そういう雰囲気を大切に残しながら、回数を積んでいただきたい。ふるさとCMというのは情報量の勝負ではなく、その街に住んでいる人たちが生活の中から見つけ出した面白いこと、好きなこと、そういうものが沢山あればあるほど、いいCMができるのではないか。そういう感じがする。撮影、パフォーマンス、CM、コメント、メイキングなど、いろいろなファクターから番組を組み立てているが、これから続けていく上で、それらの質をどう確保していくのか。局の頑張りに期待していきたい。また、こういう活動を応援できる企業は素晴らしいと思う。
・「ふるさとへの愛情を感じる」というコメントがあったが同感だ。ふるさとへの愛情が、CMの随所に顕れてくる、いい意味での小さな地域間競争が、これから番組を続けていく中で出てきて、盛り上がっていくのではないか。今回の催しで、ある程度番組としての認知度は確立できたと思うので、次回は、是非、もっと街中で、アクセスしやすい場所で、地域の物産展や「うまいもの市」なども催しながら、一つの大きなイベントとして発展させ、そのなかでCMの審査会をすれば、より一層ふるさとを身近に感じることができるようになるのではないかと思う。この審査会のあと、番組のOA前に「いーテレ」のなかで、この番組に関する話題をとりあげていたが、それを見たあと、この審査会の番組を見てみると、この番組の中には、他の番組作りのネタになるような要素が沢山ふくまれているように思った。そういう意味では、見て楽しいだけではなく、局にとっても発展性のある番組になっているのではないか。このもっと発展して、全国単位で大会のようなものができていけば、おもしろいと思う。
・地域との結びつきを深めるためには非常に有意義な番組だと思う。ただ、最初に、競争のルールの説明がない。いきなり番組が始まってしまう。たとえば、30秒CMのコンペだという説明もない。これから、回を重ねていくにはルールを明快にする必要がある。また、メイキング、CM、会場でのパフォーマンス、審査員のコメントなどのいろいろな要素が今ひとつまとまりが無く、平板に羅列されている感じで、なんとなく小学校の学芸会のようになっている。もう少しメリハリのある形で整理できないかという気がする。ただ、それはそれで各地域の特徴が良く顕れていたともいえる。小枝さんについては、なぜ地域のイベントに他所から芸人を呼ぶ必要があるのか。愛媛にもたくさん芸達者な人はいるし、たまたま中央に居ないために目が出ないという人が愛媛にはたくさんいる。放送局はそういう人を起用して、光を当てることも大切な役割ではないか。特に、この番組の趣旨からするとそういう人を使うということは大切だと思う。また、市長や町長などが登場するのは、権威主義のようで番組の趣旨にはそぐわない。審査委員長の天野祐吉さんは、局に配慮したのか、欠点を鋭く指摘するような場面がなく、コメントに普段のような切れ味がないように感じた。こういう地方から発信する番組は大切だ。また、いままでのマスメディアの盲点だったところだが、小さいところにスポットを当てるということ、これは例えば「口コミ」が今まで担ってきた役割だが、それが今のトレンドである、ということを指摘しておきたい。