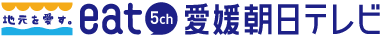第138回放送番組審議会議事録
開催日時:平成20年11月28日(金)午後3時
課題番組:「瀬戸内海から地球が見える」
1.開催日時:平成20年11月28日(金)午後3時
2.課題番組:「瀬戸内海から地球が見える」
11月10日(月) 19時00分~19時54分(54分)放送
3.議事の概要:
・日本海では越前クラゲが大量発生していますが、それとナルトビエイの大量発生とは問いかけるものは同じです。自然環境を考える優れた番組だと思います。悪者扱いせず、環境の変化とともに地球人はどう対応するのかを投げかけていると思います。
・ナルトビエイに着眼していることが手柄であると思います。美しい海で大きな生物を追いかける、そこで半分くらい成功していると思います。ナビゲーターの大杉連氏は旬の人であり、徳島出身で愛媛にも縁があるという起用は良かったと思います。高感が持てる俳優です。神戸の海水浴場にサメが出るほどの驚きはありませんが、巨大なものが突然現れると驚くと思いますし、一番大きな敵の温暖化・人類の経済活動、巨大な敵に大掴みでやっても番組にはなりません。ですがこの番組はディテールに入っていく手法が良かったです。ただ、「人間も敵」という切り方については疑問を持ちました。またナルトビエイを食べるといいのだという印象が強く残っています。人間活動がナルトビエイを苦しめ、招いている、それを食べるという印象が強く残りました。この50分の番組の中で、ディテールにこだわって申しますと、心に残るフレーズが、美しいもの、生き物を捉えていますが、その感性に訴えるものが少ないと感じました。愛媛にはナルトビエイやアサリはいないと言っていますが、そこまでデフォルメする必要があるのかと疑問を感じました。全体的には、これまでの各局協力で作った作品の中では、エリア主義が少なく見やすい番組ではありました。
・2回見ました。50分の番組は1度見ただけでは分かりにくく理解できない部分があり、2回目でクリアになってきました。50分という長さはそれだけでボリュームがあります。起承転結があり、どこがポイントなのかが1回では分かりにくかったです。手法の問題ではありますが、「人間のせいだ」と言う部分がありましたが、それが何のことなのか分かるまでにCMもあり時間がかかっていました。もう少し早く理由を出した方が分かりやすいと感じました。小説のように時間をかけて表現するのではなく、映像なので早く答えを出した方が良いと感じました。見ていて2つのメッセージを得ました。一つは、温暖化の問題がこの瀬戸内海でも起こっており、その影響でいないはずのナルトビエイが現れアサリが獲れなくなっているという問題提起。普通の地球温暖化、環境破壊の番組は問題提起で終わります。もう一つは、環境変化でナルトビエイが増加はしたが、それを食材化することで対応し、温暖化で環境が変化したことに対して人間側も対応している「しなやかさ、強さ」、変化しようというメッセージを感じました。温暖化とともに我々も変化しなくてはいけないのだと感じました。瀬戸内海の水産試験場が紹介されていましたが、連携を取るべきと考えます。別々に研究をするのではなく、連携することの大切さをこの番組で問題提起する見方もあったのではないかと思います。1/2000の模型は面白かったです。板甫牡蠣が絶滅し、もう一度復活させようとしている場面は、環境破壊とは関係なく、人の乱獲の影響でいなくなったもので、それを復活させようとしていますが、これは環境問題とは関係ありません。やりすぎは良くない、貪ってはいけないという意味では、今の金融危機と似ていると感じました。チヌがアサリを食べてアサリが少なくなっているということは、人間のせいです。漁業のやりすぎという問題提起の仕方はありますが、そのような点は環境破壊だけではなく、人間の影響も表現されており、メッセージがありました。ですが、どちらかというと焦点を絞った方が良いと感じました。
・番組内では「人間の強さ、したたかさ」と表現されていましたが、環境の変化に応じて人間はどのようにして生き残っていくのかということを考えると、人間の対応能力のすごさを、この番組を見て最後に印象深く感じました。環境問題以上に、水産試験場の方の「したたかさ」はすごいものだという印象が残りました。
・予測しやすい番組の流れでした。アサリの食害が出ているナルトビエイの問題提起から始まり、周辺事情の説明、ナルトビエイの子供は卵で生まれない、同じ瀬戸内海でも広島側と愛媛側では全く違うなど、広島、岡山、山口で全く海の状況が違う、という説明があり、解決策に繋がり、板甫牡蠣を増やす試み、子供たちが藻の繁殖に参加している、ナルトビエイを食用に開発している等、予測しやすい番組の作りで、ストレスなく見ることができました。ナルトビエイを通し番組全体が多面的に捉えられていました。ナルトビエイは、始めは食害を起こすというマイナスのグロテスクなイメージから始まりましたが、途中にはゼロになりました。ナルトビエイだけではなく人間がやっているチヌ養殖も影響しているということで、ナルトビエイのイメージをマイナスからゼロにし、そのあとナルトビエイが食品開発され、開発者の方が「ナルトビエイは天の恵み」とおっしゃっていました。そこでプラスのイメージに変わりました。テレビ局の番組作りには多面的な物の見方をしてほしいと思っていたので、それができていたので評価しました。大杉連氏はナビゲーターとして上手でしたが、市民や学生や面白い人を起用することにも、新たにチャレンジしてほしいと思います。
・ナレーションも大杉氏にやっていただきたかったです。報道番組でナレーターを使うとフィルターがかかってしまいます。ドキュメントタッチが出てこないので、大杉氏本人が足を使い見て仕上げてほしかったです。環境問題は着地点が難しいと思います。環境問題は拡散しがちで、集約のしようがありません。そうなると抽象的な言葉で終わり、投げ出してしまいます。ですがこの番組はナルトビエイだけで50分も出ていました。その方が訴求力はあります。食材として利用できるという場面は、放送時間は短いですが、強い印象で、「ナルトビエイが来ても良い、食べちゃえば」という感じになってしまいます。ナルトビエイが投げかけている環境破壊の問題が忘れてしまいそうです。環境破壊について、「テレビを見ているあなたはどうするの?」ということになりますが、今は「あなたがどうするのか言えない状態」だという表現でも良いと思います。無理やり着地点を見つけるというのは不必要な時代になっていると思います。テレビ局が着地点を見つけ「こうなのだ」という時代ではもうないと思います。
・私の頭の中には「食べる」という着地、結果的に食べるという画面が強く印象に残りました。食べれば良い、チヌ・アサリの商品価値を比べたり、アサリがいなくなってもチヌが沢山獲れたり、ナルトビエイも美味しければそれで良い、という結論でした。最後食料品がずっと並んだ場面によって、50分見ましたが、着地点は「食べる、海産物を購入する、グッズが登場する」のではないかと事前に考えました。進め方に関して、最後「食べる」となっていましたので、「やはりな」と思いました。また、番組を一度に見ることができず、何度か止めながら見ましたが、画面に変化が見受けられませんでした。いつもは止めながら見ても、全く違った海の展開があり、様々なものが展開していましたが、今回は画面の変化がありませんでした。またナビゲーターの大杉氏の次の言葉を待つ時間が長く感じました。そういうことが、トータル的に50分の番組を長く感じさせた理由でもあると思います。この番組は一般人が見ることはもちろん意義がありますが、水産試験場の方にも見ていただければと思います。可もなく不可もなく・・・といった感じです。
・見る者がどのように感じるか、どのように捉えるかは、番組を作っている人の落としどころによると思います。どういったところに着地点を求めているのかは、見る者によって多岐にわたります。どのような印象で見るのかも影響されると思います。企画意図説明の際にも、はっきりとしたものが説明の中にはなく、色々な角度、色々な切り口から、様々な捉え方をしてもらって良いという感じでの説明であり、正にその通りだという印象があります。