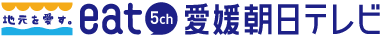第147回放送番組審議会議事録
開催日時:平成21年10月28日(水)午後3時
課題番組:「四季の国~まぼろしの黒茶をもとめて~~」
1.開催日時:平成21年10月28日(水)午後3時
2.課題番組:「四季の国~まぼろしの黒茶をもとめて~」
2009年10月17日(土)10時00分~10時55分(55分)
3.議事の概要:
・今回の課題番組「四季の国」は、シリーズ第6弾になります。見ていて素晴らしい映像の自社制作番組です。全国番審の中でPROGRESS賞が受賞されますが、来年のPROGRESS賞の候補になるのではと思うくらいの出来栄えであったと思います。長い取材期間中に黒茶の製造が終わってしまったということを後世に伝える1つの番組の役割を果たしているのかなという気がします。
・正にBSのことをお聞きしようと思っていたところでした。昨日放送があり、気がついた時は11時前で放送が終わってしまいました。中身が違うということであれば、またBSで再放送されれば見てみたいと思いました。今回のeat制作の番組は加藤氏の出番はあまり多くはなかったので、もう少しコメントが聞ければよかったというのが正直な感想です。見終わった後にホッとするというか、安心する感じの番組だと思いました。また見て終わった後、むなしい感じも少し残り、黒茶が作られないということは寂しいことだなというのが、最後に見終わった感想です。当日、土曜日の朝、生で見ようと思っていたのですが忘れていて、母が隣の部屋で見ていてスカボローフェアが聞こえてきて「あっそうだ」と思いテレビをつけました。スカボローフェアがずっとテーマ曲として使われているのはすごくイメージ的にもぴったり合うのでこれからも続けられたらいいなと思いました。映像と音と淡々と話される曾我部さんの声とのバランスがすごく良いと思いました。騒々しい番組が多い中でゆったり見られて良いなと思いました。800年前からの歴史を持つということにすごいなと思うことと、「何を聞いてもすごいな、山まで上がるのに40分もかかり心臓発作で倒れたらどうするのだろう、あの血行のよさは血圧が高いのでは?」と色々思いながら見ました。大学でお茶のことを研究されている先生も出ていらっしゃいましたが、科学的なことも少し踏まえ、曾我部さんも85歳にしてあの若々しく、足腰の丈夫で、さすがに奥さんは囲炉裏の横で椅子に座っていらっしゃるからお脛も悪いのかなと思いきや、畑で鍬を持ち作業をされていたので、その秘訣などを絡めて科学的にも教えてもらいところがあったので、そういった扱いがあるとよいと思いました。脇さんも一生懸命に山の上まで登っていかれましたが、曾我部さんの芯の強さといいますか、「このお茶は環境が作るんだ」というところにずっしりとくる、良いところに落ち着く感じだという気持ちがありました。淡々と穏やかに話されていますが、芯の強い方で、自然と一緒に生きていく為にはこういった強さがないといけないのだなという事が伝わってくるまとめになっていたと思います。アナウンサーの昔のお茶のコメントがもう一声あれば・・・「初めて飲む味ってどんな味?」と思い、「黒茶」とインターネットで検索すると、黒茶の感想ではありませんでしたが、碁石茶を飲んだ人は「漬物みたいな匂いがして、漬物が苦手な私には無理でした」というコメントがありました。そういった正直なコメントでも良いのでせっかく飲んだので、そういった言葉が欲しかったです。
・このシリーズについては、クオリティーを落とさず、ここまで続けてきていることは、とにかくすごいと思っています。クオリティーを落とさないというより、むしろ上げていこうという情熱が編集、カメラワーク、ナレーションにしてもスキルアップしていく一つの土台だと思いました。制作側の方のクオリティーにこだわる姿勢に賞賛したいと思います。今回すごく感じたことは観察の細やかさとリサーチ力の高さ。石鎚をよく歩きよく訪れている方の目線だと感じました。空撮の取り入れ方、編集の時の取り入れ方が逆にダイナミックになり、BS朝日と提携したことがプラスなのかどうか、細かいことは分かりませんが、全体的な制作スキルが十分に生かされているという気がしました。何よりも今回曾我部さんという人、一つのことに絞って、わき道を辿らず、石鎚の登る道、細い道筋を坦々と歩いていくような番組の掘り下げ方をしている情熱が、見終わった後感動として残りました。むなしさ、寂しさを感じました。二つのお茶の運命を通して見えてくる環境問題、文化を継承することの問題点、すごく伝わってきました。個人的な感想ですが、最後に沈痛な思いの方が段々と強くなっていき、それがどこかというと、脇さんが訪ねていく必要性、おそらく脇さんが行きたがったと思いますが、病気を抱えられ、自由に体が動かない脇さんが行き、その脇さんが曾我部さんに「お茶を失うな」という直接ぶつけるあのシーンは、確かにこれがあったから良かったという方もいらっしゃると思いますが、私はビデオレターでも構わないと思いました。曾我部さんもおっしゃいましたが山の掟、「しょうがない」という言葉は妥当ではないかもしれませんが、巡ってくるという運命はあると思っています。私自身も掟や逆境をバネにしてきたこと、これまでにエネルギーに変えてきたことがあるので、それはそれで分かるのでただそれを静かに迎え入れるという、曾我部さんの気持ちをもっと尊重してあげればと思いました。曾我部さんが責められているような感じがし少し辛かったです。
・山の掟、命、自然に対する姿勢、私も哲学的なものを感じた番組でした。
・映像がきれいでした。花の紹介、最初の雲海、四国、愛媛、どちらかというと南国というイメージがあり、こんな山岳はあまり知られていないと思うので、そういう点では紹介ができ良かったと思います。石鎚山は西日本一高い山で1982m、霊峰と言われています。神宿る山、神社もあり、そういう山なのでそういった紹介の仕方、奥深いもの感じさせる映像が良かったと思いました。脇さんがパーキンソン病の体を押して「もっとやったらどうか」と説得に行くシーンは感じるものがありました。先ほどから見終わってむなしい、寂しいという感想を言われていますが、その通りですが、私の場合はモノの哀れを感じ、有為転変があり、確かに広葉樹が杉、檜に取って換わられ、人為的に近代化、よくある論理ですが、昔からある伝統のものが滅ぼされていくという捉え方もありますが、考えてみれば昔も近代化する前にも滅びていったものはあります。そういった意味でも有為転変というか世の無常というか、モノの哀れとして捉えるのも一つの芸ではないかと思います。それを映像でこの黒茶を題材にして、むしろうまく描かれていると思いました。勧善懲悪やハッピーエンドで全て終わる、世の中そんなものではないので、そういった点ではむしろ淡々と曾我部さんも作るのにお年でもあり、自然もそうであり、後継者もおらず、ある意味静かに滅んでいくというか、そういった事実を報道することは良いのではと思いました。むしろそういったことは黒茶以外に他にもあると思うので、そういう点では人知れず消滅していくものをこうやって映像にし、検証したというか、そういったことだけでも立派なことだと思います。これからもこれに類するようなことがあれば掘り起こしてほしいと、それが報道の役割だと思います。私も黒茶は全然知りませんでした。前に一度見て知りましたが、黒茶は珍しいお茶、発酵茶で中国から伝わったのかどうか詳細は分かりませんが、そういう貴重なものがあるということを知りませんでした。愛媛県人でありながら知りませんでした。検証、掘り起こしを今後もやってほしいと思いました。
・脇さんが曾我部さんのところに行くことになったのは取材の過程でそうなったのですか?もし番組ができなかったら脇さんが曾我部さんのところに行ってなかった、とはいわないが、そういうところがあるのですか?冒頭に「愛媛の視聴者に届ける為にBSとは違い、逆に言うと編集の仕方をドメスティックにした」とおっしゃいましたが、そこがちょっとどうなのだろうなと実は思いました。つまり例えば新宮にしても、高知側にしても県境という人間が作った線から出ているだけの話なので、脈々とつないできたお茶の話で言えば、あまり県の境界線うんぬんはなくて、むしろ脇さんの話や広がりが出たら面白いなと思っていたら、割合・・・もう少しむしろ曾我部さん以外の文化としてそういうものがあちらこちらにあるのだと思いました。特に四国の場合は、四国山地でいえばそれほど愛媛、愛媛と言わなくても良かったのかなという印象でした。総論的に言うと、ニュースステーションの時代によく山の特集がありましたが、その時の自然もの、朝日系列の放送局が得意技にしている、ネイチャーものだとそのへんの匂いがするというか、良い意味ですが、それが脈々と続いているなと思いました。愛媛朝日テレビもそうですし、今度BSと一緒にされるので、ますます磨きがかかると思いました。編集の仕方がもう少し、もっと良い番組に、素材がすごく良く、取材もしているので、編集の仕方がもっとよくなるはずじゃないかなと思いました。素材は極上のものだと思いましたし、皆さんが色々な意味で面白く見たというのはそういった意味で、あえて辛口で言えば、編集の部分かなと思います。BGMのスカボローフェアですが、個人的にはあんまり好きではありません。つまりフィットしているかどうか、ここは好き嫌いですが、少し俗っぽいかなと思いました。
・初対面の方にもお酒が強いと言われますが、実はお酒も飲まず、コーヒーも飲まず、日本茶一辺倒ですので、非常にテーマとしても楽しく見ることができました。10年くらい前の女性誌などの流行はファッションやブランドものでしたが、ここ3、4年の女性誌の流行は生活をテーマに時代もあるとは思いますが、日常生活の中で1つ1つを大切にしましょう、ということをテーマにした雑誌が次々と創刊されかなり売れています。そういったところにもわりとフィットしたテーマだったので若い女性にも受ける番組だと思いました。お茶という生活に密着したものと、曾我部さんの山の中の生活というものに興味を持つ女性も多いのではないかと思います。もう一度見たいと思う番組でした。この発酵茶が結局番組の最後の方で「気力がなくなり、曾我部さんが作るのを止めました」という映像は最終的には、歴史的な文化が消えたという瞬間が映し出された映像だと思いました。後から見ると歴史的に意義のある映像になっていくと思いました。最後の方でアナウンスの中で文明が発達したことが結局巡り巡って非常にこんな山の中にも影響してしまうということが、表現の仕方が強くもなく弱くもなく、適切な表現だったと思います。それが結局、曾我部さんがおっしゃった「お茶は環境が作るんです」というところに結びついていると思いました。「テレビ局に曾我部さんから手紙が届きました」とありましたが、どのようにして?届くのでしょうか?郵便ですか?片道2時間とおっしゃられていましたが、片道2時間かけで郵便ポストに持って行かれたという趣旨ですか?本当なのか、やらせなのかなということが過ぎりました。
・非常にゆったりした番組で、ゆったりした番組がなぜ良いのかというと10人の視聴者がいれば10通りの見方をします。その番組のどこを見るのか?この番組の黒茶が消滅してしまうことを嘆いた人もいますし、自然の素晴らしさを堪能したという人もいますし、老夫婦の行き方に感動したという人もいますし、脇さんのパーキンソン病にも関わらず頑張って行ったエネルギーに感心した人もいますし、様々です。ゆったりした番組を作るとそういったことができます。普通は15秒サイズのカットをつなげたものに見慣れているので、改めてBSの番組の良さを感じました。表面に出ているところは小さいですが、その奥行きの深さを感じたのはこの番組は山村崩壊の一つの象徴としてあったという気がしました。10数件も最近までありましたが、あっという間に無くなってしまった。今田舎で暮らそうという時代ですが、あの曾我部さんが残っていたのは何だろうか?と色々推理します。推理させる力がある番組だったと思います。あの黒茶が存続できなかったこと、言ってみればプライドが傷ついてしまった、「もうできない」というドラマがあったと思います。続けてほしいといっても続けることができない。その黒茶が存続できないという事が、曽我部さんが山を降りる理由にもなると推理もできると思います。色々考えさせられるところがあり、楽しく、奥深い番組だったと思います。委員がおっしゃいましたが、山村の文化が音をたてて崩れきってしまっています。高知県も古い村がいっぱいありましたが、人がいなくなることによって滅びてしまったということを経過報告的に伝えることができた番組だと思います。黒茶だけの問題ではないと見ている人は思ったに違いないと思います。
・最初はDVDで見ましたが、映像が映し出された瞬間、自然な流れで入ってきているナレーションがとても心地よく、このシリーズは、今までも同じアナウンサーだったのかどうかはわかりませんが、全然違ったものを感じました。とても自然で、選曲は好みの問題ですが、今の時代には適しているとは思いますが・・・声のバランスがよく、声とナレーションの声が被らず良い関係でずっと映像が映し出され、風景がきれい、山がきれい、雲がきれいというところから入り、知らず知らずに10分15分が経った、そんな感じがしました。色々見方はあると思いますが、黒茶に対して大きい興味はありませんでしたが、黒茶を通してというよりも曾我部さんを通してこれからの、今までの山での暮らし、これからの僻地の人たちはどういう風な生活をされていくのだろうかということ、ずっと自然は破壊され崩れていき、子供たちもいなくなり、若者もいなくなり・・・黒茶ももちろんなくなり、いつの時代かまぼろしとして、こういうものがあったと語り継がれていく日本の文化になるのかなと思いました。そういったものを映像として残すということは何にも変えがたい素晴らしいことだということを感じながら見させていただきました。病気になられたらどうされるのだろう?と心配し、いつまでもお元気でそこの土地で、育ってこられた土地で過ごしてほしいと思いました。ある日気がついてみれば人生が終わっていたというそういう終わり方をしてほしいと思いました。心が温かくなり優しい気持ちになる番組でした。皆さんがおっしゃられたことと違いますが、儚さ、むなしさはあまり感じませんでした。時の流れが色々なものを儚く流してしまう、そんなものもあるのでは?「昔こういうこともあったよね」と思い出すものがあると思います。すごく良い番組だと思いました。
・一番印象に残っていることは「私が作るのではなく、周囲の環境が作る」という言葉です。自然に対する人間の奢りが自然も枯れていった、自然林から人工林に換えていった、何十年前から徐々に環境が変わっていくものである。自然も無常である、ということを感じた番組でした。委員もおっしゃられましたが、番審委員が8人いますが、8人の視点から色々なご意見がいただけたと思います。