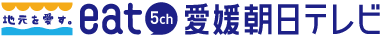第199回放送番組審議会議事録
開催日時:平成27年1月23日(金)午後4時00分
課題番組:中四国ブロック特別番組「村上水軍と塩飽水軍 海の覇者 瀬戸内海賊ヒストリー」
2014年11月8日(金)午後2時00分~2時55分(55分)放送
・和田竜さんの「村上海賊の娘」がブームとなったわけですが、この番組は単なる村上水軍ブームの紹介に終わらせず、侍軍団の村上水軍と技術者軍団の塩飽水軍を対比させ、飽きさせなかった。また、縁の土地の紹介もテンポよく紹介され、テレビ番組ならではの映像、潮流、風景、街並み、各種の収蔵品、今も生きる研究者の思いなどが巧みにちりばめられていたと思います。また、両水軍の対比を横軸とすると、それらの現代とのかかわりを縦軸として立てているのだろうと思われます。生存者がいない史実の報道においては、現代とどう関わりがあるのかを示さないと共感が得られません。単なる遺跡、発見された物の紹介では、歴史的研究の引き写しに過ぎず、報道番組としての意味がありません。そういう点では非常に苦心していると思います。たとえば、香川照之さんが村上水軍の家訓を紹介し、現代のリーダーシップ論を論じていますが、これより水軍を歴史的な存在としてだけでなく、現代人にも通じる存在として感じることができる。また、香川照之さんは自分の目で見て、感じたことを随所で語っていますが、これが番組にテンポをもたせ、筋を通す効果を持たせていると思います。また、日露戦争で活かされた村上水軍の操船術、咸臨丸に活かされた塩飽水軍の造船技術の話も、両水軍が近代日本の礎を築く上で生きていたということを示すものでもあります。番組の最後で縁の施設の紹介があり、入場料、開館時間などを伝えていましたが、ここまで番組を見て、旅情を誘われているタイミングでの紹介で、非常に親切であったと思います。欲を言えば、合戦の様子など、イラストだけでなく、CGをもう少し使えば、さらに解りやすくなっていたのではないかと思います。
・村上水軍は有名ですが、具体的にはあまり知りませんし、塩飽水軍のことは全く知りませんでした。ですから、この二つの水軍が対比され、それぞれ明暗を分けていくという展開は歴史好きの私には非常に興味深いものがありました。海を領土として捉えるという考え方は新鮮でしたが、番組を見て非常に納得できるものがありました。また、なぜ香川照之さんがナビゲーターなのだろうと思っていましたが、コメントを聴くと、歴史ファンの耳にも、説得力があり、なるほどと思いました。小豆島の海底の話は、何が発見されるのか、何があるのかと期待しましたが、結果的には石の紹介で終わってしまい、どういう意図で取り上げられたのかよくわからないままに終わりました。最後に「水軍紀行」として、取り上げられた場所などの情報がまとめて紹介されましたが、歴史ファンに優しく、ありがたい配慮だったと思います。
・私は歴史に興味があるわけではないので、この番組は自分から進んで見るような番組ではありません。しかし、1時間弱という、まずまず長時間の番組でしたが、すんなり見ることができました。非常に印象に残ったのは、海と島の美しさで、私が最初に愛媛に来た時に島並みの美しさに感動しましたが、番組内の映像でも同じことを感じました。香川照之さんのナビゲートは、自分で実際に興味を持ち、深く理解した上で取材に同行していることが伝わってきて非常に印象的でした。いろいろな博物館、資料館が紹介され、それらは最近、子供の遠足などでも頻繁に使われるようになっている場所でもありますが、必ずしも歴史番組ということではなく、ある意味では四国の名所案内という見方もできると思いました。身近なものにはなかなか興味を持たないものですが、この番組を見た人が、もっと両水軍、瀬戸内海、小豆島などに興味を持つようになるきっかけになればいいと思います。これだけふんだんに土地や施設が紹介されるので、最後のインフォメーションのコーナーは非常にありがたいと思いました。
・この番組は「海賊」を取り上げているわけですが、「海賊」というものについて普段考えることはありません。まず、そこに興味を持ちました。そして、普通の海賊のイメージ、つまり、何か船を襲って物を略奪するというものとは違う。なるほど、水路の案内をして通行料を取ったり、難所の通行の手助けをして対価を得たりしていたのかということがわかりました。また、海賊がなぜなくなり、どうなっていったのかもわかった。ただ、村上水軍が海流が早く複雑なところで通行料を取っていたということはわかったのですが、どうしてもこの難しいところを通らなければならない理由というのが何かあったのか、その部分の説明があれば非常に納得できたと思います。番組は、そのあと塩飽水軍の話に移るわけですが、塩飽水軍のことは初めて知りました。村上水軍とは異なり、時代の流れに乗って天下人に仕えていったということなのですが、途中から塩飽水軍の話に切り替わる意味がよくわからなかった。最初に、両水軍を対比をするということや、村上水軍を紹介し、次に塩飽水軍を紹介するというガイドマップを説明しておけば、わかりやすくてよかったのではないかと思います。香川照之さんのコメントは確かにいいコメントがたくさんありました。大山祇神社の武具を見たときの感激も、実際にドラマなどで身に付けたりしたことのある人ならではの感動が伝わってきました。最後に村上水軍と塩飽水軍を対比しているまとめは解りやすかったと思います。
・現在は「海賊」がいないので、「海賊」とは何かということになるわけですが、難所を案内したり、通行料を取ったり、合戦のときに武勲を立てることを生業にしていることで概念がはっきりしたということはまずよかった。また、、村上水軍に比べて知名度の劣る塩飽水軍ですが、塩飽水軍の地元局が幹事だっせいか、バランスよく紹介されており、対比もよく効いていた。利害打算ではなく信念に従って進む道を決めていた村上水軍に対し、時の天下人につき従っていった塩飽水軍。しかし、村上水軍は武力では滅ぼされず、海賊禁止令という法で滅ぼされた。他方、塩飽水軍は柔軟に時代に対応し、幕末まで人材を残していったという意味ではしたたかで、たくましい。香川照之さんのコメントは素晴らしかったと思いますが、唯一最後のコメントは、支離滅裂というか、言葉がいろいろちりばめられているもののまとまりがなく、彼らしくないコメントだったと思います。
・4社共同制作だけあって、映像、音楽ともに素晴らしく、内容的にもレベルが高く、両水軍の歴史を学ぶことができました。塩飽水軍のことは初めて知りましたが、塩飽水軍の末裔がまだ生きているというところに非常に長い歴史のロマンを感じさせます。番組の構成として村上水軍と塩飽水軍を対比させているところが非常にわかりやすかったと思います。
・風景が非常に美しく、海、動物、人のバランスが素晴らしくよかったと思います。番組の最初の要約、ダイジェストの部分も素晴らしく、わくわくしながら番組に引き込まれていきました。放送時間が土曜の午後だったのですが、この時間帯だと歴史好きの人が見られるか疑問であり、平日の22時台でも十分持ちこたえる重量感と見ごたえのある番組でした。CM入りのところで「CMのあと…」というガイダンスが出ていましたが、これは頭を整理する上で非常に有効だったと思います。ナビゲーターの香川照之さんを起用する苦労や。短時日でロケを済ませる苦労などが偲ばれる番組でした。
・とてもいい番組だったと思います。ローカル制作番組で、今まで水面が映ると、なぜか船酔いしそうな撮り方ばかりだったのですが、今回はそういうこともなく、とても美しいと思いました。私は歴史に詳しくありませんが、非常にわかりやすかったと思います。話が少し脇道に逸れるようですが、県民性というものはこのころから始まっているのかなと思いました。よく、香川の人は状況把握が上手、状況を見ながら事を進めるので失敗はあまりない。愛媛の人はその時が良ければよく、深く考えない、だから後から失敗していることに気がついたり、取り残されたりしてしまうといいますが、その通りだと思います。たとえば、塩飽水軍の流れで讃岐彫りが残っていますが、村上水軍の流れで何が残っているでしょうか。割賦販売の発祥の地が今治だと思い出しました。全体としては、ナレーションも音楽もよく、細かなところまで心配りができていて、最後の案内も大変丁寧に作られていると思いました。
・両水軍の特徴を対比するという番組の組み立てはよく理解できました。ただ、瀬戸内海には他にも海賊がいたのではないかという気がしますので、他の海賊がいたとすれば、それはどのようなものだったのか気になりました。また、この番組が愛媛、香川以外のところでも視聴されるとすれば、他の土地でこの番組の面白さが理解できるのか気になりました。また、瀬戸内海の海流の研究をしている末永教授と香川照之さんの交流についても、もう少し触れられていると面白かったように思います。
・今回のテーマを選んだ理由は、2014年が瀬戸内海国立公園指定80周年であったこと、「村上海賊の娘」が2014年の本屋大賞となり、村上水軍博物館の入館者数が昨年のゴールデンウィークなどで例年の2倍以上になったというようなことがあり、ちょうど放送エリアが瀬戸内海の四県であるということもあり、興味を持ってもらえるのではないかということがあります。村上水軍は知名度が高いのですが、塩飽水軍については、地元香川でも名前を知っている程度という人が多く、どうすれば知ってもらえるか。対比すれば興味を持ってもらえるのではないかと思い、武の村上水軍と技の塩飽水軍とという形にしました。香川照之さんは人気俳優であるというだけでなく、ご本人も歴史に興味があって、番組中のコメントもこちらで方向性を示してはいますが、構成台本も自分で読んで理解された上で、基本的にご自身で考えられ、コメントは基本的に自分の言葉で話しておられます。人気のある方ですが、どうしてもお願いしたかったので、二ヶ月間粘って交渉しましたところ、こちらの熱意が通じて、ドラマを一本断っていただくなど、ようやく出演を了承してもらえました。ロケは8月後半の3日間、この3日間しかないという3日間で、初日に広島入りし、大三島、大島、2日目に本島、小豆島、3日目に香川大学を訪ねるという強行スケジュールで、2日目には雨も降りましたが、逆に晴れのカットばかりにならずよかったようにも思います。最後のコメントが支離滅裂という指摘がありましたが、あの部分は実は撮影の途中で録ったもので全編の仕上がりを待たずしてしゃべったコメントだったために、あそこだけは、あのような中途半端なものになってしまい、残念です。小豆島の海底の映像について蛇足だったのではないかとご意見がありましたが、あの部分は実は8月に調査が始まっていて、もしかすると何か見つかるかもしれないと思っていたのですが、結果的に特に関係あるものは見つからなかったということがあります。しかし、大阪城築城に使う石を運んでいた船が難破し、石が実際に海底に沈んでいるということで、なかなか見られない海中の風景と史実を結びつける興味深い映像なので取り上げました。CGを活用すればよかったのでないかというご指摘については、確かに予算との関係があり、あのようなものになりました。香川大学の末永教授と香川照之さんの交流につきましては、末永教授は実はボクシングの試合の映像コレクターとして有名であるということがあり、プロが対戦相手の研究のために試合の映像について末永教授のところに依頼に来るほどの方なのです。香川照之さんも実はボクシングが好きであるため、20年来のお付き合いがあるそうです。全体として、歴史に詳しい方にとっては少し物足りないかもしれませんが、歴史に詳しくなくても面白く見られるような番組にしたつもりです。