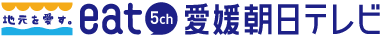第202回放送番組審議会議事録
開催日時:平成27年4月24日(金)15時00分
課題番組:BS朝日「にほん風景物語」2時間SP
文豪 夏目漱石 名作の舞台 名作「坊っちゃん」の故郷 松山・道後温泉 / 「草枕」の舞台 熊本・小天(おあま)
2015年3月10日(火) 21時00分~22時54分(114分)放送
制作・著作 BS朝日・愛媛朝日テレビ・熊本朝日放送
※主として当社関係部分(前半)を審議対象
・私のような年代にとって、非常に落ち着いた、癒される番組でした。『坊っちゃん』愛媛 松山のことを中心にということですが、知らないことも多く出ていたこともあり、熊本の方が非常に良く感じました。特に、高橋源一郎さんの漱石に対する分析が面白かった。俳句をたくさん作ったけれど、小説家になる以前の漱石という見方も面白かったし、俳句では、とても収容しきれなくなったので、小説家になったのではないかという分析も面白かったと思います。『坊っちゃん』は、今、愛媛新聞にも掲載されているので、読み返してもいますけど。松山の人間ですから、散々読んだこともあるし、『坊っちゃん』に関する論評も山程あります。例の喫茶店で“坊っちゃん会”の人もいろいろ言っていましたけど、『坊っちゃん』の描写は非常に厳しい松山批判というか、こき下ろされていますが、最近、私は漱石ほどの文豪が単純に、田舎を、松山人を馬鹿にして、批判だけをしているのかなというふうに、感じるようになりました。というのは、「坊っちゃん」は江戸っ子、「山嵐」は会津ということで、「赤シャツ」、「野だいこ」とか校長の「タヌキ」が批判されていますが、漱石の時代背景というのか、日本が急速に近代化している時代、文明開化という時代に対して、江戸っ子の漱石が少し抵抗を感じていたというか、疑問を挟んでいたのではないかと。近代化という言葉、綺麗な言葉ですが、もうひとつ詳しく見ると、「赤シャツ」や「野だいこ」という狡い人間というか、狡猾な人間が幅を利かせる時代じゃないかと。「坊っちゃん」のように一本気とか、「山嵐」とかいう人が割を食う時代に対する批判を漱石は言いたかったのではないかというように、少し感じました。『坊っちゃん』には、明治維新のことを“御瓦解”と書いています。瓦解に“御”という丁寧語を付けて。要するに、江戸時代が壊された。極端に言うと、良い時代が壊された。明治維新を“御一新”と、美化するだけではなくて、それに対する批判というか、漱石は洞察の深い人、大文豪ですから、そういうことが言いたかったような気がします。その中に、松山人の批判が含まれているような気もしました。そういう意味では、島田先生の分析は高橋さんに比べると、少し何か物足りないような、通り一遍のことだったように思いました。
・2時間のBS番組ということで、スピードがゆっくりで贅沢な番組だと思いました。熊本の方の映像がすごく綺麗で、見ていると、熊本に旅行で行き、散歩をしたくなるような感じがしたので、きっと他の地域の人は松山のところを見ると、松山に行きたくなると思いました。『坊っちゃん』は観光小説でもあると言っていましたが、その通り、『坊っちゃん』を追うことによって、観光で松山に来て下さいというような番組になっていたと思います。松山城からの映像などが非常に綺麗でした。坊っちゃん列車に乗ったり、道後温泉に入ったりというところが観光に近い番組かと思ったのですが、道後に漱石が泊まった宿がある訳ではないので、宿とか料理は出ていないというところで、普通の観光番組との違いを感じました。松山は熊本と違って、漱石は熊本に4年数か月居ましたが、松山には1年しか、居なかったということで、熊本に比べたら、多分、素材がすごく少なかったと思います。そこは大変だと思うのですが、当時、漱石が何を考えていたのか、とか、新しい解釈とか独自の視点とか、それは面白いなというものと、それがより現代に、例えば、今、漱石が居たら、どういうふうに感じるだろうとか、そういったような視点が島田さんか、ナレーションを通してかであったら、もっと面白いなと思いました。
・前半だけが課題とは知らなかったので、最後まで通して、比較しながら見たことを最初にお話ししておきます。『坊っちゃん』は青春小説でもあり、島田さんのいうように観光小説でもある。一方で『草枕』は淡々と主人公の思索を綴るという二つの小説の性格は異なりますが、番組を通じて、教員として過ごした松山・熊本、共に、お城や路面電車、温泉、蜜柑、俳句など、共通する点が多いことを興味深く拝見しました。島田雅彦さんが松山を漱石の出発点と言い、高橋源一郎さんが熊本を小説家として目覚めた地と表現しているのも、番組サブタイトルの“漱石の原点を求めて”に通じる共通性のようなものを感じました。放送はBS朝日なので、全国の視聴者に広く受け入れられる番組作りを意識されたと思います。ただ、そのためか、番組前半で島田さんが訪ね歩く、道後温泉、松山城、松山鮓などは、愛媛県ならば、よく知っている場所、エピソードが多く、若干、新鮮さに欠けていたのではないかと思いました。他県に住む人たち向けの観光ガイドの色合いが濃かったのではないかと思いました。また、島田さんならではの辛口で尖がった発言を期待していましたが、ソフトな発言が多くて、肩スカシをくらったような気もしました。島田さんの個性が十分に生かし切れていなかったように思います。ただ、島田さんが『坊っちゃん』について、「よそ者の意地悪な目で、地方の人々を活写している。松山でのことを必ずしも、良くは書かれていない。」と指摘しているのは、さすがに島田さんらしい視点、見方だなと感心しました。少し、外れますけれど、私はこの番組を見るまでは、[よもだ]という方言を知りませんでした。広辞苑を引くと、「(愛媛県)いい加減なこと。または、そのような人。」とちゃんと載っていました。さらに、「亡くなった天野祐吉さんが“よもだの精神”という言葉をよく使っていたし、松山市のキャッチフレーズ“いい加減”の由来でもある。」ということも教えてもらいました。番組後半の『草枕』は地元の人すら漱石が訪れていたことを忘れていた峠越えが舞台なので、少なくとも私の知らなかったエピソードが多く、発見が有りました。『草枕』の中身自体が美術論を展開するような内容なので、視聴者を惹き付けるのは難しかったと思います。それに対して番組では、高橋さんが実際に山道を歩きながら、想いを語ったり、高橋さん自身が『草枕』の道を映像で俳句的に表現することを試みたり、漱石が感じていただろう熊本を切り取る映像を撮影したりするなど、出来るだけ、飽きさせないような演出、高橋さんからの言葉を引き出すような演出というものを感じました。番組が2時間スペシャルと長かったので、最後に番組で訪れた場所を紹介することは、番組内容を振り返りながら、見る人間にとっては整理するのに役立ちましたし、視聴者に親切だったと思います。
・「にほん風景物語」シリーズの良さというのは、やはり作家で、島田雅彦さん、高橋源一郎さん、山本一力さんがいらっしゃって、言葉の蓄積がある作家から綺麗な日本語であったり、イメージのある言葉が出て来る、そこがこのシリーズの魅力だなというのを今回、見せていただいても思いました。例えば、青森の太宰治だと、太宰治という人の一生を知っていると何か辛い思いがしますけど、今回のように、道後温泉を夏目漱石という、割と松山のことをシニカルに捉えているけれども、ウェットな文体の人ではないだけに愛媛と熊本を繋ぐ意味で、私は面白いなと思って見ました。驚いたのは、ナレーションの声が松坂慶子ソックリだったことです。後で、字幕でナレーションはテレビ朝日の村上祐子アナウンサーと分かりましたが、このナレーションはすごくいいと思いました。もうひとつ、さっきも、[よもだ]という言葉がありましたけど、私は松山生まれで、松山で育っていますので、「また、よもだなこと言うて。」というようなユーモアという意味は分かります。ただ、使い方によってはとても厳しい言葉、違った意味に捉えられて、今で言う“ヤバイ”と一緒だと思います。昔、“ヤバイ”と言うと、本当にいい意味ではありませんでした。今、「ヤバーイ」、「ヤバイ、美味しい」とかは美味し過ぎることを“ヤバイ”で表現したりします。言葉の文化の変化のような説明があると、良かったかなと思ったりはしました。私自身の要望としては、まず、漱石の『坊っちゃん』の中に書いてある言葉を出したりする時に、同じトーンでバックに音楽が流れていましたが、一気にあそこで、音楽を消して、男性ナレーターがその言葉を読んで、また、音楽が入るという風に、言葉のところだけ、不意に音楽が途切れることで、言葉が大きく浮かび上がって感じるような効果を試されることです。ずっと、音楽がバックに流れているということで、何となく単調な感じが、中盤からし始めてきました。ずっとBGMが流れていると単調になるから、そこはポンとBGMを切って、言葉を浮かすというような手法もありかなと、素人目に思いました。それから、CMです。あれだけ、風景とか、人とかがあると、CMと混同してしまいます。例えば、番組をフェイドアウトして、一遍切れたようにして、CMをインするみたいな。フェイドアウトしてCMをカットインするみたいに、“番組の切れ目は此処ですよ!”と知らせてから、ポン!とCMを入れるとかやっていくような手法はないのかなと思いました。あとは、BS自体のことですけど、BSの知名度は、どうしたら上がるだろうということです。これだけ、クォリティのある番組で、見た人は多分、松山を、愛媛を訪ねてみたくなる感じなのですけど、やはり、地上波でないBSに対する知名度は、まだ、とても低いというのがあります。歴史とかこういったドキュメンタリーというのは、2時間ぐらいあり、腰を落ち着けた丁寧なつくりの番組がBSにはあるんだということをもう少し、伝えていって欲しいなと思いました。
・今回、初めてのBSの番審ということですけども、出足の映像がやはりすごく綺麗ですね。音楽も素敵。また、最初はナレーションとかは入っていないですけど、引き込まれていくものがございました。でも、やはり見ていますと夏目漱石、『坊っちゃん』、道後温泉、松山城と、どの番組も実は似たような傾向がありまして、一般のローカルで流れるよりは、ものすごく綺麗ですが、ものすごく硬いですね。たくさんの取材場所もありましたが、2時間がとても長く感じました。最初から最後まで、熊本版も見ましたけれど、漱石の文学『坊っちゃん』を追っていく上では、とても見ごたえがあります。多分、この火曜日の9時くらいからの設定ということで、見はじめた方は、多分、2時間集中されて見て、松山に、また、熊本にと、行ってみたいな思われること、この上ないですけども、私はこの番組を一度、最初に見ましたところ、どうしても、何を書いていいのか分からない。そこで、子供たち、主人にコメントをひと言もらえないかと思い、家にいる時間帯の9時、10時から、この番組をつけておきましたが、「ちょっとこの時間帯に見るには…。」と言われ、コメントはもらえませんでした。また、漱石が松山を批判していますので、島田さんも、厳しくその通りのことを伝えていらっしゃいましたが、そのことを、松山住人の私には、あまり心地良くはとれなくて、あまり松山批判をすると、皆様が松山に来て下さらないのではないかとそんな風に、逆に捉えてしまい、松山を大好きな私にとっては、寂しく感じました。松山には、坊っちゃん列車に、うつぼ屋さん、坊っちゃん団子と、ありますけど、熊本でも、そういった風に、漱石の『草枕』の関係で売り出しているのでしょうか。松山をすごく観光的な目で見ていたのですけど、熊本は散歩道や美しい映像があり、ちょっと見てみたいなというものがたくさんあったのですが、作り手が違うせいか、そんなにアピールしていないような気がしました。最後のインフォメーションは、映像と共に、最近は名前と電話番号と出ていましたので、分かりやすくて良いと思いました。
・私が感じたのは、愛媛から熊本に移行する時、スムーズに流れて、そして、愛媛で撮られた部分、熊本で撮られた部分がぜんぜん違った着眼点ですごく良かったと思います。いつも音楽のことを言うのですが、本当に上品でとてもいい仕上がりの番組だと思います。ちょっと偉そうな言い方ですけど、どなたがお作りになられたのだろうとか、制作者にお会いしたいと思うくらい、とても良かったと思います。こういう番組では、食べることがいっぱい出て来る映像が良くありますが、そういうものが無い、そして、文学的な視点で、観光地、例えば、道後温泉を捉えるところも、すごく良かった。また、三津浜婦人会の方たちが松山のちらし寿司をつくられているあのシーンはとても、和やかで良かったと思います。岡山のちらし寿司、「祭りずし」はとても有名で、いろいろな処にありますけど、松山のちらし寿司は、あまり脚光を浴びていないので、これから、あれをきっかけにされたらいいのではないかと思いました。これは余分な話ですけど、[よもだ]は松山弁ではなくて、愛媛県内どこでも使う言葉で、田舎に行くと、よく使っております。これは難しく強い言葉ではなくて、ユーモアを踏まえた、例えば、お酒を飲んでいる処で、討論みたいになった時に、「そんなこと言われん。よもだなんて言われん。」という感じの柔らかい、ソフトな表現の仕方というのが、ほとんどだと思います。[よもだ]はよく使っていますが、[~ぞなもし。]は、今、全く死語になっています。ですから、あれを方言のひとつとして捉えられるマスコミの方も、よくいらっしゃいますけれど、あれはちょっと違うのではないかなと。[よもだ]と[~ぞなもし。]というのは、違った秤に乗っているのではないかなと愛媛県民として申し上げます。とてもいい番組でした。ピアノの音色がすごく自然で、風景とか、言っている映像とか、番組自体をすごく高度なものに感じられました。すごくいい番組だと思いました。
・小説家二人、島田雅彦さんと高橋源一郎さん、二人とも個性的で、現代のなかでは、注目されようと言うか、自らいろいろ新しい試みをされている小説家の方なので、その新しい視点で漱石の松山に居た時と熊本をもう少し分析するのかなと思いましたが、そこにはあまり深くは入って行かなかったような気もします。文学の授業でもないので、細かく言っても仕方ないと思うのですが、やはり、通り一遍の評価で済ませるのではなく、このお二人を使ったのだったら、もう少し現代の視点で切り込むのがあってもいいのかなという気もしました。そこは少し物足りなかったのですが、難しいところだと思いますけど、番組の流れとしては、非常にスムーズ、見やすかったと私は思います。『坊っちゃん』については、観光小説というパターンで利用しているのは松山市というか、むしろ、松山市と役所が観光小説として、利用していると思いますけども、深く読んでいくと、やはり、そうではないということが分かってしまうので、そこをこれからどうしていくのかなというのを松山市に聞いてみたいと思いました。
※「放送番組の種別ごとの放送時間」の報告
2014年10月~2015年3月の各月第3週に放送した番組の「種別ごとの放送時間」について報告があった。