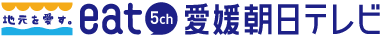第191回放送番組審議会議事録
開催日時:平成26年3月24日(月)午後3時00分
課題番組:3/14(金)に発生した伊予灘地震の報道について
今回の地震は、揺れは大きかったが、その割には被害が少なく、愛媛大学では今日、卒業式だったが、もし被害が大きければ卒業式どころではなかったのではないかと思った。今、思い出すと、横揺れが来て、大きい地震だなと思ったときには、テレビのリモコンに手が伸びたので、何かあればまずテレビを見るという発想は私の中にできているのだなと思った。あの地震でメディアはどのような対応をしたのかが気になっていたが、本日の資料を見て、とても安心した。メディアが、実際にこういう素早い対応をするということが心の平安につながり、ひいては落ち着いて対応するという防災意識にもつながると思う。また、地震のあと数日間は余震があるかもしれないという心配があったが、そういう心配に対してもメディアが心の支えになっていたと思う。地震の際には、原発情報、余震、津波、自治体の災害対策本部の状況、交通情報などを確実に流していただきたい。また、こういう地震があると、防災意識を高める意図でいろいろな情報が流されると思うが、あまり煽りすぎず、日常生活の中で混乱なく災害に備えられるようなバランス感覚のある番組作りをしていただきたい。
地震のときは、やはり津波が一番恐ろしい。今回の地震報道では、「津波のおそれなし」という文字が概ね常時出ていたが、ときどき消えることがあった。視聴者はいつ番組を見始めるかわからないので、不安を早く解消するためにも、あの文字スーパーは常に出しておいて欲しい。また、EATは、地震のあとのローカルニュース入りは遅かったものの、ローカルニュースになったときには、既に空港や伊方原発、高速道路の映像などが次々に出され、大変驚いた。ここまでのスピード感をもってやるには日常のトレーニングやマニュアル作りの積み重ねがあるのだと思い、とても安心感を持った。大澤アナウンサーは寝起きだったのか眼が充血していたが、落ち着いていて、よかった。
テロップについては、最初に「西予市で震度5強」とだけ書くと、ピンポイントの情報しか入らないため、不安をあおるのではないか。私の会社の社員は南予地区に住んでいる者もいるので、私の会社でも災害対策本部を立ち上げたが、「3時現在で被害情報なし」という報道を聞いて非常に安心した。総じて、文字テロップは視覚に訴える力が強く、充実していた。ただ、「〇時○分で通行止め」という道路交通情報があったが、「〇時○分に通行止め」という書き方にすると、「で」と「に」の違いだが、印象がずいぶんやわらぐ。そのあたりの細かな配慮もお願いしたい。場所的に久万高原町と松山市内の情報しか出なかったのも気になった。地震というと、やはり、しまなみ海道はどうだろう、とか、液状化のおそれが指摘されている西条市はどうだろう、という心配もある。また、ガソリンスタンドについての情報も一店舗出ていたが、一店舗だけではかえって混乱を招くことも考えられる。さらに、火災や土砂崩れについても不安があるが、ニュースの中では触れられていなかった。加えて、大きな地震があると、本震か余震かが気になるが、そのあたりがわかると更によかったのではないか。今後、日常的に防災情報を流すと災害時に頼りにされる局になるのではないか。
今回の地震は、発生時刻が幸いして、落ち着いて行動できた。テレビを見たが、どこの局も同じような情報を繰り返し流していた。このような災害のときには、誰がいつ見ても分かりやすいように、重要な情報を繰り返して出すということも、確かに必要だ。しかし、さらに大災害になったときには、むしろ各社が協力して取材できないか。各社の取材陣が争って取材することにより、結果として早く情報が集まるということもあるかも知れないが、情報を共有化することはできないのか。また、大災害のときは、各社の流す情報の影響は非常に大きいと思うが、どのような情報を流すのかを判断するのは誰なのか、そのあたりも気になった。
情報として、ライブ中継と録画映像が出てくるが、「生」なのか「録画」なのかを、もっと誰にでもはっきりわかる形で示すべきだ。「録画」なら、いつごろの映像なのか、それとも「生」なのか、はっきりさせるべきだ。また、更に大災害になると、停電になりテレビが使えないということもありうる。そういうときには、ラジオやワンセグで情報を得るということになるが、それに備えて、映像がなくても分かる伝え方を心がけていただきたい。今回はいわば一過性の地震だったが、今後より大きな災害が発生したときのために、今回の経験を活かしていただきたい。
私は今までこのような大きな地震に遭ったことがなく、そもそもテレビを見るということが思いつかなかった。地震後、しばらくして公民館から「ラジオ、テレビの情報に注意してください」という放送があり、そのときに初めてテレビを見るということに思い至った。こういう人も少なからずいるのではないか。EATは総じてスピーディーに情報が流れていて、ガソリンスタンドの情報などもありがたいと思った。津波や伊方原発の情報は常時出しておくべきではないか、とか、アナウンサーの話している内容と映像の内容がずれていることがあって視聴覚障害者に不親切ではないかというような点も気づいたが、それは後から言えることであって、災害時にはやむを得ないのかもしれない。しかし、総じてテレビの情報はわかりやすかった。
EATは立ち上がりが早く、映像も充実していた。今回の地震では発生当初から震度以外の情報が入らず、被害の状況など詳細がわからなかったが、そういう中でここまで早い対応ができたのは素晴らしい。特に、早い段階で各所にアナウンサーが出ており、行政よりも、明らかに早く情報をつかんでいた部分もあった。各種のライフライン情報も早い段階で出ていた。最初に戸谷アナウンサーが出て、情報が限られている中をよく繋いでいたが、大澤アナウンサーに交代して、安定感が増した。視覚的な情報伝達は確実性が高いので、L字のスタートがもっと早ければ、更によかったのではないか
地震時は自宅がさほど揺れなかったので、たいしたことはないと思っていたが、ほどなく電話がどんどんかかってきたため、テレビを見ることにした。いろいろ見てみたが、EATが一番見やすかったのではないか。限られた情報の中で、あれだけしゃべることができるというのはさすがだ。今後、防災をテーマにしたミニ番組を企画するというのもいいのではないか。
地震時には東京にいたが、愛媛の様子をテレビで知ることができず、もどかしい思いをした。今は、インターネットも普及しており、東日本大震災のときには、ユーチューブやニコニコ動画でも地上波テレビが送信された。あれは特例だったのだと思うが、東京をはじめ、各地にいろいろな地方の出身者がおり、インターネットを利用して地元の映像を見ることができるようにならないものか。ラジオはインターネットで聴くことができるようになっているし、テレビもインターネットでの送信を検討すべきではないか。また、ツイッターなどの活用も考えてよい。なるべく補完手段を増やすことを考えるべきではないか