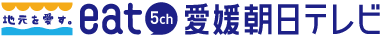第192回放送番組審議会議事録
開催日時:平成26年4月24日(木)15時00分開会
課題番組:「ふるさとCM大賞えひめ'14」
・今回の「ふるさとCM大賞」は9回目ですが、愛媛朝日テレビのウェブサイトで過去の作品を視聴することができます。これを見ると作品のレベルも毎年向上していることがよくわかります。コンピューターの動作原理の基礎を考案したノイマン・ヤーノシュはハンガリーのブダペストの人ですが、ブダペストはドナウ川の周囲に発展した都市で、ブダペスト出身の著名人としては他に「水爆の父」といわれるエドワード・テラーもいます。マッチを発明したイリーニもハンガリー人だそうです。愛媛は川ではなく瀬戸内海をはさんで他の地域文化と交流をしてきたわけですが、このように少し離れた異文化と交流するところには、よいもの、おもしろいものが育つ可能性があるように思います。
・この番組を見るのは前回に続き二回目です。たむけんさんのノリのよさを見て、今年もCM大賞を見たという実感がわきました。今年はフードコーナーも設けたとのことで、さぞ盛り上がったのではないかと思います。出品されているCMは内容的に昨年と重複しているものもあり、出品者も生徒から自治体職員まで様々、レベルもいろいろでしたが、全体としてレベルはアップしていたと思います。他県にも流れるということですので、とてもよいPRになると思います。キーワードで分類されていましたが、内容的に、何をPRしたいのかよくわからないものもありました。しかし、このように地元住民とテレビ局が協力することは非常に有益なことではないかと思います。
・この番組は毎回見ています。確かにレベルアップしていると思います。プロ並みのレベルのものもあれば、非常に手間のかかっているものもある。25作品が審査対象となったわけですが、これをすべて見せるという制約の中で、90分という長時間番組のメリハリをどう付けるのか。そのための工夫として、たむけんさんの起用、キーワードによる分類、メイキングや背景の紹介などがあったわけですが、更にメリハリを付けるとしたらどうするか。このためには、例えば、他局の番組ですが「欽ちゃんの仮装大賞」のようなスピード感、あるいは、審査員の審査点数を各作品に対して出すなど、違ったエネルギー源がないか。同様の番組のある他地区ではそのような工夫はないのか。そういう新たなメリハリを付ける工夫があれば、より面白くなるのではないかと思います。
・個人的には、宇和島市のメイキング映像が心に響きました。ふるさとのPRというよりは、「消えゆくふるさと」のPRともいえるものでしたが、それが逆にこの番組の趣旨を引き立てている。また、受賞作の発表のところで、自分たちの名前が呼ばれて、一瞬固まっている人たちがいましたが、これが逆にリアルでよかった。今後はアマチュアとプロが連携して作るというのが地方でのコンテンツ制作のポイントではないかと思いますが、ラストシーンで全員がステージに上がったのは、それを象徴しているように思いました。
・この番組は初めてのときからずっと見ていますが、次がちょうど10回目となり、一つの節目となります。マンネリ化をいかに防ぐか、新たなネタをどう探すかということには苦労しているのではないかと思いますが、番組の軸になっている8つのテーマはどう決めたのでしょうか。予めテーマを決めて選ばせたのか、作品が集まってから決めたのか教えていただければと思います。テーマの中には「アンダー18」というのがあり、これが出てきたときに、とっさにどういう意味なのかわからなかった。後で「18歳以下」ということがわかったのですが、わからないまま終わっている人もいるかもしれず、こういうところは誰でもわかるようにしていただきたい。作品の制作手法には新たなものもあり、工夫も随所に見られましたが、素朴さから離れると逆につまらなくなるということもあり、なかなか難しいところだと感じました。また、ステージではたむけんさんと司会者が出場者をいじったり、出場者などとの掛け合いをしたりして、それが番組の抑揚を生んでいるのですが、関西の言葉の方が愛媛の言葉に近く、関西系のタレントが愛媛のCM大賞には向いているかもしれないなと思いました。このような番組を続けていくのは大変だと思うので、今後どのように工夫していくのか注目したいと思います。少し立ち入った話になりますが、松山市から北条の街づくり協議会と三津の街づくり協議会が出品者として名を連ねていました。実は、松山市は広報委員制度をやめて、街づくり協議会という制度を発足させたのですが、いろいろ混乱していて、現実に街づくり協議会ができているのは、半分ほどの地区だけです。松山市の一地区は独立の一町村ほどの規模のものもあるのですが、その中で街づくり協議会制度がうまく機能して、活発に活動しているところが出品しているのだと思います。
・たむけんさんは2回目の起用で、非常に快調だったと思います。ただ、85分間という長時間番組なので、中だるみ感は否めません。しかし、なんとか持ちこたえている感じです。私は審査員をしたこともあるので、よく分かりましたが、確かにCMの作り方は非常に上手くなった。以前は、とりあえず人が集まって「来てねーっ!」と叫ぶだけというレベルのものが少なくなかったのですが、ずいぶんレベルアップしたものだと思います。番組の途中では、当然、本当のCMも入るわけですが、これと見比べても、ふるさとCMならではの感覚が伝わってきました。次回が10回目ということですが、10回記念というような何かがあるのではないかという期待もある一方で、10回というのが一つのターニングポイントになるかもしれないという気もします。一旦、止めてみて、今後の方向性を考えてみるというのも一つの方法かもしれないと思います。また、今回からは、収録会場の外でフードコーナーを設けたとのことですが、どのような効果があったか知りたいものです。
・この番組は今回初めて見ました。新鮮な気持ちで、この番組を楽しみました。地元のことを知らない人は意外に多いものであり、このような番組を通じて自分の住んでいる地域を再発見するという意義は深いと思います。出演者の世代も幅広く、古くから住んでいる人にも、最近になって移住してきた人にも楽しめる番組になっていると思います。内容的にも、作品の紹介にとどまらず、制作者との掛け合い、制作背景の紹介など厚みがありました。入賞作の一部は、県外にも流れるということですが、県外の人には制作意図がわからないものもあるように思います。メリハリ作りのためにキーワードで作品を分類していることについては、やや無理なものもあったと思います。
・イベントとしてではなく、番組として見たとき、楽しく見られるところと、つくりがいまひとつうまくいっていないところが分かれていたと思います。たむけんさんの前は、桂小枝さんがタレントとして起用されていたのですが、だんだんやる気がなくなっていく感じが見て取れ、たむけんさんになってリフレッシュしたと思っていたのですが、前回に比べるとやや歯切れが悪くなっているようにも思います。次回で10回目とのことですが、正直なところ10回で一区切りではないかと思います。このような番組を作りつづけるというのは、なかなか難しいと思います。ただ、私と縁のある人たちも出演していて、変わらない温かさが伝わってきましたが、そのような温かさを視聴者に届けるには良い番組だとは思います。また、切り口として、県外の人に愛媛県の良さを教えてもらうという観点の作品があり、そういうところは面白かったと思います。この番組が提供しているものは決して悪いものではないし、県外から移住してきた人が愛媛の文化を知るには良い番組かも知れません。ただ、これからも長く続けていくには、何か足りない。そういう気持ちがいたしました。
・CMだけ見ると、意味が解らないものがありました。そういうものは、意味が解らないからこそ、心に残るということもありうると思いますが、説明があると解りやすいし、説明がないと結局意味が解らずじまいということになりかねない。また、こういう番組は、出品作をすべて出すということに一つの意義があるわけですが、そうすると逆に番組を最初から最後まで見るのは大変になるというジレンマがあると思います。
・愛媛は娯楽が少ないので、イベントとして定着すれば、さらに発展の余地があると思います。また、実際に映像作品を作っている審査員については、その人がどのような作品を作ったのか紹介していただくと、イメージが沸きやすいと思います。一つ言い忘れていましたが、作品の中に、非常に画面の荒れていたものがありましたが、あれは出品の時点で荒れていたのなら、明らかに直させた方がいいと思います。