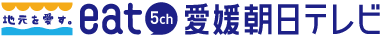第208回放送番組審議会議事録
開催日時:平成27年11月25日15時00分
課題番組:テレメンタリー2015「シリーズ戦後70年(7)空に舞った徒花 ~風船爆弾悲劇の記録~」
2015年8月1日(土)[午前] 6時00分~[午前] 6時30分(30分)放送
・地方局が少ない人数でつくっているのではなく、都会のキー局などが委託して制作した番組のように思った。その理由は風船爆弾が太平洋を横断することを可能にした物理的な条件と技術についてとても分かりやすく説明していたことや、取材がとても丁寧だったこと。当時の少年少女で今もご健在な方やアメリカのオレゴンの悲劇の取材もしっかりしていた。インタビューの中身も非常に分かりやすく、具体的な話も聞き出していたので、今の映像をみるだけで当時どういうことがそこで起きたか、つまり、落下した風船爆弾に子供たちが近寄り爆発してしまったことを、とても具体的にイメージしやすい感じがした。番組のテーマとなった風船爆弾というものを知らならなかったし、唯一アメリカ本土に被害が及んだことであったということも知らなかったが、この番組をみて強く印象に残った。最終的な結論として、「忘れたいけれど、忘れられない記憶として残っている。」と当時、少年だった方が話すところもあって、非常に見応えのあるドキュメントだと思った。
・四国中央市の女性が最初に出てきたが、このように軍事に携わっていたご存命の方を探して取材をするというところから、丁寧さがよく伝わった。オレゴン、カナダ、オタワとまわっていたことも、多くの取材をしていたことが感じられた。今年で戦後70年だが、風船爆弾のことは知らなかった。これはこれからも語り継がなくてはいけないことなので、映像で残したことは素晴らしいことだと思う。また、戦争に詳しい大学教授のお話しは、分かりやすい説明だった。今、炭疽菌とかペストを使ったテロが恐れられているが、戦時中に日本でそれらを使った兵器を考えられていたことを知り大きな脅威を感じた。
・地元の伝統技術があのような戦争兵器に使われていたことを知らなかったので、みていて正直に驚いた。先の大戦が地元の人たちにとってすごく近く感じられたことではないかと思う。また、本当に身近にいる愛媛のおばあさんがそんな大変な苦労をして、親に隠し事をしながら日々を過ごさなくてはいけなかったことを思うと、やはり胸に詰まるものがあった。番組全体としてはどちらかというとロジカルなのだけれど、レポートっぽい感じを受けた。理路整然と淡々と進んでいくのだが、そこにおばあさんやおじいさんの苦悩であるとか、オレゴンの人たちがどういう悲嘆を味わったのかとか、そういうエモーショナルな部分が弱かったかなという感じがして、このドキュメンタリー番組は一体何を伝えたいのか、一貫したものが分かりにくかった。番組資料には、"戦争の異常さとか悲惨さというものに迫る。"とあったが、非常に淡白な感じだったような印象を受けた。そこの部分をもっとグッとフューチャーした内容でも、良かったのではないかと感じた。
・番組の課題を三つ挙げたい。1点目は少しミスリードかなと感じた部分。大学教授が、「風船爆弾は731部隊と関わりがあって、無差別大量(破壊)兵器になる恐れがあった。」と話しをしていた映像に根拠資料みたいなものが一切なく、教授の持論という感じを受けた。根拠資料を示していたら、ミスリード感は薄かった。ドキュメンタリーなので、このコメントの部分はもう少し丁寧にするべきだったと思う。2点目は『空に舞った徒花』のタイトルに疑問が残ったこと。徒花が実を結ばないで咲いた花を連想させる点を考慮すると、風船爆弾を花にたとえて、本当に良かったのかという疑問が残った。風船爆弾も原子爆弾のように、膨大な犠牲者を出していれば、実を結んだ花だったのか。風船爆弾の制作や試射に関わった方たちは膨大な犠牲者を出していれば、実を結んだ花だとおっしゃっただろうか。花という言葉を使うのが非常に残酷なような気がした。当時はどうであれ、視聴者のひとりとして彼らの気持ちを考えるならば、徒花の表現は適切ではなかったと思う。3点目は、最後の場面で風船爆弾と原子爆弾の映像を繋いでいたこと。原子爆弾が実を結んだ花、風船爆弾が実を結ばなかった花、そのふたつを対比するための演出と推察された。原爆の投下は風船爆弾の報復攻撃ではなかったはずだ。硫黄島から続く地上戦の緊迫した状況の中で、当時の複雑な世界情勢と外交が絡み合って、原爆が投下されたことは多くの人が知っている。風船爆弾と原子爆弾の映像が並ぶことは適切ではないと思う。また、番組の最後を締めくくるナレーションの「風船爆弾は劣勢を覆すことなく、時代の徒花となって敵国の空に散っていった。」では時系列に無理があり、この番組のまとめとしては十分ではないと思う。むしろ、風船爆弾の元試射部隊の方が70年前、風船爆弾の作業をした跡地を訪ねて、発射台の痕跡もない場所でつぶやいた言葉、「忘れない。忘れたいけど、忘れられない。本当にむなしいことだったと思いますよ。」が一番心に刺さるコメントだったので、このシーンとコメントで終わることがドキュメンタリーとしては一番自然に受け入れたのではないかという思いが残った。
・風船爆弾のことについて聞いたことがあるので知っていたが、こんなに詳しいことは知らなかった。個人的には、物量でアメリカに全く劣っていた日本が、劣勢のなかでこの風船爆弾で、勝てないけれども一矢でも報いたいとしたことだったと思う。そういうことから、『無差別大量破壊兵器』という表現には、違和感を覚えた。先程、根拠がないという意見もあったが、確かに風船爆弾で細菌を送ったとしても、戦況を覆すこともできるはずもない。戦前の日本とか日本軍のことを全てネガティブに捉えようとする気持ちは分かるが、それにしても、少し非科学的過ぎる感じを受けた。そういう意味で戦時中の悲劇というか、その一断面を表した番組、ドキュメンタリーとして受けとめた。『徒花』という表現もどうかと思う。徒花というのは比較的何か相当の成果があったけれど、それは虚しいものであったというイメージなのだが、成果は全然なかった。最初の女性の方から最後の元少年兵の方の印象を聞きながら、心痛む思いがした。本当にささやかな、当時の日本人として必死でやったけなげな抵抗だったという気がした。戦後70年、どうしても戦争否定、戦前の日本否定という言論空間なので、微に入り細にわたってまで否定したがる気持ちは分かるが、もう少し庶民レベルでの健気さであった部分も表現して欲しかった。
・風船爆弾の報道は多数あるが、今回の番組のように、実態を深く掘り下げるというか、かつての女学生だけではなく、元試射部隊の隊員、それからアメリカで犠牲となった人、そうした人たちの証言と過去の映像を織り交ぜながら、これだけまとまって風船爆弾を捉えた報道というのは貴重なものだと思う。勤労動員の元女学生が親にも言えなかった軍事機密で孤独だった、その一方で、犠牲を受けた米国人の町もまた、軍隊によそに漏らすなと報道管制が敷かれた。戦争はいざ、突入すると、敵味方を問わずものを言えないような状況をつくりだしていく。そういう部分でいろいろな方の証言がひとつに結びつき、さらに、その元試射部隊の隊員が、「忘れたい。忘れたいけど、忘れられない。」と言った言葉が重なって、胸に突き刺さってきた。アメリカ本土、唯一の犠牲者が風船爆弾によるものだということを知らなかったので、あのような小さな爆弾が、実は、アメリカ人にも犠牲を出した悲劇として語り継がれているということを紹介したことは良かったと思う。もっと人間的にというようなご意見もあったが、こういう問題は、抑制した形で冷静につくっていった方が良いと思う。ナレーターの抑制の効いた口調は番組に落ち着いた雰囲気を与えていた。何人かの方からご意見があったが、最初、『徒花』と聞いたとき、やはり違和感を持った。『無差別大量破壊兵器』の破壊という表現についても疑問に思った。
・若い方が若い感性で制作したことが、とてもよく分かった。だいぶ前のことだが、四国中央市で、当時女学生は風船爆弾を作っていて、家族にも風船爆弾を作っていたことを言えなかったという話しを聞いたことがある。その時は、家族に言えないことで女学生たちにどれだけのストレスがかかってきたのか、それも若い純粋な年頃ではとても辛かったのではないかと、涙が出たことを今も憶えている。地元をテーマにして細やかな取材、なおかつ、専門的な捉え方をしていて、番組づくりとしてはとても良かったと思う。だが、『徒花』というのは、何に対しての何が徒花なのか。せっかく知っているから、この言葉を使おうと安易に使われたのではないか。もう少し違った、的確な表現があったのではないかなと思った。こういう戦争や重いものを題材とした番組にタイトルを付ける時には、若い方たちだけで相談して決めてしまうのではなく、ご年配の方からも情報収集をして決定されると良いと思う。
・ドキュメンタリーをつくる上で、根拠資料は一番気になるところだとは思う。今はおじいさん、おばあさんになってしまっているので、映像からみた印象は決して少年少女ではないが、当時は10代半ばの少年少女だった彼らがそういう戦争兵器をつくる、或いは戦争兵器を飛ばす、これは特攻隊ではないけれど、今の中東で起きているような問題。一体どこでどういうことを考えて、そういうことをやらせたのかということは、一切、番組のなかには出なかったが、唯一、登戸の研究所が出ていた。大学のキャンパスは登戸研究所があったところなので、教授はおそらく、もう少しいろいろな資料を持っておられると思う。こういう重いテーマであるが故に、やはり根拠資料のところは時間を掛けても出来るだけ正確に表現した方が良いと思う。