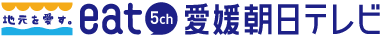第136回放送番組審議会議事録
開催日時:平成20年9月25日(木)午後3時
課題番組:①「四季の国~四国愛媛の碧く輝くとき」
②「裁判員制度導入にあたっての報道の責任について」
1.開催日時:平成20年9月25日(木)午後3時
2.課題番組:①「四季の国~四国愛媛の碧く輝くとき」
9月13日(土) 10時00分~11時00分(60分)
②「裁判員制度導入にあたっての報道の責任について」
3.議事の概要:
①「四季の国~四国愛媛の碧く輝くとき」
・今回は夏であり、四国は夏にぴったりな地域ですので、非常に良かったと思います。特に石鎚山の自然、沼、滝の紹介、素晴らしい自然が残っており良いと思い、爽やかな気持ちで見ることができました。一番印象に残っているのが、青島の盆踊りです。自然も良いですが、人口かつては700人いたのですが、それが30人となり、限界集落を思い浮かべました。年齢65歳以上の人が人口の50%を超えるところを限界集落と言うそうですが、それが日本に2000、3000あると言われています。いずれ消えていくところ、人がいなくなるところという位置付けです。まさに青島はそうだなという感じを受けました。お盆の時にだけ、若い人が帰ってき、お墓から先祖を背負って帰ってくるシーンがありましたが、そのような風習があるのかなと、初めて見ました。いかにも先祖を大事にしているなという印象を受けました。元気なおばあちゃんが沢山いましたが、この方たちがいなくなったらどうなるのかなという思いがしました。「愛媛の碧く輝くとき」とのことでしたが、寂しいというか、哀愁を感じました。だからこそ紹介が必要だと思います。また北条の沖に安居島町というのもありますが、そこも人口が少なく、かつては漁業、海運で盛んでしたが、時代の流れでこうなっています。紹介は良かったけれども、悲しさも感じられました。アナウンサーの語り、音楽はかつてのNHKの「新日本紀行」を少し連想しました。そのような作りで郷土を紹介するのは良いと思います。検証とまでは言いすぎかもしれませんが・・・離島の哀愁、良かったかどうかは別とし、個人的にそう感じました。
・放送されたのが、9月13日で、丁度夏が終わる頃で、番組を見て、夏が終わったな、と言いますか、夏のまとめのような感じを受けました。この夏に取材し、放送するから、丁度その時期になると思います。自然が沢山出てき、もっと大きい画面で見ることができたらと思いました。内容としても、難しくなく、ボーっとしながら家で点いていたら家族で見ると、かなり気持ちの良い番組ではないかと思いました。石鎚山ですが、何時間もかけて山を登り滝を見るというシーンは、かなり見ていて気持ちが良かったです。テレビの醍醐味は、一般人ができないことを代わりにやっていただくということにもあるので、日本の滝百選にも選ばれたという102メートルの滝の映像はかっこ良かったと思います。全体として自然と島の盆踊り、カルチャーの両方がミックスされてバランスが良いと思いました。愛媛と言えば、私のイメージですが、水不足というキーワードがあるので、そういう観点からのシーンがあっても面白かったのではないかと思います。
・自然番組は、各局からも出ています。BSからも結構出ています。そういう中でこの番組は静かな感動をよんだと思います。それは何なのかと思うと、やはり人との関わりで描いており、一番の成功の原因だと思います。ハイビジョン、BSでよくやっている、珍しいところをしっかりと撮ったものは意外に感動をよびません。地域に住んでいる人が、自然と関わり頑張り、その自然の良さを感嘆しながら活動しているというのが一番この番組の特徴ではないかと思います。ナレーションが良かったという意見もありますが、「新日本紀行」のようなナレーションは古いです。ナレーションがあったということを感じさせるナレーションは駄目です。ナレーションは裏方です。そういうことから言えば、あのナレーションが良いというのはなく、「新日本紀行」を思わせたのは少し良くなかったと思います。悪口を言っているのではなく、考え方として、ナレーションはそういうものだと思っています。愛媛県の人が見ていないところにカメラが行っていました。笹倉湿原、御来光の滝、私は両方とも行っていますが、行くのは大変です。湿原は一つ物足りませんでした。湿原はどんどん狭くなっており、あと何年かするとなくなると思います。2、30年前に論争がありました。遮断し保護すべきか、自然のものだから自然に任せておけば良いのか、それは決着が付かず、行政も手を拱いて、感心を呼ばないままに忘れられていると、それについて一言触れてほしかったです。どんどん狭くなってきています。4、5年で明らかに狭くなっているのが分かります。ディレクターが御来光の滝を仰いでいるのは、羨ましかったです。あのようなところに行き、皆に紹介してくれたということだけでも、素晴らしいと思いました。まだまだ色々ありそうだと思いました。これからも続けてほしいと思いました。
・段々良くなってきているような感じがします。1作目の時とは違いバラついた感じはなく、今回は3つのテーマに絞ってあり、「新日本紀行」の話がでましたが、音楽もテーマソング化していて、印象に残り良いと思いました。愛媛の夏、大澤アナウンサーから切り替わり、足摺海があり、最初に高知?と思いましたが、足摺宇和海の公園ということで納得しながら見ました。松山からそこまで行くのは距離があるので、めったに行くことができないので、自然の世界を見ることができて、すごくゆったりとした気分になり、行った気分になれて良かったです。水の中の可愛い生物を見るのが好きで、「こんなのがいる」という感じですごく楽しく見させていただきました。見ているだけで、滝の映像にしても、水中の映像にしても、マイナスイオンが出てくるような、そういう番組作りをこれからもされたら、今までの騒々しい番組とは違い良いと思いました。また、視聴者の中にはお年寄りや足の悪い方もいらっしゃるので、行ったような気分にさせてもらい、良いものがあるなということが発見でき良かったのではないかと思います。矢佐間アナウンサーの淡々とした、でも澄んでいる綺麗な声で、バックの青の風景にあった声で、私はすごく良いと思いました。今回は褒めてばかりですが、良いと思いました。
・スカボロー・フェアの音楽から始まり、このシリーズはこの音楽で始まるのだなと、何か一つ取り上げるテーマと共にテーマソングを選んでいるのが良いと思います。最初の海の「碧」の時に、夜中の海中であの映像を撮ってきているというのはすごいと思いました。またダイバーの方が潜っているのではなく、上がって海の動物の話の際、シンクロさせ小さい画面の表示がありましたが、その工夫が、逆に言うと海は綺麗で海を映しとけば良いというアイデアだけではなく、その中に、分かりやすくするヒントが隠されているという作り方がしてあり、良いと思いました。石鎚山に関しては、ありきたりな言葉かもしれませんが、美しかったです。私も大学生と一緒に、石鎚登山が授業科目であり、鎖も登りました。御来光までは行っていませんが、天狗の鼻までは行きました。滝までは行っていなかったので、何度か行った石鎚山でも、新しいものが見つかり良いと思いました。やはり自分の郷土なので、ぼんやり眺めていてもそれだけで満たされるものがある感じがしました。スタッフ力だという気がしました。「スタッフ頑張れ」という感じで、若い体力のある、活き良い、未熟でも、そういう若いスタッフを採っていただき、未熟者は未熟な割に、きっと山川海、谷底等に連れて行くと色んなものが見つかると思うので、冒険をさせてあげたら良いと思いました。DVD等にして販売されるのではないかと思っているのですが、その時にはDVD用の編集をされたら良いと思います。最後に、賛否両論がありますが、青島の盆踊りに関しては温かい感じのコメントで、踊りに関わる者として、嬉しいですが、ですが物足りませんでした。踊りの専門というのがあるのかもしれませんが、この盆踊りの良さが時間的に短く、表現しきれていないと思います。中学校の子供たちは、壁が厚いですが、それを一枚取ると、沢山出てくると思います。そこまで関わる時間がなかったのではと思います。もし、時間切れなのであれば、中途半端に画面にしないでほしいと思いました。盆踊り、民謡等は、ある程度第三者が必要です。第三者が、「こういう風情がなんとも言えないんだよね」という風に、外から触れてきた人に、少しコメントを言ってもらう方が良いと思います。「おばあちゃんのあの手の動きがね、心に返ってくるよね」という風な、何か第三者が見ての感想が、ある意味で踊りを光らせたり、美術、工芸等を光らせたりするので、できれば過疎、限界集落という問題点を浮き彫りにするのではなく、持っている踊りの素晴らしさ、青島の30人しかいないけど、幸せそうに暮らしているところ等を表現してほしかったです。心が痛くて、最後の7分はいらなかったのではないかと思っています。ですが愛を持って見ました。
・前回の滝雲のシーンは印象的でした。足摺岬まで足を伸ばし、愛媛の局が非常に枠を大きく捉えた良い番組だと思います。メッセージもしっかりしていると思いました。自然だけではなく、青島の心の問題にまで入っていこうとしており、起承転結ができていると思います。あまり言わなくてもよいのかなという部分がありました。「ちょっとした努力が必要だ」というナレーションは言い過ぎているくらい、十分伝わってきています。あまり言わない方が良いくらいの着地で良かったのではないかと思いました。石鎚山の瓶ヶ森の風景、良い財産だと思います。そんな「碧」少し薄れている面があるというメッセージがしっかり伝わってきたと思います。
・最近はテレビを見るのが嫌になってきていましたが、この番組は実際の放送を見るべきだと思いました。心打たれる情景が沢山出ていました。足摺宇和海の、アオリイカの産卵は感動しました。子供が生まれ波の中に泳いでいく光景、生命の誕生と命の大切さが、番組の中に非常に良く出ていたと思います。生きることの素晴らしさをDVDにし、小学校に回し、子供に見せてあげたいと思いました。今の子供はこのようなことを知りません。親が知らないので、子供も知らないというのが現状です。私は、家が色んなことをしていたので、子供の時は色んなものを買うなどしてよく知っていたのですが、自分の子供になると、そういうことを教えることがなかったので、子供に見せてあげると喜ぶと思います。感心して見ていました。珊瑚の上には、海水の温度が3度上がった為に海藻が付かなくなり、光合成ができないといった内容は、非常に生物の学問的な問題で分かりやすい情景で知らされていたと思います。石鎚山は前から登ってみたいと思っていました。車で行けるところまでしか行ったことがなかったので、色んなものを見せていただき、ありがたかったです。御来光の滝にカメラが付いて行かれる時に、上から石が落ちてくるのではないかとハラハラしながら見ていました。お怪我はありませんでしたか?ゴロンゴロンと落ちてきていたので、下にいたら大変なことになると思い見ていました。誰か包帯でもして帰ってきていないか心配でした。石鎚山の湿原は知りませんでした。素晴らしいものでした。青島の盆踊りですが、800名いた人が30名というようなことで、これが限界集落というのかなと思って感心して見ていました。私が小学校6年生の時に、中島の沖に津和地という島があり、そこはとても盆踊りが盛んなところです。小学校5年生の時の先生がそこの小学校の校長先生となり、盆踊りを見せてくれるとのことで、久米の小学校から10名くらいが行き泊まり、夜通し盆踊りをしていました。そのことを思い出しました。島の盆踊りは素晴らしいものです。もっともっと大勢の人にこのようなものを見ていただき、残すべきものは、愛媛県の財産として残すように、放送局に頑張っていただければと思います。できればテープにダビングし、DVD等に残し、各小学校に、中学校は少し大きいかもしれませんが、小学校の高学年くらいに渡せるようにできればと思います。
・随分前に石鎚山に登ったことがあります。とてもしんどい思いをして登りました。行こうと誘ってくれた方がいまして、その方が東京の方で、その機会はないと思い登りました。二度と登れないと今思っています。カメラを持って登られたということがビックリしました。もちろんカメラマンなので持って登らないといけないと思いますが。海の中の映像は、ボーっと見ていたのですが、黄色のハコフグが出た時は、私に宝物をくれたような感じがし、一番好きでした。青島の盆踊りを見た時、時代の流れを感じました。毛糸の帽子を被って、男の子が仏壇に手を供えていました。昔のおじいちゃん、おばあちゃんは「帽子と取りなさい」と言っていたと思います。このようにして、これも一つのファッションで流れたのかなと思いました。こういう風にして何百人もいた集落が30人くらいに減り、時を重ねてきているのかなと、あの映像を見たとき寂しい感じがしました。宇和海と石鎚山と青島の3つありましたが、青島は別の意味で、別タイトルで取り上げられるべきだと思いました。そうすれば青島はもっと浮き出てくるのではないかと思いました。宇和海と石鎚山と、もう一つ別の面の夏を表現されるともっと良かったのでないかと思います。ナビゲーターのコメントですが、もっとお洒落な言葉が見つからないのかなと思いました。実は2回見ました。1回目を見たときは眠たくなり寝ました。コマーシャルになると音が高くなるので目が覚めます。番組が始まるとまた寝てしまいます。寝てしまうような低い低音でずっとナレーション、音楽が流れていくのは、心地良いかもしれませんが、見ようという気持ちにはさせません。課題番組だと思い、今度は座って見ました。ナレーションのトーンが今回はとても気になりました。テレビの番組を見ながら寝てしまってはいけないと思います。全体的には良く、これを病院に入院されている方がご覧になられたら、良いなと思われたのではないでしょうか。石鎚山は登れないと思いますし、海の中にも入ることはできないと思います。また青島の盆踊りは昔の若く元気だった頃を思い出すと思います。小学校だけではなく、入院されている方にも見てもらいたいです。とても苦労を感じました。
・寝られるだけ癒し系の番組だと思います。見ていて寝ることができるという番組は、逆に考えると、それはそれなりに評価に値するのではないかという気もします。愛媛の財産である自然、文化を紹介し、癒し系の番組だと思います。このような番組も必要だと思います。素材は限りなく多くあると思います。これからも第4弾、5弾と期待をしたいと思います。
②「裁判員制度導入にあたっての報道の責任について」
・色々な角度から資料を頂き、BPOの報告の中にも、テレビが裁判員制度に間違った判決を出させるということになりはしないかという危惧から始まり、民放連は裁判員制度化における事件ごとに関する考え方を取りまとめています。しかし当たり前のことをずっと書いているという感じです。最終的に報道に関する考え方もありますが、ここで怖いことは、視聴者の興味を煽り、視聴率を考えるあまり、あまりにその基準から逸脱する危険性が潜んでいると思います。それを防止する為には、現場の人の協力、研修しかないのかなという気がします。これからのマスコミ関係者の責任が非常に重大になるのではないかと思います。
・一番責任があるのは司法です。まずこの時期にどうして制度を導入するのか、その主旨が法務省のHPを見れば出ています。裁判を身近なものにする、信頼を回復する等、もっともらしい主旨が書かれていますが、あまり知らない間に国会で審議されたのか、司法、行政、立法という「三権分立」なので、司法で勝手にやったのかと、立法で審議はしたのかという感じですらあります。審議はしているらしいですが・・・どうしてこの制度を導入しようとしたのかということを報道なりに、当局発表をそのまま伝えるのではなく、掘り下げて欲しいと思います。戦前も陪審制があったらしいですが、あまり評判が良くなく、中途半端に終わっているみたいです。各国、裁判員制度をやっている国がありますので、他国がやるから日本もやるというのか?それともここ近年の特に平成に入ってからの改革流行、何でも改革、改革と言い、その一環で司法も改革をやらないといけないとのことで、風潮に乗りやっているのか?逆に言うと今の司法は信頼性がないのか?という事も含めて、掘り下げてほしいと思います。報道の責任は、なるべく当局の発表とは違った、あるいはその奥にある本当の理由、狙い等を報道することが責任だと思います。また実際に始まった時の報道ですが、新聞の文字とは違い、テレビの力はあると思います。一般の国民から選ばれるのは6人だと思いますが、刑事裁判、重いものを、判決し、事実判定だけではなく、量刑まで決めるとのことですので、どんな気持ちでやっているのか、生々しく報道し、くじ引きで当り、当事者になった人の心境も報道してほしいと思います。そうすれば結局最後は前例にない、「今までこのような事件はこういう刑だから、これもこうする」となると、あまり改革の意味がないと思います。そのようなことを含めて、鋭く切り込んでほしいと思います。
・報道機関の責任は大前提として、裁判が終わるまでは無罪推定の原則が働くということを、司会者のみならず、多くのコメンテーターの方たちにもしっかり分かっていただき、発言していただきたいものです。現実では逮捕されると真犯人で有罪だという一般国民のイメージがあるので、その偏見を助長しないようにして気をつけていただきたいと思います。よくテレビのコメンテーターの方が、殺人事件や、何かが起きた時、非常に無責任なコメントをすることがあります。私の記憶がある限りでは、母親が息子に殺され、息子の友達が殺したという事案で、ワイドショーのコメンテーターの方が、その母親とその息子の友達との間に、なんらかの交際関係があったのではないかという推測をしてコメントをしていたのですが、実際、後追いで、本になったものを読むと、その事件は、実際は実の息子が虐待を受けていて母親を殺すにあたり、友達にそれを頼んだとのことで、全然違っていたわけです。しかし、その裁判で明らかになった事実そのものは放送されていなく、先のワイドショーだけを見たほとんどの人は、その事件はそういう事件だと思ってしまう可能性があります。先のコメントをした方だけでなく、コメンテーターの皆さんには、コメンテーターが言ったことは、どれだけ責任が重いのかということを分かっていただきたいです。逮捕された被疑者、被告人の人権を侵害しないような報道を心がけていただくことに加えて、被害者、被告人の家族について、プライバシーの問題には配慮していただきたい。広い意味での関係者の人権については十分配慮していただきたいです。また国民が冷静な判断ができるようにしていただきたいです。特に最近であれば、少年や成人の事件でも、残酷な事件が多いという感じで報道されていますが、実際そうなのか。数の統計がどこまで報道機関が把握してやっているのかが疑問です。実際は戦前、戦後も残虐な事件はあり、統計的に、平成のこの現代がその時代から比べ残虐な事件が飛躍的に増えているのかというと、実際の統計では増えていません。実はむしろ減っています。しかしながら報道機関が残虐な犯罪について大々的に報道することによって、国民は体感的に治安が悪くなったと、感じてしまう状況を作っているのではないかと思います。それによって国民の処罰感情が増し、厳罰を望む方向になっていくと思います。報道機関の方たちが、犯罪は増えているとコメント等をする時は、実際のデータを踏まえた上でコメントしてほしいと思います。裁判員制度自体も重要ですが、その後、犯罪が確定し、刑務所に入り、出て来た人たちがどのように社会に復帰していくのか、被害者の人たちが被害の回復にどのようにやっていくのかということを、トータルの視点で、裁判員ということだけではなく、犯罪を取り巻く環境、その後の人たちの生活等、幅広い視点から報道していただければと思います。裁判員制度については、始まっていない制度で問題はかなりあります。実際に始まったとしても、色々な問題が生じてくると思うので、それについてどのように制度改革をしていくのか、制度を改正していくのかということを、報道機関の方たちが建設的な報道をし、改善点を洗い出していき、問題点と指摘することが求められていることではないかと思います。裁判員制度となれば、国民が主体的に司法に関わっていくことになるので、法教育が非常に重要になってくると思います。法律的なものの考え方、法律の知識だけではなく、法的な、リーガルマインド、リーガルな思考パターンがどういうものなのか、教育として国民に分かっていただきたいと思います。そういう考え方、知識、情報を提供する番組、情報を提供する場を作っていく、例えばここにアクセルすれば、そのような情報が入りますというようなことも、法教育という観点からやっていくことも一つの責任ではないかと思います。
・正に今言われている通り、色々な本を読んでみても最終的には、事件を報道するという大きな目的は、マスコミは犯罪というものを取り上げて、その背景を探ることによって社会不安と解消し、再発防止に繋げる役目が本来の姿であるということが書かれています。事件の裏側を探っていくという報道姿勢が重要ではないかと思います。
・日本の政治が官僚指導型で、政府が変わっても殆ど政治が変わらないというようなことがあります。この司法制度の改革、極めて乱暴だという印象があります。つまり人の死に関することを扱うことになりますが、それを国民の納得が得られないままにスタートしようとしています。NHKの世論調査で77%が反対しています。そのようなものが来年の4月、5月に実際に行われてしまいます。乱暴だと思いますし、ゆり戻しがあると思います。後期高齢者医療制度も、麻生総理が、なかなか難しくて分からないと記者会見時に言っていました。その国の政治の流れをマスコミ、報道機関がどのようにチェックしていくのかというと、最近は後追いが過ぎるのではないかと思います。半歩先に出て、疑問を投げかけていく立場にあるのですが、それにしては少し勉強不足かなと思います。あらゆる面で、これほど難しい問題が多いので、後追いでも良いので、「ちょっと待て、おかしい。延期した方が良いのでは?」という話が当然出てきます。来年の4、5月に本当にスタートするのか疑問に思っています。当然国民の大部分が首をかしげていると思います。選挙の争点にはなりにくいです。賛成というと国民は怒ってしまうからです。報道機関というのは、国の政治の流れ、どこに位置していかなくてはならないのか、そのことが問われている問題である気がしています。この裁判員制度は特に裁判員になる人に裁判長が諮問し、死刑反対論者をコミットできます。死刑制度を維持する為に、必要なことです。死刑について、鳩山氏が悪口を言われています。そういうことがどうなのかということも含めて、命に関わる問題なのだということを、命に関わる問題を国民がやろうとは、けいけいに判断できません。それがどんどん決まっているということに疑問があります。そこを報道機関が厳しく問い詰めて欲しいと思っています。
・単語の意味すら分からない部分もあり、その程度しかない私が言う意見ですのでそれを踏まえてください。多分、来年スタートと言われても、「へ~そうですか」、年末くらいには選ばれた方に通知が来ますと言われても、「あ~そうですか」、私には関係ない、私のところには来ないという感覚でしか国民は思っていない、関心が持たれていないような気がします。渡部委員も言われたように、テレビは楽な情報源で、目で見るだけのものよりも、映像に加え、視覚聴覚の両方のインパクトはかなり大きなものがあるので、興味本位で事件、出来事を見ている者にとっては、左右されやすい状況になると思います。どの程度の事件をどのように扱うのかについても、私達は来た時に考えれば良い、対象に当ればその時に考えれば良いという程度しか考えていないと思いますので、基礎知識的な広報番組からしていただければと思います。裁判所のビデオみたいなものを作り、コムズ等で上映会をしていますが、そこに行かないと見ることができない、そのことに興味がある人しか見ない、本を買って読んだり、傍聴したり、そのような人は興味があるかもしれませんが、私達一般の人からするとかなり重い責任になるにも関わらず、興味、知識はない状態です。そういう部分を導入前に、導入してしまった後だと後手後手になってしまうので、知識的な事をもっと私達に投げかけてくれたらと、一般的な感覚として思いました。
・正に私もそうですが、他人事みたいな、あまり一生懸命勉強しようという事を思わない方が多いと思います。専門家故に過去の経験に捉われた判断となっていると考えることができると思います。逆に我々が出ることを肯定的に考えると、世間一般常識が裁判の中に取り入れていただける、専門家は過去の判例等を知り尽くした人が今まで、判事、弁護士、検事にしても、知識を持っているわけですから、逆に世間一般常識、常識がないと言っているわけではありませんが、そういった観点から意見を述べることは良い制度でもあるのかなという気もします。変に勉強するよりも、一般民間人としての意見を裁判の中に取り入れるという観点から考えたら面白いと思います。
・変に聞きかじた、知ったかぶりをするよりも、全くのゼロの状態で自分の心、感情をきっちり感じ取り、これだけ色んな人がいるので、それぞれ価値観が違い、そういうものを出し合っていき、お互いがそのことに対して歩み寄れるところを探していくという作業が、教育界にいながら日本の教育で一番足りていなかったようなところがあります。完璧な制度はこの世の中に存在しないと思っています。無知なところから、マイナス経験からプラス経験に、制度を使って日本人自体が変わっていくべき時だと思っています。今の若者のブログの書き込み、匿名ならあそこまで書くのかという、言葉の残虐性があり、それが裁判員となり、自分が匿名で語れるとなると、どんなことを言い出すか分からない、そのような部分があります。匿名制だから良いというわけでは決してなく、自分の発言にどれだけ責任を持てるのかというところも追求されると思います。従来の日本人は、議論が苦手でずっときています。それが新しい状況となり、苦手と言えない、何とかしていくという、日本人は一生懸命にやる時は一生懸命にやるので、私は一生懸命に裁判員制度をやるような気がします。そこに賭けてみたいと思いますし、例えばもし大きな問題が起これば本当に完璧な制度はこの世の中には始めからありはしないので、それを完璧な制度に近づけていく努力は、人というものの将来を考えた上で、やっていかなければならない大事な作業だと思います。
・まず司法の改革です。司法に風を入れるということが随分言われてきており、一番変わっていない黒マントを来た裁判所は非常に異様な空気があり、なかなか世間の風が入りにくい場所です。新聞記者が一番驚いたのが、裁判所の中の空気です。非常に古めかしい中で人が裁かれ、非常に異様な中で犯罪が再現され、罪が確定していくことを見ることはとても面白いですし、犯罪を非常にリアルに再現してくれています。曽野綾子氏は事件は知らないけれど事件を書くことが出来るという小説を沢山書かれていますが、全部裁判所の中で取材をしています。報道は小説家とは違いますが、それを記事にする場合は、裁判官はよく「この被告は社会的制裁を受けている」と言いますが、新聞テレビで報道され、家族を含めて、そのカタチで制裁に関わる側に私達がいるということで、それは重い作業ではあります。報道の自由といいながら、偏見報道をしないという事は最大のテーマであすので、面白く報道しているだけではないかと言われますが、各々のジャーナリストとしては、最大の悩みとなっています。事件にはそれぞれ性格があり、秋葉原のように動いていく事件は、マスコミ関係者が傍観者でいられるわけではありません。例えば学校の中で、子供たちが何人も殺され、その犯罪が確定していくまで、無策で良いのかというわけではなく、犯罪の性格によってはマスコミが報道していかなくてはなりません。ですから司法に市民の風、感覚を入れていくという制度は、大きなベクトルとしては間違えてないと思います。必要なことです。検査審査会もあり、市民の風、目線は司法を通されたものとは違う感覚を入れられる環境、そういうことで大きな前進だと思います。それからが問題で、公正な裁判という時の在り様です。どんな人がなっても良いのかというと、一定の面接があると思いますし、呆けた量刑を被せたりすることはあり得ないと、一応の仕組みが担保されていなければなりません。マスコミは偏見の報道をしないということで、チェック、テレビ、新聞各社の問題だと思います。ただし、なかなか大きな発生があるとそこに集って取材していくことが起こりますので、一定のルールが必要だということで、新聞協会がその裁判員制度の報道に対しての指針を出しました。それは偏見報道をしないことに尽きます。新聞協会が、8月に別冊で裁判員制度の取材、現被告から考えるというテーマで出しています。そこの中の、早稲田大学のカワニシという先生が、殆ど結論なのですが、努力をしないとどんでもないことになる、とよく言っていますが、「報道に関する国民の疑義に対して、新聞は伝達する情報が自由で民主的な社会における多様で多角的な討議の促進にどのように寄与するのか、を示すことが出来なければならない。新聞にはその各部があるのだろうか?そうであるとすれば個々の事実で若干の軋轢はあろうが、読者は支持するであろう」。偏見報道しないという覚悟はあるのかということ、それを貫いていてれば、司法制度が変わっていってもマスコミの国民的な支持はありえるだろう言っていただいています。朝日新聞も正に裁判員制度で連載をしていますが、一個人としては、検査審査会も嫌で、裁判員制度でお前やれと言われ、なりたいと思う人は少ないと思います。ですが言われれば一生懸命にやらなければいけませんし、今言った主旨から司法制度がより良いものに変わっていくという努力を市民としてやらなければいけません。マスコミとしてもこれをチャンスに公平裁判、裁判所の改善をしないといけないということをチャンスにしていかなければならないと思います。
・私は全く分かりません。裁判員制度が導入されるということをずっと前から聞いていましたが、「どうぞ私に当りませんように」と思っています。専門家に任せる方が良いのではないかなと思います。皆さんと意見が違うかもしれませんが、こういうことについて考えることは、私自身大変四苦八苦しないといけません。
・裁判官の先生の講演がありました。講演を聴いても言っていることが全然日本語と分からないような内容で、分かりませんでした。お話されている先生ご自身も分かっていらっしゃらないような、ちぐはぐな1時間を過ごした記憶があります。隣の人にも聞いたのですが、「何にも変わりませんでした」と言われました。結局4、5人にお聞きしたのですが、皆が何も分かりませんでした。それは裁判員制度が始まるよりも随分前で、お話している方はもちろん的を射たお話ができていなかったのかもしれません。裁判官は、私から見ると凄く偉い方で素晴らしい人間性をお持ちの方だろうなという想像があります。賢いから庶民のことが分かっていない、そこに裁判員として選ばれたその人たちが、それぞれの持論、意見を法廷で述べ、一つの判断の材料になさるのかと思います。私もどうぞ選ばれないようにと祈っている一人なのです。司法に風をと言われていましたが、これがどのように生かされるのか、発展し進展していくのかは、マスコミの方の報道で一般人は本当に色々左右されると思います。マスコミの使命、よくお考えになられて、一般人、賢くない私達にも良く分かるような、裁判員制度のこれからの在り方を、分かりやすく報道していただきたいと思います。なぜこういうことが大切なのか、必要なのかというところからの入り口、指導、道しるべとなる放送を願っています。分からない人にも分かるような報道からしていただき、皆が理解できるような足がかりとなるようお願いしたいと思います。
・全般的には、制度自体への意見が殆どだったような気がします。導入は決まり、来年から導入されるので、それに対するマスコミ、報道の責任に関すると、事件内容、情報源は、我々民間人は報道関係からしか入ってきません。正に一番怖いのが、純粋なニュースであれば良いのですが、ワイドショー的なものをよく見られている方は、事件自体を偏った見方をする危険性があると思います。ワイドショーの内容によって変わってくる危険性があるのではと思います。かなり重い責任がマスコミに科せられた、裁判員制度導入ではないかと思います。被疑者が犯人であるという像を作り上げてしまう危険性が出てくると思います。我々自身も報道された時点で、もはや犯人だろうというところからスタートしてしまいます。報道され、裁判になって初めて弁護士が登場しますが、弁護士の意見が報道の中に取り入れられているかというと、今の状態ではなかなか弁護士サイドの意見は反映されていないと思います。偏った、警察の発表が原点になってしまうので、そういった意味で、今後非常に報道には責任の重大さがあると、皆さんが言っていただいたのではないかと思います。
・まだ駆け出しの頃は逮捕されると犯人でした。呼び捨てで原稿を書いていました。「Aがあいつを殺した」、「Aが~した」という感じでした。今は被告と入れたり、発表元を入れたりしています。警察署の発表によれば等、警察もそうですが、国家権力を行使すれば公開が原則だと思います。警察が発表してくれなくなると、ややこしくなります。昔は検察庁が「Aを逮捕する模様だ」といったややこしい事を言ってニュースソースを隠していますが、国家権力のニュースソースを隠す必要はありません。善意で情報提供者を守るという、「検察庁がAを逮捕する模様だ」警察幹部くらいの表現はあるかもしれませんが、国家権力側の情報既得はなるべく止め、誰が発表したのかをきっちりしていきましょうという風潮は我が社を含め、どの社もそういう表現になっていると思います。どこからでた情報なのかきっちり書こうとなっています。ですが弱い人は守らないといけません。新聞社もこれを機に反省すべきは反省しようという空気はあります。