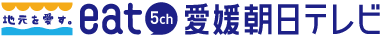第166回 放送番組審議会議事録
開催日時:平成23年9月26日(月)午後3時
課題番組:「テレビ朝日系列24社番組審議会代表者会議 議題:震災報道とテレビ報道について」
3.議事の概要:
・テーマが重いので、意見をまとめるのが苦手ですがお聞きください。「原子力発電所に関するメディア報道のあり方」について、今回のニュースを見ていて、原発に関しての用語は難しく、記者の方も限られた方しか十分な知識がないのだろうと思いながらニュースを聞いていました。日頃から記者のみなさんも色々な事に目を向けていただき、その場その場に起こっていたことに対して対処するのではなく、日頃からスキルアップなり、知識を身に着けていただいたらと思いました。同じ解説の方が何日も出続けているのを見ると、「この人寝る間はあるのかな?人手が足りないのでは?」と心配しました。出ているテロップと言い間違えて用語を発言した場合に、側にいるディレクターの方が訂正するように促してくださるとか、きちんとした内容を、「今言い間違えましたので~です」というようなことを、素早く訂正していただきたいと思います。どこの局だったのか覚えていないのですが、赤い淵のメガネをかけた解説の方がすごくよく出ていらっしゃったのですが、通常であればオシャレなメガネをかけた方だなと思うのですが、非常時だけに、そのような出で立ちで発言されると、信憑性を問われたりするので、発信する方の身なりはとても大事なことだと思いました。「震災時の放送で、テレビが伝えられたこと、伝えられなかったこと」について、今回の報道で一番印象に残ったのは、NHKの7時台のニュースで何日だったのかは忘れたのですが、階上(はしかみ)中学校の卒業式の様子を報道したものでした。必至に涙をこらえながら、卒業生の男の子が答辞で「苦境にあっても天を恨まず、運命に耐え、助け合って生きていくことがこれからの私たちの使命です」と言っていました。家族団欒でご飯を食べていたのですが、何も言えずに、もくもくと食べるのに集中して、胸に伝わってくるものがありました。大きな避難所はよく報道されるのですが、小さな避難所で本当に必要な支援物資について、NHKや民放各社で地域を分担して、「ここはこういうところが足りません」といったように、くまなく報道することはできないのかなと思いました。「被災者、原発被害者及びその家族などへの取材はどうあるべきか」について、報道だから何をしてもよいという訳ではないことは皆さんご承知だと思うのですが、撮影時のライト一つにしても、プライバシーなど、細心の注意を払うべきだと思います。何日も瓦礫の山を彷徨って身内を探し、その結果、悲しい事実と向き合わなければならないケースも多々あると思いますが、そんな方を取材するのに、ドキュメンタリー化しようなど、別の目的があるような考えで取材をすることだけはしないで熟考していただきたいと思いました。「震災からの復興にむけてテレビというメディアが果たすべき役割や可能性とは」について、私たちからすれば、もう半年と思うかもしれませんが、実際に被災された方々は、まだ半年しか経っていない、時の流れすら分からない方もいらっしゃると思います。前向きになってもらうようなことを提案するのはもちろんですが、無理に復興と追い立てなくても、精神面の整った状態で、私たち西日本が頑張っているところに乗っかっていただくような情勢を作れるような、抽象的で曖昧ですが、そういう西日本を活気づけることも考えていただけたらと思いました。無駄に電気を使って何時間も夜中放送をする番組は嫌いなので見ません。「震災時のコマーシャルの扱いについて」は、3月の番審の時点でもお話ししたと思うのですが、ACの音楽を聴くだけで頭が痛くなるような状況に今回なりました。CM挿入することが民放の宿命とはいえ、その枠を差しさわりがないACで埋めてしまったことは反省すべきだと思います。震災時は飛び込んでくるニュースを瞬時に整理して、正確に届けなくてはならないから、最初からつなぎとしてのCM、打ち合わせの為のCMの時間という風に取るのではなく、万事に備えられる番組体制、制作体制を作ることが大事だと思いました。今回、テレビだけではなく、ネットも見たのですが、やはり放送されないもの、放送できない映像が、ネットの上ですごくいっぱい転がっていて、子供たちには見せられないような映像もネット上にはいっぱいある中で、普段、テレビから流れてくる情報は一部だけなのかなと知らされ、どこかで都合よく制限されているのではないかなと懐疑心すら抱いたような気がしました。
・私は小学校4年生の時に終戦を迎え、松山の焼けたところ、被災したところを見ました。5年生の時に、祖父が大阪の被災した場所を見せてやると船に乗り、高浜から連れて行かれ、着いたら途端に向こうが見えるように焼け野原でした。それと重なりました。見るのが辛く、涙が出て、小学校の時のことを思い出し、どうにも止まらないという状態で見るのが辛かったです。その中で感じたことは、いわゆる記者の方が人の心の痛みというものをよく理解せずに、何でも聞けばよいというような感じで聞いている人がいます。年配の記者と若い記者とはインタビューの仕方が違います。若い人は色々な事をよく勉強した方がよいと思います。自分の仕事と重ね合わせてみて、私は料理のことなどよく聞かれるのですが、聞くときに全く知らない、聞き方も知らない、内容も知らないのに聞いてきて、こちらが教えてあげないといけないことがあります。そういうような聞き方があるのかなと思い見ていました。もう少し上手に人の心を逆なでしないようにインタビューするのも大事だと思いながら見ていました。「テレビが伝えられたこと、伝えられなかったこと」について、私が一番思うのは、村の放送があるのですが、それが全然聞こえない、自分が動揺している時は聞こえない、その時にテレビやラジオが伝える役目を果たしてもらいたいと思います。テレビ画面を真っ赤にし「危険だ」というような、何か瞬時に知らせることができないのか。ラジオでもそのようなことができないのかと思います。この度もテレビを見ていた人が、何も分からず、ぱっと出てしまった、出てみて津波が来ていた、というような方が沢山いましたが、もう少し何か放送関係で研究していただければ、もっと被災者がでなくて済むのかなと思いました。支援物資ですが、なかなか一か所にまとめて分配するのに時間がかかり、配達するのが遅れてしまう、そのようなことが多々あったと思います。私の方は2つに分け、学校に送る、赤十字の募金活動に参加する、というようなことをしましたが、やはり何か送る場所を取り上げ、「こちらへ送ってください、直接送ってください」というような方法もあってもよいのではと思いました。コマーシャルの件ですが、本当にもっと知りたいと思う時にぱっとコマーシャルが入ると、嫌だというような気がしました。大事なことが流れている時には、あまりコマーシャルは入れない方がよいと、コマーシャルが迷惑になる感じがしました。未だに胸の痛い毎日が続いています。
・体力的にも精神的にも非常に苦労が多かったと思います。現場に出向いた報道員の方に、まずは敬意を表したいと思います。今回、報道を見ているとタイムリーな報道の必要性を感じました。しかしながら、映像がライブか、少し前に起こった出来事なのか非常に判断がし辛かった。同じ場面が何回も流れるので、ライブの放送なのか、ライブであれば「LIVE」という表記を出す必要があるのではないかと思いました。インパクトのある場面を振り返り流しているというところが非常に見えました。また何日間か経って思ったのですが、同じ内容の放送ばかりが続いていた。各局すり合わせをして情報交換しながら、各局が違う放送の内容をしてはどうなのかと思いました。例えば、安否情報、ボランティア情報、物資の不足の情報、避難所の現況の報道など、局ごとに地域を分けて報道をする、テーマを分けて報道するといった方が、整合性がとれ、全体的に見て必要な事ではなかったのかと思います。各局が独自でどんどん取材をして流していく必要もあるのかもしれませんが、このような未曾有の地震の時くらいは、それぞれの局が共同しながら番組を作っていく、報道していくということが必要だと思いました。阪神大震災以降もそうですが、このような震災の報道は定期的にある程度編集しながら報道をし、記憶から消さないこともメディアの責任でもあるのかなと思います。しばらくすると人を救うために犠牲になった人、美談が流れていましたが、逆に自分の命は助かったが家族を失った人、自分を責める人間もいるので、美談の裏側、その裏にも悲劇があるということを考えながらバランスのとれた構成をする必要があると思います。どのように報道するのがよいのかは、私自身も正解という答えはありませんが、美談として取り上げるのはよいのですが、その裏にあることを心の中に、頭の中に入れながら番組を作っていただきたいと思います。福島の原発の問題は、早くて正確な情報が必要ですが、後で聞くとパニックを防ぐために報道を遅らせたということもあり、これはある程度、報道規制的なものがあったのかなと多少感じました。正確な早い情報は報道各局の義務。情報を流すということは義務ですので、報道規制というものはなかったと思いますが、原発事故の恐ろしさはチェルノブイリや色々取材をされた局も沢山ある訳ですから、その悲惨さを早く報道する必要があると思います。このような時には専門家が急に増えますが、どの専門家の言うことを聞いたらよいのか、なかなか判断し辛かったです。風評被害的なものはメディアの取り上げ方にも責任があると思います。被災者が最も必要としている情報と、番組視聴者が必要としている情報は共通ではない。どのような区分け、やり方をするのかは、正解はありませんが、優先順位をはっきりさせて情報提供、特にテレビを見ることができない被災地の為に何ができるのか、被災地ではないところにどのような報道をするのか、きちっと仕訳をしながら構成、編成をしていく必要があると思います。
・まず「原子力発電所に関するメディア報道のあり方」について、関東一円に放射能がばら撒かれた訳です。これでどの程度の人が将来癌になるのかまだ予測はつかない訳ですが、福島県では何人もが県知事から疎開させられ、かなり多くの人が被害を被っている。国策として原子力発電所の建設は行われてきた。今、世界でドイツが脱原発で舵を切り、どっちが正しかったかは何年か後に答えがでるだろうと思いますが、今あれだけの人が被害を受けて、ひょっとしたら私たちも放射能の入ったものを食べているのかもわからない。そういう可能性について国も考えなかったし、メディアもそれをチェックできなかったというところが、非常に大きな問題です。ある大きな国策なり、何なりを決める時に、チェックできるのはメディアだけです。その時に、基準にするのが世論調査で、しかも操作された世論を調査するので、40%、60%、そういうのを基準にしてやるので、メディアは結局世論に阿ることになるという指摘が50年も前にありました。それがいまだに続いています。そのメディアの責任というのが放送にはでてきていません。国の責任があり、それをチェックできなかったメディアの責任がありますが、メディアの責任は何なのか、何を基準に判断して放送すべきなのかということが、全然意識されていません。つまり放送法というのがあり、放送倫理規定があると思いますが、根底にあるのは、基本的人権です。憲法の中でも一番大切な基本的な人権の尊重というところが判断の基準になる訳で、例えば、1000万人の人が安い電力を買うことができるから、3人くらい癌になっても仕方がないということには決してならない。しかし多数決の論理で、今、世の中が動いている。ここが一番の問題点であると思います。同じことが繰り返されている。段々、また世論操作も行われ、そういうことをもって、脱原発の意識が薄らぎ、原発が復活するという風に見ていますが、それをチェックするのはやはりメディアしかありません。根底に必要なのは基本的人権の尊重。一人でも癌になれば、それは許せないという気持ちがないと、この報道としての責任は果たせないだろうと思います。「震災時の放送で、テレビが伝えられたこと、伝えられなかったこと」について、伝えられなかったことは実は分かりません。もっと色々と多分あるに違いないし、報道の操作はあっただろう、国のお粗末も色々あっただろう、きっと伝えられなかったことはあるだろうと思います。その1つは、義援金です。一部しか渡っておらず、7割はどこに行っちゃったのか?誰も伝えていません。私たちは街頭で何回も募金に応じましたが、それが被災者のところに届いていない。そのことのチェックもマスコミはしていません。「被災者、原発被害者及びその家族などへの取材はどうあるべきか」について、各社が勝手に行って、良さそうな人をひっぱってきてインタビューしていました。ここは報道協定の様になってしまいますが、被災者も、それに対応する団体を作り、そこから代表者を出す、一番ふさわしい人を出すなど、そのようにしていかないと、よくしゃべる人だけが、あるいはマスコミ対応が上手い人だけが画面に出てくる結果になってしまうのではないか。「震災からの復興に向けてテレビというメディアが果たすべき役割や可能性とは」について、100年に1回、大津波が来るということは皆分かっていて、また同じところに家を建てています。これは「やめましょう」ということを言わないと、それが一番マスコミが言うことではないだろうか。「震災時のコマーシャルの扱いについて」は、震災時に必要なコマーシャルはあったと思います。震災のグッズ、生水が飲めないからどうすれば良いのか?といったコマーシャルができたと思います。そういったコマーシャルが流れませんでした。災害にあっている人たちはテレビが見えず、災害にあっていない人だけがテレビを見るという状況でした。それが全体に言えば、この番組は誰に流して良いのかということが明確でありませんでした。避難所の一部ではテレビが1台くらいあったとしても、ほとんど見えないという状況が続いていたと思います。
・「被災者、原発被害者及びその家族などへの取材はどうあるべきか」について、被災者はかわいそうな向う側の人たち、取材する人や我々テレビを見る人間は幸せなこちら側の人たち、という感じを与えかねないような報道が時々あったような気がします。もっと厳しく言うと、見世物を報道するようなニュアンスを感じる時も無きにしも非ずでした。これは慎むべきではないか。被災者と同じ心境になるのは無理なのでしょうが、できる限り被災者の気持ち、現状を伝えてほしい。具体的には、バラエティーのような、ニュースショー番組のような、アナウンサーや解説者の方、コメンテーターの解説は、なるべく聞いた風な解説は止めていただき、被災者のありのままの声や、生の姿をもっと増やすべきではなかったかと思います。コメントが上手い、下手などではなく、下手でも上手くてもどちらでも良いので、本当にありのままの報道をもっともっと増やすべきではないかと感じました。「震災時の放送で、テレビが伝えられたこと、伝えられなかったこと」について、伝えられなかったことではなく、伝えなかったことだと思いますが、見るに堪えない現場です。多分それは亡くなった人の映像だと思いますが、これを外国メディアなどは伝えているようです。ネットでも伝えているようです。考えたのですが、やはり今回は伝えなくて良かったと思います。総合的に考えて・・・。ただしこれを機に、テレビは、楽しいことや面白いこと、明るいことを伝える傾向になるのは無理ないと思いますが、こういう大災害なので、人間の死、禍、不幸なことを直視した報道もやっていただいてもよいのではと思いました。生々しい死者の姿を送ることはやらなくてよかったと思いますが、人の死、2万人以上が亡くなっているので、そのことについては直視した、死と向き合った報道もあってよいと思います。こちら側の論理ではありませんが、幸せな側、何も被害にあわなかった側の無神経さを、ある時は報道同士で批判してもよいと思います。どの番組かは忘れましたが、東京電力が被害者に補償金を払うということで、その手続として書類を出してくださいと、福島の人に書類を配っていましたが、分厚い書類です。それに書くのは大変なことです。その発想は、東京電力の本社のぬくぬくとしたオフィスで、東京電力の都合のいいように書類を作らせるためにやり、全然被災者のことを考えていない。はらわたが煮えくり返りました。こんな無神経なことをよくやるなと思いました。そのことに関しては、その番組ではあまり言っていませんでした。書く側が「こんなものを配られてもしんどい」とか言っていましたが、ズバッと報道同士でもこの際、批判することは批判してもどうかなと感じました。
・新聞メディアの一員でもあるので、どうしてもそういった見方になるのですが・・・。最近は編集にいなかったので、違った見方になるのかもしれませんが、基本的には、映像メディアの力の大きさを実感したと思っています。活字メディアではあれだけの惨事を瞬時に伝えることができたかどうか、映像メディアの力を感じました。阪神大震災の教訓も随所に生かされていたのではないかと思いました。最初はどうしても衝撃映像が流れます。最初は分からないので、それを流して早く多くの人に伝えなければならないので、そういう映像が流れますが、徐々に被災者の声にシフトしていったように、自分も伝える側だからかもしれませんが、少なからずそちらにシフトしていったのではないかと感じました。被災者の人権に配慮した取材、報道はやはり見ていて、テレビの場合、アナウンサーやコメンテーターの人の発言による印象が大きいと思います。限られた時間内でコメントをするので、丁寧な言葉は難しいのかもしれませんが、割とその言葉のインパクトが強く、それが見る人、聞く人の印象に非常に残っているのかなと感じました。伝える中で、誰もが気を付けているとは思いますが、風評被害を防ぐ対策をその都度、頭に置いて伝えないといけません。ただ起きた事象を急ぎ伝えようとして、その映像、ニュースを流すことによって生じる波紋に思いを至らせないと、伝える側と違った方向に物事が動くということが今回もあったような気がします。この点は自戒を込めて言います。原発報道については、専門家によっても言うことが違うので、伝えるのは非常に難しい。ですが、何が起きているのかは、視聴者の方は非常に知りたい情報なので、それをいかに早く伝えなければいけないか、また丁寧に伝えなければいけないかということで、どの番組のどの情報がよくなかったのかということは、言うことはできませんが、今後の課題として、原発という物自体についての知識が伝える側に足りなかった訳で、その点を反省し、どういう風に伝えていけばよいのか、またこの原発報道は現在進行形ですので、今、視聴者の方にとって何が求められる情報で、どの情報が正しいのか、ここのところは難しいと思いますが、まだまだ模索しながら伝えていかなければいけないと思いました。レギュラー番組の再開が15日の夜からされた訳ですが、この時期はどうだったのか。テレビ東京が少し早かったと聞いていますが、ネットの力、報道する体制が各社によって、系列によって違うとは思いますが、ある時期からレギュラー番組に戻すタイミングは、どの時期がよいのか、あれで本当によかったのかどうなのか?私はあれでよかったのかどうかを、今この場で言う見解を持っていませんが、CMの流し方も含めてもう少し考える余地はなかったのかと思っています。視聴者の方は、十人十色で求める情報も関心も全然違い、色々な声があると思いますが、今回の震災報道の場合、常に動いていたので、2時間後にどのような番組、情報が流れてくるのか、なかなか掴みにくかったです。予定が立たない、どういう報道がされているのか、視聴者の側にとってボランティアや震災グッズ、原発、それぞれ求めるニーズが違った中でそれがいつ報道されるのか、なかなか掴み辛い期間があったと思います。テロップを使うなど、これからどのような報道がなされるのかというのがもう少し視聴者の人に分かり易く伝える手立てはないのかと思いました。視聴者の人が冷静迅速に行動するための判断基準をいかに伝えていくのか。正確な報道を、粘り強く被災者の方を支援する報道を期待しています。
・職業上、大学で教員をやっていますが、その立場から1つだけ原発問題については、個人的に考えたことを述べたいと思います。私は理学部物理学科出身で、「原爆を作るのは全然難しくない」と私の学生時代の先生はそういう風に話していました。原爆は、技術的に何マイクロセカンドでどのように爆薬を爆破させるのか、技術的な問題だと言っていましたが、そういう中で育ちました。私自身は愛媛県で育ち、伊方ができる前に愛媛を離れてしまいました。本当は戻ってくるつもりはなかったのですが、こちらに戻ってくると伊方原発が動いていた。その中で、反対運動の時に、当時、東京大学助手の宇井純先生がいつも来ていて、この先生の話を聞いている人たち以外の人たちも沢山いました。先ほどコメンテーターの方たちの話がありましたが、こういう大学という教員の世界にいると、教授から助手までランクがあります。その当時は私は教員でもなんでもありませんでしたし、どうなるのかよくわかりませんでしたが、こういう世界に入ってみると、東京大学で万年講師の医学部の先生など色々な人たちとお話しをする機会があり、なかなか社会はそう簡単ではない、本音のことを言えるかどうか、あるいは最近、涙を流しながら内部被爆の話をされている東京大学の医学部の先生がいらっしゃいます。自分の考えを学問的な知識と合わせて正確に公の場でしゃべれる人と、しゃべらないでおこうという人がいるということを、しばらく経って仕事を始めてから段々分かってきました。原発報道に関しては非常に不満があるのが、1号機、2号機と爆発して、3号機がプルトニウムで爆発しました。あの映像は1回流れたかどうか分かりませんが、1回くらい流れてあとは一切流れていないと思います。あとはどこかのメディア、海外のメディア、あるいはネットの世界で3号機が爆発している映像が出ていますが、この3号機のプルトニウムの爆発は、おそらく致死量に相当するものが沢山出ただろう。本当は大変なものだと思いますが、まさか報道規制はないと思いますが、なぜ流れていないのか?という疑問を持ちました。私は実はゼミで学生を何人か持っていますが、原子力の専門でも物理の専門でもない学生が、「先生、日本は危ないのではないのですか?」と聞いてきました。彼はどういうネットワークでそういう情報を得ているのかというと、彼はミュージシャンですが、結構有名なギタリストです。海外のギタリストとも付き合いがあり、海外のギタリストから情報が色々伝わってくる。そうすると日本には住めない地域がだいぶ増えてしまっている。海外からの情報ももちろん100%正しい、裏付けがあるという訳ではありませんが、そういう風に一般の学生でも危機感を持っている。そういう学生が実はあまりマスコミの報道を信用していません。こちらの方が問題だと思います。テレビの報道を信用しなくなってしまっている。おそらく新聞もあまり信用していないと思います。そのような若い子たちがいて、学生に質問されると、私自身も非常に悩んでしまい、一緒に色々考えるしかありません。大学教育という中で見ても、職業的に見ても、この原発の問題は今の日本社会に対して非常にすごい問題を投げかけたと思います。教育面でも大変な試練を受けてしまっている気がして仕方ありません。
・一つ気になったのは、東電の責任追及、批判、それが非常に今回は少なかったと思います。スポンサーの関係があったのではという話が、あちらこちらから流れてきます。情報はいわゆる原子力保安院などからの一方的な説明だけで、後手後手になっているのが事実で、ですから逆に言うと、先ほども言われましたが報道を信用しなくなってきた。「本当か?」という疑問形でしか受け取れなくなってきたというのは、非常にメディアにとっては自分たちの首を絞めることではないだろうかと思います。