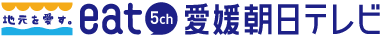第133回放送番組審議会議事録
開催日時:平成20年5月26日(月)午後3時
課題番組:全国番組審議会委員代表者会議課題テーマ「テレビ離れについて」
1.開催日時:平成20年5月26日(月)午後3時
2.課題番組:全国番組審議会委員代表者会議課題テーマ「テレビ離れについて」
3.議事の概要:
・このテーマを頂いた時に、色々な方に、「最近テレビ離れはどうですか?」と聞きましたが、普通通り見ている人もいますし、最近インターネットを使うからテレビ自体を余り見ていないという人もいます。最近はインターネット、パソコンでテレビを見ているという人もいます。「テレビ離れ」ということについては、色々な疑問が出てきますが、視聴率は1995年から2007年を見るとトータル的に全日で、ほとんど横ばいになっています。2005年の発行のある書物には「最近テレビ離れが進んでいますけれども」という書き出しがありましたが、配布された資料を見ますと、偶々でしょうか、確かに2005年だけ落ちています。その本は、一過性の現象だけを見て書かれたのではないかという気もします。確かに年齢層、男女等に分けて「テレビ離れ」が進んでいるのか分析したり、番組のジャンルにもよって視聴率が落ちているのかどうか見たり、いわゆる視聴率が落ちることイコール「テレビ離れ」と直ちに定義付けて良いのかどうか疑問はあります。視聴者の興味はテレビからどちらへ向いているのか等、色々な角度からみなさんのご意見をお聞きしたいと思います。個人的には、今は娯楽としてテレビだけでなく色々な選択肢があり、ちょっとでも興味がなくなるとテレビのチャンネルを変えたり、他のメディアに移行したりすることができます。視聴者にとって選択肢が沢山あるというところで、やはり番組の質が最終的にはテレビ離れを抑える一つのキーワードではないかと思います。
・テレビ離れと言われたときに、我が家のことを考えると、正にテレビ離れで、テレビっ子と言われた私でもテレビを消してしまう時間が大分長くなってしまいました。息子が、テレビでゲームするから貸してと言われると、見るものがないから、良いよと言って貸しています。どうしても見たい番組がニュースと重なると、二画面にして、音声だけをニュースにしています。つまり、1つのテレビを二人で分けています。テレビは合計6台あり、またパソコンをしながらテレビを見ることもありますが、テレビは音が出ているだけで、寂しさしのぎというか、テレビが点いているだけという見方しかしていません。かつては、朝起きてテレビをすぐ点け、時計代わりにし、昼は料理の情報を取り、夜はニュースを見てという生活の流れがありましたが、今は料理の情報にしても、インターネットでレシピを取れば良く、ニュースについても後からウェブサイトで見ても良いというふうに、代替となるものが沢山出てきているので、どうしてもテレビでなくてはならないということが無くなったことが視聴者の動きに影響を与えているのではないかと思います。テレビでなくても良いということについては、「あるある」事件などでテレビそのものへの信頼が揺らいできていることも原因の一つではないかと思います。また、wiiでネットしましょう、老人の方もwiiならできます、というような多機能化も影響していると思います。しかし、それにも増して見たくなるようなテレビ、自分が行くことができないような映像であったり、体験することのないものを見る、またスポーツ番組は、自分がその場にいなくては得られないもの、生放送で見て勝ったときの感動をリアルタイムで味わったり、感情を共有できるようなもの等、即時性があればテレビに向いていくのではないかと思います。テレビで見る番組がなくなってしまえば消すし、待機電力ですらもったいないと思うようになる。ぜひ見たいと思うような番組を作っていただくように考えていただきたいと思いました。
・テレビ離れと聞いて、電話のことを連想しました。いま固定電話が非常に減ってきています。ほとんど携帯電話に変わってきています。テレビを固定電話だと想定し、インターネットで全てまかなわれる世の中になるのかと言うと、それは絶対にありえないと思います。テレビにはテレビの魅力があり、インターネットと共存できるということが前提としてあります。私が小さい頃は、「早く宿題をしてテレビを見なさい」、「早くご飯食べてテレビを見なさい」と言われテレビを見ていました。実はテレビ離れというのは、テレビに対する価値観が変わってきたのではないかと思います。テレビ離れというより、テレビが好きだった人が減っているのではないかと思います。若者達は、視聴率、視聴者として考えた場合、あまり当てにしなくても良いのかなと思います。若い時代はテレビを見る時間や寝る時間を削ってまで、やりたいことが沢山あり、おそらく学生はテレビを全然見ていないと思います。見る時間もなく、アルバイトに行くことが多いと思います。そのようなことを考えますと、よほど、どうしても絶対に見ないといけないと思った番組だけは録画をしてでも見ていると思います。むしろ高齢化の世の中を考えると、中高齢者、特に高齢者の人にとって見たい番組がテレビの中にあるのかなと思います。病院に行くと、みなさんテレビを点けています。ですが、ほとんどが再放送で見たことのあるものでした。高齢者の方が見る時間の番組作りの安易さがあるのではないかと思います。在宅の方、高齢者の方達が本当に見て面白い番組、働いている人は夜10時以降しかテレビも見る時間がないので、そのような時間帯ではなく、もっと長くテレビを見る人のために、そういう時間帯に、何かできることがないのかを制作者は考える必要があると思います。学生たちは、「相棒」あるいは「ごくせん」などが好きで、はみ出した教師、はみ出した刑事といった規格外の人、心のどこかでそのような人を待望する、待っている、という思いがあると思います。ドラマにしても、巨大すぎる夢はいかがなものかと思いますが、何か待望しているものが、制作者側と視聴者側で食い違っているのではないかと思います。インターネットでも代用が利くものは、おそらくテレビからは自然になくなってくると思います。テレビはもっと中身を絞り込み、テレビが好きという人を増やす努力をしていく必要があります。ピンチをチャンスに変える時だと思います。
・私も大学の時はほとんどテレビを見ていませんでした。その事を改めて思い出しました。今になると、起きるとテレビをずっと点けっ放しにしています。テレビの音がなかったら寂しいというイメージがあるので、テレビの音が聞こえることによって主婦の方は安心感が出てくるのかなとも思います。年齢によって違うという事がよく分かりました。
・新聞のことに思いを及ぼしますと、いま活字離れが深刻な問題となっていて、学生のほとんどは新聞を取っていないと思います。テレビと新聞とで共通している事があり、これだけ情報の流通化、インターネットを介して、どこかにネタの元があり、それがグルグルとたくさん情報が流通する時代です。ですから新聞、テレビの影響力は、相対的に下がってきています。その辺の自覚が必要だと思います。新聞と絡めていいますと、テレビも総合情報化しており、新聞がニュースから娯楽にまで総合情報化した過程を経ましたが、テレビも、ニュースだけ、スクープだけ伝えるという時代ではなくなったと思います。権力監視、新聞の主な役割は、強気に屈しない、国民と共に立つ、反戦等大きな教訓の中にありますが、その一方で、巷の低い目線に記者は常にいることから、権力監視ができると思います。日常的に、権力監視をするわけではなく、目線を低いところに置きながら、市政の話を聞き取っていく、それはニュースと娯楽は切り離されたところにはないという切り替えで、テレビと新聞は共通してあるところだと思います。新聞は活字なので、若干テレビよりも、知性、読ませて分からせていくということが必要ですが、その点テレビは映像的効果が大きく、新聞よりも感性に訴えるツールがあり、インパクトの強い道具だと思います。仮にニュースを掘り下げていく機能がテレビの中にある限り、情報流通化の中で、影は薄れるけれども、テレビはなくならないと思います。新聞も同じことが言えると思います。引越しをした時、まず何をするのかを聞くと、テレビの環境を整えるのが第一で、テレビが点いたらここで生活できるという感じです。ですが、ここ数年はインターネットの環境の方が先という感じがします。ユーチューブ等見たい番組を見逃してもそこで見られるという意味でもテレビ離れの環境が進んでいると思います。テレビ離れについて若い方に聞いてみますと、「楽しみが沢山増えてきた、見る側が見たいときに見たいものを見る時代になった、家にいる時間が少ないがインターネットなら自分の好きな時間に自由に得たい情報を得ることができる、始まる時間を待って見なくても良い、見たい内容だけ見ることができる、テレビ離れはインターネットの手軽さ自由さの中で衰退していくのでは」といった意見がありました。ですが、ジャーナルの本質は、そしてテレビマン、新聞記者、ディレクターの魂は本当のところどこにあるのかを見せる、作らなくてはいけない、取材しなくてはいけない。伝えたいものは明確にどこかにあると思います。
・今の学生は、ほとんど新聞を取っていないと思います。インターネットを開くと前日の大きな事件、情報等が掲載されており、彼らなりに、きちんと情報を得ており、奥深くつっこんでいこうかと思うと、検索でキーワードを入れると、その情報が洪水のように流れてくるということで、逆に多すぎて、その選択に彼らの能力の違いが出てくると思います。
・テレビ離れについて、まず、テレビ番組を見ていますと、どこの局も慌てているような番組作りをしているような感じがします。テレビを流す事に対して慌てているような感じがします。次に、見たくないなと思う番組が多く、その理由を考えて見ますと、どこも同じ様な内容で、少し変わっているだけで、同じ中身のものが多いということがあります。どこかの局で流行ると、こちらの局も真似をするという感じです。もう少し丁寧に番組作りをしていただきたいです。番組内に出てくる人が、非常に乱雑な言葉を使っており、それが世の中に出て行くと子供が真似をし、嫌な感じがします。ラジオでも、めちゃくちゃな言葉を使っています。若者たち、お年寄りがどう見るのかということまで考えて、まともな番組、言葉使いをしてもらいたいです。また、世の中、仕事が沢山ありすぎて、働かされています。そのような人たちがテレビを見るのかというと、疲れて寝てしまうので、見る時間が無いのかなと思います。世の中の一つの流れだと思います。そのような人たちはインターネットを利用していると思います。社会の人の動きを考えた上で、中身を作っていかないといけないと思います。また老人はテレビを見たいと思う人が多いと思います。何が見たいのか、どのようなものが見たいかというと、昔のことを思い出す、良いドラマ等色々あると思います。その中で一番大切なのは、老人に「あなたは何が欲しいですか?」と尋ねると「健康が欲しいです、命が欲しいです」という回答が返ってきます。そのような人たちに元気付けになるような番組を作っていただくと、老人には喜ばれると思います。
・番組の質については、テレビのコストの問題があり、制作費の削減等により雑な、小手先で作っている番組が氾濫していると思います。視聴者が敏感に感じ取って面白くないと思うとすぐに消えていく番組も増えています。継続されている番組は、ある程度密度の濃い、きちんと作った制作者のポリシー、熱のこもった心のこもった番組はそれなりに評価をされていると思います。やはり質を上げる必要があると思います。
・テレビ離れという問題は、テレビ会社の経営者が考えるべき問題であると思います。民放にとっての問題はテレビ離れというよりも、広告離れ、CM離れであり、これは経営者が深刻に考えないといけない問題かと思います。広告はパソコン、携帯電話、ブログ等に流れています。教養性の高いもの、内容の良いものという話が出ていますが、いわゆる娯楽番組、馬鹿番組の需要も確かにあると思います。テレビでいつも堅苦しい、ハイレベルのものばかり見ていると、もっとテレビ離れが起こるのではないかと思います。時には、そのような番組はストレス解消にもなり、その効果も無視できないと考えます。そういう意味では、あまり堅苦しく考えることはないかと思います。ただ、活字離れという話もありましたが、テレビが出てきた時に、新聞という媒体はテレビに取って代わられるのではないかと皆心配していましたが、実際はそんなに取られていないと思います。本、雑誌があり、新聞も発行部数は少し減ってはいますが、そこまで深刻なものではないと思います。テレビ離れといいますが、中高年はテレビに噛り付いていますし、テレビがなくなることはないと思います。ただ、なくなることはないと思いますが、広告を独占的に取っていく時代ではない。将来的、経営的には考えておかないといけないと思います。特に民放は無料でも見たくない、欲しい情報はお金がかかっても欲しいということで、若者はそちらに行っています。魅力のあるものに流れていくので、その意味では先ほどから言われていますように、番組の内容で勝負しないといけないと思います。内容で勝負の時に、あまり質の高いもの、教養性の高いものばかり追求しても、かえって難しいのではないかと思います。ただ、テレビは全国一律に同時に見られますので、非常に情報の公平化には役立っている。教養のセーフティーネットという役割を果たしていると思います。そういう意味でもテレビの役割は消えることは無いと思います。視聴率呪縛が何とか解けないものか、確かに商売ですので、視聴率を無視するわけにはいかないけれども、上から順番にやると、悪貨は良貨を駆逐すると思います。良質だけれども余り見てもらえられない番組が、いま段々減っていく傾向にあると思います。どこかでルールを作り、最低限でも視聴率が低くても教養等で流すことができるようなシステムがあってほしいと思います。本でも、教養の高い、内容の濃い純文学が売れているかといいますと、売れていません。出版社を支えているのは雑誌であったり、タレント本であったりします。ハイレベルの人からすると見下すような内容かもしれませんが、それが飯の種で会社の屋台どころを背負っている現実があります。教養の高いものばかりやるということは、経営的にはどうかという部分は否定できません。その辺のバランスは経営者の眼だと思います。テレビ局の経営者は、文化性、経営性も見なければいけない時代だと思います。
・この何十年視聴者の視聴の仕方は全然変わっていません。つまり「ながら」です。それが数字に表れているのが視聴率です。視聴率の考え方をもう少し考える必要があると思います。送り出す方はある程度視聴率を考えながらやっていると思いますが、情報が多すぎる中での生存競争ですから、送る方も中身的に言えば何十年もそれほど進化していません。受け手、送り手両方とも進化していない中で、ハードだけが進化しているところに問題があります。ただ、ハードの進化はまたとないチャンスだと思います。送り手と視聴者の双方向性ともいいますが、簡単すぎて何も大したことはやっていません。しかし、ハードの進化をうまく使えるのではないかと思います。何でも長時間見てもらえれば良いというわけではありません。本当に見てもらいたいものを、こういう人に見てもらいたい番組を見てもらえるという番組を作ってもらえるのが一番良いことです。私もインターネットをやるようになってから、テレビの視聴時間は確かに減りましたが、これはという番組には印と付けてしっかり見ています。本当に良い番組を出し、視聴者にしっかり答えてもらえられるよう、視聴者と結びついて番組を育てていく、視聴者との結び合いのあり方を変えていかないと単なる視聴率だけでは、これからの進化はほとんどないような気がします。確かに実質的な本当の視聴率は減っていると思います。点けっ放しの人が多いと思います。ですが、こんなに沢山の人が見ているということはすごいと思います。見過ぎではないかというくらい見ています。例えば民放が団結し、ものすごく良い番組を出すと、普通1本1億円でやるのを、10社で10億円の番組を作ると見るわけです。そのような知恵が民放には欲しいです。NHKはお金を使ってやっています。世に残る、文化遺産になるようなものを出していくというのが、視聴率を食い止める良い方法だろうと思います。娯楽もそうです。視聴率を高めるというのは、視聴の内容を高める、視聴者を高めるということだと思います。見る時間を増やすのではなく、視聴者を育てるという思想が一方にないと、視聴率を高めることにはならないと思います。結局こうのは見てもらえられると思うだけであり、本当に良い番組は、こういうところが良いのだというのを視聴者に投げかけ、訴えて、視聴者も答えるものがないと、そこに未来は無いと思います。ただ流されている、面白いから少し見たということではこれからは生きていけないと思います。今までは、視聴者との関係が薄っぺらでした。視聴者に真剣に問いかけるような事をしていかないと、視聴者もこれまで通りテレビをつけてチャンネルをよく変えるくらいの見方しかしていかないとすれば、テレビという文化はもったいないと思います。
・私の場合は、毎日が忙しいので、テレビを点けっ放しにしてボーっと何かをするという時間はなかなかありません。テレビ離れがあるということについては、好きな時に好きなものを見るというふうに現代の人たちはわがままになっており、どうしてもそれを求めてしまうところにズレがでていると思います。テレビ番組を見るとしても、インターネットやユーチューブで好きな時間に好きなもの、番組を見るという風になっていると思います。しかし、テレビでないとできないものが沢山あると思います。同じ時間に同じ情報を多くの人に流すのはテレビにしかできないことだと思います。例えば、中国の地震では、インターネットのニュースでは文字と写真だけですが、テレビのニュースであればリアルタイムでどれだけのことが起きているのか映像で流すことができます。これは、テレビのニュースのすごいところだと思います。テレビのニュースでとりあげることによって、例えば一般の人に対して、犯罪の予防ができます。また、「振り込め詐欺」のように、犯罪の手口等の情報を知らなければ引っかかってしまうということがあります。実際に、テレビのニュース等で取り上げられることによって、手口がかなり認知され、弁護士のところに相談に来る人も減りました。また自分の名前で新しく通帳を作り、それを第三者に売ると犯罪になるということを認識できない若者がいます。多くの若者がアルバイト感覚で、通帳を作り、売って逮捕されたということがありました。そういうことも、ニュースを通じて報道されることにより、そのような銀行口座が振込み詐欺等に使われ、犯罪になるということが認知されてきました。ワーキングプアの問題も各種の番組で取り上げられており、何らかの世論を作っていくには、テレビが大きい役割を果たしていると思います。テレビ離れを食い止めるには、良質な番組を作り、それも見たいなというものであることだと思います。例えば若者に対しては、キャリア教育等、将来どのような仕事があり、それに対してどのようなことをすればその職業に就けるのか、どういう世の中で役割を果たせるのかを映像で具体的にやっていただくと、家族で見れば団欒にもなります。また消費者教育を含めてテレビの力で文化、教育の底上げをするような番組をつくっていただければなと思います。中高年に対しては、団塊の世代の方が引退され、その方たちのテレビを見る時間が増えると思いますので、その方たちが、どのように生活をしていくのかについて特集した番組があればと思います。
・テレビ離れが始まったことについては時代的な要因があると思います。各年代に関係なく忙しすぎると思います。子供の頃はテレビが珍しく、近所の人が集まって見るという時代でした。テレビで放送され、見たことが次の日の学校で話題になるという時代でした。今はそういうのが少しずつ薄れているのではないかと思います。時代背景が違ってきたのではないかと思います。やはり最近感じるのが、各局のカラー、特性が薄れ、どこのチャンネルにしても、似ているのではないかと思います。特にお笑い系の番組は内容の低劣さが目立つと思うのですが、その中で特に嫌な思いをするのは、ものを知らないことが可愛いことであるかのように見せようとすることで、無知というのが恥ずかしくないかのような状態になっていることです。良い意味での知性、知識を身に付けさせてあげるということも、テレビの大きな役割だと思います。昔テレビに出演するとなると、隣近所、親戚等に声を掛け合って見た時代でした。ですが今はみんなが出演者になり、一般の出演者のほうがプロよりうまかったりします。また、女性アナウンサーのタレント化があまりにも最近目に付きます。しかし、テレビは絶対になくならないし、なくなってはいけないものだと思います。インターネットで配信されるものもありますが、インターネットの使えない人も居ます。また、インターネットで配信されたものではなく、同時にたくさんの人に放送されたものを見てどう受け止めるか、それは視聴者の自由ですけれども・・・テレビ離れしている状況はあるとは思いますが、テレビは絶対になくなってはいけないものであり、なくならせてはいけないと思います。そしてなくならないものだと思います。活字離れはよくありますが、読んでいる人は読んでいますし、読まない人は始めから読まない、テレビも見ない人は見ない、見ている人は見ています。昔、歌謡番組が盛んだった頃が良い時代だったテレビの最盛期で懐かしい思い出になりました。